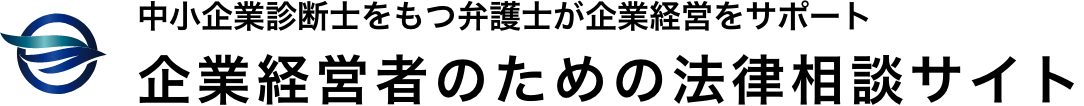問題社員とは
問題社員とは、社内の規律や業務命令に反する言動を繰り返し行うことで、会社内の就労環境を悪くさせたり、能力不足、協調性不足、勤務態度不良といった問題行為を繰り返す社員を言います。モンスター社員とも呼ばれることがあります。いずれも法律的に規定された用語ではありませんが、問題社員に対する適切な対応ができなければ、会社内に様々な問題を生じさせます。
以下では、問題社員に対する適切な指導に関して解説しています。
問題社員の解雇に関しては、以下のコラムでも解説しています。
解雇一般についてはこちらのコラムをご参照ください。
問題社員に対して適切な指導が必要な理由
就労環境の悪化
問題社員が社内にいる場合、この問題社員と同じ空間で仕事に従事する、その他の従業員の就労環境を悪化させます。想像してみてください。職場にパワハラをする上司がいます。この上司からパワハラを受けている従業員は当然のことながら精神的な苦痛を受け、その就労環境を悪化させます。それに留まらず、直接の被害を受けていない従業員も、パワハラが常態化する空間での就労を強いられることになります。
このように、問題社員が社内にいると周りの従業員の就労環境を悪化させ、これによりモチベーションの低下→会社に対する忠誠度の低下→離職という結果を招きます。
新たな人材を確保できない
問題社員を放置することで、その他の従業員の忠誠度が低下するという話をしました。
このような状況を漫然と放置すると、在職中の従業員も含めて、SNSで会社に対する不満を発信したり、転職会議などの掲示板に会社の悪評を書き込むといったことがなされることがあります。SNSや掲示板を通じて会社の信用を毀損する情報が発信されると、不特定多数に情報が流れてしまい、収拾が付かない事態となります。
転職希望者は、転職時に必ずと言っていいほど、インターネットを通じて転職先の情報を収集します。万が一、インターネット上で貴社の悪評に触れることができる場合、貴社への転職を敬遠する転職希望者も出てくることでしょう。
このように問題社員の放置は人材の確保も困難にさせます。
損害賠償のリスク
問題行為のうち、パワハラやセクハラのように被害者がいるような類型の場合、問題社員を雇用する会社が適切な対応をしないと、被害を受けた従業員から損害賠償請求を受ける法的なリスクがあります。社内だけでなく取引先対するハラスメントについても同様です。
ハラスメントを行なった従業員が被害者に対して損害賠償責任を負うことは分かりやすいと思います。
さらに、ハラスメントそれ自体を行なっていない会社も加害従業員と連帯して損害賠償の責任を負います。なぜなら、会社は従業員を雇用することで利益を得ている以上、その従業員の言動によって生じた損失も負担するのが公平であるという考え方があるからです。
損害賠償の対象は、治療費だけに留まらず、休業している場合には休業損害、通院に伴う慰謝料、後遺障害が認定される場合には逸失利益などが含まれますので、損害額が予想以上の金額まで膨らむことがあります。
そのため、会社としては、問題社員に対して適切な指導、懲戒処分、教育の機会の付与といった、ハラスメントを防止するための措置を講じておく必要があります。
解雇のハードルが高い
問題社員を放置することに伴う様々なリスクは解説してきたとおりです。
それでは、問題社員を解雇すれば良いのでは?と考える方もいるかもしれません。
しかし、早まって問題社員を解雇してしまうと、思わぬ経済的負担を強いることになります。
懲戒解雇や普通解雇が有効となるためには、合理的な理由があり、これを相当とする場合であることを要します。つまり、解雇処分は従業員としての地位を失わせるため、非常に不利益の程度の大きい処分です。そのため、このような不利益を受けざるを得ない程に重大な非違事由がない限りは、解雇は有効とはなりません。
数回の遅刻や無断欠勤を理由に解雇する場合、能力不足を理由に解雇する場合、一回のパワハラやセクハラを理由に解雇する場合、行き過ぎた処分として無効になる可能性が高いです。
解雇が無効となれば、半年から一年分の給与(バックペイ)や解決金といった金銭を支払いをする必要が生じます。また、労働審判や訴訟にまで発展すれば、会社の信用を毀損するような情報が発信されるリスクもあります。
そのため、問題社員であることを理由に、安易に問題社員を解雇処分をすることは、会社に重大な負担を生じさせるおそれがありますので、慎重な対応が必要です。
問題社員に対する指導方法
問題の把握について
問題行為の類型のうち、遅刻欠勤、能力不足、業務命令違反といった類型については、問題行為それ自体の有無に関する調査はそれ程難しくはありません。
他方で、秘密裏に行われるような問題行為、例えば、会社の備品の横領行為、セクハラやパワハラ行為、経歴詐称といった非違行為については、何らかの情報提供が調査の端緒となりますが、直ちにはその非違行為が存在していることが明らかになるわけではありません。そのため、このような類型の問題行為の場合には、その有無に関する調査を尽くした上で、問題社員に対する聴き取りを行う流れになります。調査方法について後述します。
電子メールの閲覧調査
問題行為の調査をする過程で、電子メールの内容を閲覧する必要が生じることがあります。この調査方法が対象者のプライバシー権を侵害するのではないか、という問題が生じます。
しかし、会社には企業秩序を維持する権限が与えられています。そのため、電子メールの内容を確認することは認められます。
しかし、電子メールのチェックも無制限というわけではありません。例えば、①メール内容を確認する業務上の必要がないのに、興味本位からメールを確認する、②メールが私的利用されていないかを確認する立場にないにも関わらず、メールをチェックするような場合には、電子メールのチェックはプライバシーを侵害する違法な調査となる可能性があります。
聴き取り調査
聴き取り調査の前に行った調査によって、問題行為の概要を把握し整理するようにします。関係者からの聴き取り調査が有益なものとなるよう、客観的資料から認められる事情を時系列に沿って整理したメモを作成するようにします。
聴き取り調査の下準備ができれば、関係者から話を聞いていきます。パワハラやセクハラのように関係者が複数いる場合には、まずは被害者→上司・同僚→行為者本人の順に聞いていくようにします。
面談時の注意
行為者から事情を聴き取る面談時の注意点ですが、同席する人数は1人あるいは2人に留めておき、必要以上の人数を同席させると、圧迫的な面談となりますので注意を要します。例えば、行為者本人が一人であるのに対して、企業側が5人程同席して、その大部分が取締役等の経営陣である場合、圧迫的な調査であったとしても供述を強要されたと主張されることがあります。
また、行為者の心理的負担を緩和させるため、企業側の担当者のうち1人は行為者とは異性の方を同席させる方が良いと言われています。
さらに、面談時の発言にも注意が必要です。後述する注意指導の際も同様ですが、ついつい熱くなるあまり、行為者に対して暴言を吐いてしまうことがあります。面談時には、行為者が秘密録音している可能性が十分にありますので、録音されていることも視野に入れながら十分に言動には気をつけましょう?
注意指導
従業員の問題行為が聴き取り調査、客観的資料及びその他状況から認めることができる場合、問題行為の内容が懲戒する程に深刻ではなく、これまでに懲戒歴もないのであれば、その従業員に対して注意指導を行います。軽微な事案であれば口頭による注意指導でも結構ですが、できれば注意指導に至る具体的な理由も記載した書面を併せて交付しておくことを推奨します。これは、事後的に裁判等の係争となった時に、口頭では十分に問題行為の内容や経緯を証明できないリスクがあるからです。
注意を要するのは、注意指導、特に口頭による指導が行き過ぎると、かえってパワハラになるリスクがあります。注意指導の中で、ついつい業務とは関係のない事柄まで指導が及ぶ、例えば、お前はバカ、ブス、小学生以下といった人格に対する言動はパワハラに該当し得るでしょう。さらに、少しのミスであるにもかかわらず、注意指導が熱くなるにつれて、指導者が感情的になってしまい、大きい声を挙げたり、机等を叩いたりしてしまうと、パワハラに該当する可能性があります。加えて、直接的な暴力は当然のことながら、相手に当たらないように物を投げつける行為も暴行になりますので、パワハラ行為となります。
そして、暴力や暴言がなかったとしても、一つの問題行為に関連して、1時間以上個室内で叱責し続ける行為もパワハラに該当する可能性がありますので、気をつけましょう。
業務日報の作成
問題社員の改善のために、業務日報の作成を推奨しています。特に、パフォーマンスの低い社員や顧客からのクレームの多い従業員に関しては、業務日報の作成により改善が期待できます。
問題社員の中には、自分自身の問題点を意識していない人が一定数います。そのため、会社から当該問題社員に対して指導をしても、全く響かないということがあると思います。
このような問題社員に関しては、指摘されている自分自身の問題点に気づいてもらうために、業務日報の作成を指示します。業務日報は、30分から1時間刻みで、業務内容の詳細を記載してもらいます。これによって、1日の就労時間において、具体的に何をどのくらいの時間をかけて行なっていたのかが見える化されます。業務日報の内容を基に1週間から数週間の業務内容を一覧にすると一層分かりやすくなります。
また、従業員に一方的に作成してもらうだけではなく、会社側のコメント欄に上司によるコメントを記載してもらうことで双方向にコミュニケーションが行われるようにします。決して感情的なコメントをしないように留意してもらい、淡々と問題点を指摘し、これを改善するためのアドバイスを書いてもらうようにすることが肝要です。
教育の機会を与える
問題社員に対して、注意指導をしたり、業務日報の作成を指示することも非常に重要ですが、問題行為を改善させるために教育の機会を与えることも大事です。上司や同僚が問題社員に対して直接、技術指導などをすることもあれば、社内または社外の研修・セミナーを受講させてスキルアップさせることで、能力不足等の課題を解決させます。
懲戒処分
懲戒処分とは
業務日報の作成や注意指導といった手を尽くしても改善されない場合や軽微ではない非違行為に及んだような場合には、懲戒処分を行います。
懲戒処分は、注意指導とは異なり、企業秩序に違反した労働者に対する制裁罰です。
就業規則の定め
懲戒処分を行うためには、就業規則に①どのような行為が懲戒処分の対象となるのか、つまり、懲戒事由を定めるとともに、②懲戒事由に当てはまる行為をした場合に課せられる懲戒処分の種類と程度を規定することが必要です。
一事不再理の原則
一事不再理の原則とは、一度懲戒処分の対象となった問題行為を理由に再度、懲戒処分を行うことができないというものです。つまり、一つの非違行為に対する懲戒処分は一回きりということです。例えば、1月10日の遅刻について、1月11日に戒告処分をした後、1月12日に減給処分をすることはできません。
ただし、後日の別の問題行為に対して懲戒処分を行う際に、過去の問題行為を考慮して処分内容を決めることは認められます。
懲戒事由に該当するかを判断する
先程解説しました問題行為の調査手続を経た上で認められる事実関係が懲戒事由に該当するかを判断します。いくら問題行為があったとしても、それが就業規則の懲戒事由に該当しないのであれば懲戒処分を行うことはできません。
懲戒事由の解釈については、できる限り限定的にする必要があります。つまり、企業側の裁量や主観的な意図から懲戒事由の文言を広く解釈させることはできません。
懲戒処分の選択
仮に問題行為が就業規則上の懲戒事由に該当したとしても、あらゆる処分を付すことができるわけではありません。
問題行為の内容やこれによって生じた被害の程度、行為者の職位、これまでの処分歴といった様々な事情を十分に考慮します。また、処分の前に、行為者本人から言い分を聴き取り、反省の弁を述べている場合には、これも考慮します。
その上で、これら事情に照らし処分内容が重すぎることのないように処分内容を選択します。当然ながら、就業規則に規定されていない懲戒処分を行うことはできません。
懲戒処分の種類
以下では解雇などの処分と比べて比較的軽めの処分について紹介します。
譴責・戒告
譴責とは始末書を提出させて将来を戒める処分です。戒告とは、将来を戒める処分ですが、譴責とは異なり始末書の提出はありません。
いずれの懲戒処分も、それ自体によって経済的不利益を与えませんが、昇格、昇給、賞与といった人事評価において、マイナスの評価事由として考慮されるのが一般的です。
減給
減給とは、労働者に対して支払われる賃金から一定額を差し引く制裁です。無制限に減給処分を行うことはできません。労働基準法91条において、減給額の制限が付されています。具体的には、一回の問題行為に対して行える減給額は 1日分の給与の半分を超えることはできません。半分を超えない場合でも、一回の問題行為を理由に1日分の給与の半分に達するまで何度も減給ができるわけではありません。また、複数の問題行為があったとしても、その総額が一支払期における給与額の10分の1を超えることもできません。
賞与の減額
制裁として労働者の賞与を減額する処分です。
賞与にも色々な種類があります。
ここで過去の懲戒処分を理由に賞与の査定をすることが一事不再理(二重処罰)の原則に反しないか?という問題があります。
賞与には、①毎月の固定給のようにあらかじめ決められた金額が支給される場合もあれば、②賞与の支給の都度、人事考課により査定される場合もあります。仮に①の場合であれば、一度処分を受けた問題行為を理由に賞与を減額すると一事不再理に反する可能性があります。他方で、②の場合には、人事考課において過去の処分歴を考慮して査定をするわけですから、一事不再理に反しないといえるでしょう。
退職勧奨
会社が問題社員に対して繰り返し指導や処分を行ったにも関わらず、改善しない、それどころか悪化するような場合、退職勧奨を検討せざるを得ません。退職勧奨とは、会社が従業員に対して、雇用契約を終了させるために、退職を勧めることです。あくまでも、従業員の自由な意志によって判断されるものです。そのため、執拗に退職勧奨をしたり、強い口調で退職を迫ると、退職勧奨ではなく退職強要に当たることがありますので注意してください。
退職合意書の作成
退職勧奨の結果、従業員が退職の申し出をしてきた場合には、退職合意書の作成を忘れないでください。退職後のトラブル、例えば、退職ではなくて解雇された、退職を強要されたなどのトラブルを未然に防ぐためにも、退職合意書は作成しましょう。
退職合意書には、
- 合意により退職すること
- 退職日
- 給与や退職金の支払い
- 貸与品の返却
- 秘密保持義務
- 競業避止義務
- 権利関係の清算
といった各事項を盛り込むように工夫してください。
解雇
退職勧奨をしても解決できない場合には、普通解雇や整理解雇を検討します。ただ、先程解説したように解雇はとてもハードルが高いため、余程の事案ではない限り有効とならないため、その点を十分に留意してください。
問題行為の累計別対応
遅刻欠勤などの規律違反
遅刻や無断欠勤のような事例の場合、その問題行為の有無が問題となることはほとんどありません。
会社としては遅刻や欠勤を漫然と放置することなく、その都度注意指導を行います。
改善されない場合には、文書や電子メールを用いて厳しい注意指導を行います。
文書や電子メールには、遅刻や欠勤を行ったことに加え、これまで再三にわたって遅刻や欠勤に対して注意指導を行ってきたが、改善されていないことも記載するようにします。
それでもなお、遅刻や欠勤が止まない場合には、懲戒処分を行います。懲戒処分にあたっては、対象社員と面談を行い、遅刻や欠勤を繰り返す理由を聴き取り、遅刻欠勤に正当な理由があるのかを確認します。もし万一、遅刻等の理由が、会社内のハラスメントや会社側の事情である場合には、懲戒処分ではなく遅刻等の理由となっている事情を解消する必要があります。
能力不足
遅刻欠勤といった勤務態度不良や業務命令無視といった問題行為は客観的に認定しやすいです。
他方で、能力不足については、そもそも何をもって能力不足と評価できるのか、画一的な基準はなく、主観的な評価が多分に入り込みやすいものです。
そのため、能力不足を理由とした解雇は原則として難しいと考えるべきです。 特に、新卒採用の場合には、能力を有することが雇用契約において求められていないため、能力不足を理由とした解雇や処分は困難と言うべきです。
そのため、パフォーマンスの低い従業員に対しては、①定期的に面談を行い、②適切な教育の機会を与える、③業務日報の作成を通じて能力不足の原因を追究するなどして、能力不足の改善を図ります。
それでもなお、改善が見られない場合には、配置転換を行います。
配置転換をする際には、配置転換を行う理由を具体的に告知しなければなりません。
配置転換を行う理由が能力不足であることを正確に告知しないと、配置転換を受けた理由をよく分からず、改善に向けた努力をする機会を失ってしまうからです。
配置転換を経ても、やはり能力不足が改善されない場合には、退職勧奨を行い契約関係の解消に向けて対応する他ありません。
協調性不足
会社という組織は、複数の従業員が協力し合って労務提供することで、会社の目的を達成させるものです。そのため、従業員には、他の従業員と協調して就労しなければなりません。
しかし、協調性を欠くことは、能力不足と同様に主観的な評価が多く入り込むため、事後的な証明が難しくなることが多いです。
そのため、協調性の欠く言動があった場合に、その都度、上司や同僚がメモを作成したり、電子メールや報告書により事実関係を記録しておくことが必要となります。また、問題社員に対して実施した指導教育の内容についても記録化しておくようにします。
その上で、協調性を欠く言動が止まない場合には、配置転換を行います。先程と同様に配置転換を行う理由を具体的に告知します。根気強く面談や指導教育、再度の配置転換を行ってもなお改善されない場合には、退職勧奨を行い契約関係の終了に向けた対応を行います。
問題社員を採用しないためには
試用期間
問題社員を採用しないようにするための方策としては、試用期間を設けることです。
試用期間とは、本採用をする前に正社員としての適格を判断するための試みのための雇用期間であり、その法的性質は解約権留保付の雇用契約であると解されています(三菱樹脂事件・最高裁昭和48年12月12日)。
面接当初は従業員の適格性を知ることをできなかったものの、試用期間を通じて出勤状況、勤務態度、能力等に関する問題点を把握するに至り、本採用することが適切ではないと判断できる場合には、解約権を行使して本採用を拒否することが考えられます。
本採用を拒否する際のポイントは、具体的な客観的根拠を示すことができるかです。単なる主観的な理由で本採用を拒否することは許されません。また、本採用を拒否するにしても、試用期間の数日前に告知するのではなく、予め早い段階から面談を行い、従業員の問題点を指摘した上で改善に向けて指導教育を行うようにしましょう。さらに、当初の試用期間だけでは十分に判断できないケースもありますから、就業規則や雇用契約書に試用期間を延長できる規定を設けるようにしましょう。
有期雇用
試用期間を経て本採用に至った後、問題行為を把握することができた場合、余程の事情がなければ有効に解雇することはできません。問題社員を雇用し続けることは会社に対して様々な負担を生じさせます。そこで、試用期間中に問題行為を把握できない場合に備えて、雇用契約を有期契約としておくことが考えられます。その上で、雇用契約書の更新の有無に関する欄において、『更新しない』と明確に記載するか、『更新する場合がある』という程度の記載に留めておくようにします。
問題社員の問題行為が雇用契約を維持できない程に深刻なもので、改善が見込まれない場合には、期間満了により雇用契約を終了させるように対応します。
最後に
たとえ問題社員と言えども、そう簡単に解雇することはできません。そのため、日頃から改善に向けた面談や教育指導を行うなど適切な指導を行うことが非常に重要です。
問題社員の指導でお困りの場合には弁護士にご相談ください。当法律事務所の概要はトップページにてご覧ください。当事務所では無料法律相談も行っております。