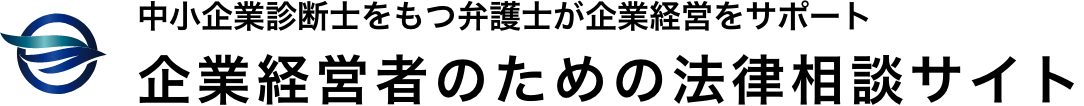解雇には、懲戒解雇、普通解雇、整理解雇といった種類があります。労働契約を一方的に解消させる場合には、解雇の他にも、有期契約の雇止め、試用期間満了による本採用拒否、内定取消しなども広く含まれ、多くの法律上の論点を含んでいます。
今回は、これら解雇をはじめとした労働契約解消に関する要件について解説します。

解雇とは
解雇とは、企業が労働者に対して、雇用契約を一方的に解消する処分を言います。
解雇には、一般的には懲戒解雇、普通解雇、整理解雇があります。
懲戒解雇とは、就業規則で規定されている懲戒事由、例えば、ハラスメントをする、備品を横領する、機密情報を漏えいさせる等の企業秩序に反する重大な非違行為を従業員が行ったことを理由に、その制裁として雇用契約を解除するものです。
普通解雇とは、能力不足、協調性不足、勤怠不良、私傷病で働けないなど、従業員が労務を提供する義務を果たさないことを理由に雇用契約を解除するものです。
整理解雇とは、事業不振等による人件費削減のために行われる解雇処分です。整理解雇の場合、そのほかの解雇と異なり、従業員に問題行為等の帰責事由があることを要件としていません。
懲戒解雇
懲戒解雇の要件
懲戒解雇が認められる要件について解説します。
懲戒解雇は、雇用契約を一方的に解消させる処分であり、従業員としての地位を奪う重大な処分です。その上、懲戒解雇の場合、退職金の全部又は一部が不支給とされたり、退職後の転職活動に重大な支障を及ぼすなど、従業員に対して様々な不利益を及ぼします。
そのため、懲戒解雇が有効となるためには、懲戒解雇を選択せざるを得ない程の合理的な理由があり、これを許容する社会的相当性が認められることが必要です。
具体的には、
①懲戒解雇事由に該当すること
②社会的相当性
③解雇手続の履行
を充足させることが必要です。
①懲戒解雇事由の該当性
まず、懲戒解雇をはじめとした懲戒処分を課すためには、懲戒事由が就業規則に具体的に規定されていることが必要となります。
その上で、問題社員の行為が、懲戒解雇事由に該当することを要します。
形式的に懲戒解雇事由に該当するだけでは十分ではありません。
懲戒解雇が企業秩序を維持するために、従業員としての立場を奪う重大な処分ですから、懲戒解雇とせざるを得ない程に重大な非違行為であることが必要です。
②社会的相当性
仮に従業員の行為が懲戒解雇事由にあてはまるとしても、直ちに懲戒解雇が有効となるわけではありません。
懲戒解雇が重大な処分であることから、
- 対象となった行為の内容、態様、
- 行為によって生じた結果、
- 過去の処分歴、
- 行為前の指導や注意の有無、
- 調査手続に対する協力状況、
- 反省の有無
などの事情を考慮して、懲戒解雇とすることがやむを得ないと言えることが必要です。
③解雇手続の履行
就業規則や労働協約において、労働組合との協議や懲戒委員会を開催することを解雇の要件として規定している場合には、これら手続を履行しなければなりません。
また、これら手続が規定されていなかっとしても、懲戒解雇が懲戒処分の中で最も重い処分ですから、事前に従業員本人に対して弁明の機会を与えることが必要です。
累計別解雇事由
解雇事由のうち一部を以下のとおり取り上げます。
経歴詐称
経歴詐称とは、学歴、職歴、犯罪歴を偽った場合をいいます。
ただ、あらゆる経歴詐称が懲戒解雇の対象となるわけではありません。
経歴詐称が雇入時に発覚していれば、企業がその労働者を雇用しなかった、あるいは、同一条件で雇用しなかったといえ、客観的にそのように認められる場合には、重大な経歴詐称として懲戒解雇事由に該当し得ます。
例えば、高卒であるのに大卒と偽って高い初任給を得ていたり、職歴を偽り、その職歴に応じた高額な給与を得ているような場合です。
業務命令違反
従業員が、業務命令を拒否する場合に、当該従業員を懲戒解雇することができるのでしょうか?
業務命令違反を理由に懲戒解雇するためには、その前提となる業務命令それ自体が適法であることが必要です。
業務命令には、日常業務や時間外労働に関する業務命令から人事権に基づく業務命令まで含みます。
業務命令違反による解雇をする場合には、業務命令の内容に応じた対応が必要となります。
日常業務等の業務命令
まず、日常業務等の業務命令について、労働者は労働誠実義務を負っていますので、この業務命令に従う必要があります。
ただ、日常業務に関する業務命令違反に対して、懲戒解雇を課すことは重すぎる処分となり無効なる可能性が高いです。
そのため、厳重注意や戒告といった軽い懲戒処分などを通じて改善の機会を与えます。
それでもなお、業務命令に従わない場合には、退職勧奨を行った上で懲戒解雇を行うことになるでしょう。
人事権に基づく業務命令
人事権に基づく業務命令とは、従業員に対して職種変更や転勤等の配置転換を求める業務命令です。
会社には、従業員の雇用を確保させるために、広範囲の人事権が与えられていますので、人事権に基づく業務命令は広く認められています。
そのため、業務命令が権利濫用と認められない限り、その業務命令は適法と判断されることが多いです。
ただ、業務命令違反があったことのみを理由にすぐに懲戒解雇とすることは早計です。
懲戒解雇は非常に重たい処分ですから、慎重な手続が必要です。
具体的には、業務命令の必要性を丁寧に伝えた上で、業務命令を拒否する理由を聴き取り、業務命令に従うように説得します。
それでもなお、応じない場合には懲戒解雇を選択せざるを得ないでしょう。
私生活上の非行
職場や業務とは無関係に、労働者が逮捕勾留されたり、刑事罰を受けたなどの私生活上の非行を理由として、懲戒解雇を課すことが認められるのでしょうか?
そもそも懲戒権は、企業内秩序を維持するために使用者に認められた権限です。
そのため、私生活上の行為は、あくまでも業務外の行為であって、企業内秩序に影響を及ぼすことはありませんので、原則として懲戒の対象とすることはできません。
しかし、企業の事業活動に直接関連する場合や会社の社会的評価を毀損するような場合には、懲戒解雇の対象となり得ます。
例えば、バスやタクシー会社の乗務員が飲酒運転をした場合や鉄道会社に勤める者が電車内で痴漢行為に及んだような場合には、懲戒解雇が有効とされる傾向があります。
なお、問題社員の適切な対応については、こちらのコラムを参照ください。
普通解雇について
普通解雇の要件
労働契約法16条には、『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』と規定されています。
つまり、普通解雇においても、①客観的に合理的な理由が認められていること、②解雇処分とすることが社会通念上相当といえることが必要となります。さらに、これらに加えて③手続的要件を満たしていることも必要となります。
①客観的に合理的な理由があること
普通解雇は、雇用契約上求められた労務の提供をしないこと(債務不履行)を理由とした解雇です。そのため、解雇理由として、能力不足や協調性不足、勤怠不良といった債務不履行があることが必要です。
この債務不履行は、使用者の主観的に認められるだけでは十分ではありません。
客観的な証拠を持って債務不履行の事実を証明することが必要です。
その上で、これら債務不履行が就業規則の普通解雇事由に該当していることが必要です。
②社会通念上相当であること
普通解雇も雇用契約を終了させる処分ですから、債務不履行の内容等がこれに見合ったものと評価できることが必要です。
具体的には、
- 雇用契約上求められる労務提供の内容(新卒か中途採用か等)
- 債務不履行の内容や程度
- 教育指導の機会を与えたか
- 処分歴の有無やその程度
の事情を考慮して解雇処分とすることがやむを得ないといえるかを判断します。
③手続要件の履行
解雇処分の重大さから、解雇をする前に労働者に対して弁明の機会を与える必要があります。
弁明の機会を与えるにあたっては、従業員に対して会社が考えている解雇理由を具体的に説明します。
これに対して、従業員において、解雇理由となる事実関係が存在するのかを弁明し、これを裏付ける客観的資料がある場合にはその提出を促します。
さらに、従業員が非があることを認める場合には、反省の弁を述べる機会を与えます。
さらに、就業規則において解雇にあたって一定手続を必要とする旨規定されている場合には、これを履践します。
④解雇制限
上記の①から③までの要件を満たしたとしても、以下に該当する場合には解雇が制限されます。
労働基準法によるもの
労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
年次有給休暇を取得したことを理由とする解雇
労働組合法によるもの
労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇
労働者が労働組合の組合員であることや、組合に加入したり組合を結成しようとしたことなどを理由とする解雇
男女雇用機会均等法によるもの
労働者の性別を理由とする解雇女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
育児・介護休業法 によるもの
労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、または育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇
累計別解雇理由
能力不足を理由による解雇
新卒一括採用のゼネラリストの場合
能力不足というのは、雇用契約上求められている業務遂行能力がないことを意味しています。そのため、雇用契約の内容を踏まえ求められている具体的な能力を特定することが必要です。
新卒一括採用のゼネラリストの場合、入社後に社内教育や人事異動を通じて業務遂行能力を身につけていきますから、雇用契約締結時点において、特定の業務を遂行できる能力を有していることは通常契約内容に含まれていません。
そこで、新卒者をその能力不足を理由に解雇することは困難というべきです。
教育指導の機会を適切に与え、配置転換を行いながら、能力不足の解消に努めることが必要となります。
中途採用者の場合
中途採用者においても、一般事務のように、高度な専門的な能力を求められていない場合には、能力不足を理由に解雇することは困難です。
また、経験者として中途採用された場合でも、高度の専門的知識を有していることを期待された場合であれば別ですが、そこまでの能力を期待されていない中途採用者であれば、高度な専門的な能力を発揮することを契約内容としているわけではないため、期待された成績を残せなかったとしても直ちに解雇することはできず、配置転換や研修等の教育の機会を通じて改善を図るべきと考えます。
他方で、地位特定者の場合、能力不足を理由とした解雇が認められます。地位特定者とは、職位上の地位が特定され、その地位に応じた具体的な業務遂行能力等を有していることを期待されて、これに見合った待遇を約束され中途採用された者です。特定の地位に見合った能力を有していることが契約内容とされているため、異なる職位や職種への配置転換は予定されていません。そのため、特定の地位に見合った能力がない場合には、解雇をせざるを得ません。ただ、あらかじめ雇用契約書には、①特定の地位を明示した上で②具体的な職務内容を記載し、③求められる仕事の成果の数値や内容を具体的には明示しておかことで、成績不良か否かを客観的に判断できるようにすることが重要です。
無断欠勤遅刻を繰り返す場合
無断欠勤や遅刻を繰り返す場合に普通解雇とすることができるのか?という問題です。
労働基準法39条では、年間の出勤率が80%を超えている労働者には有給休暇を付与しています。これを踏まえ、たとえ欠勤を繰り返していたとしても出勤率が80%を超えているのであれば、欠勤等を解雇理由とすることは難しいことが多いでしょう。
また、欠勤日数が多かったとしても、その欠勤理由が非常に重要です。たとえ無断欠勤が多かったとしても、その原因が社内のハラスメントや就労環境の悪化である場合には、会社には従業員の就労環境を整備する義務を負いますから、欠勤を理由とした解雇は回避すべきです。他方で、欠勤理由が合理的ではなかったり虚偽の内容の場合には、普通解雇事由に該当するものと考えます。ただ、いきなり解雇処分とするのではなく、早い段階から注意指導や戒告などの懲戒処分を行い、改善の機会を与えることが必要です。
整理解雇とは
整理解雇が認められるためには、以下の4つの要素を満たすことが必要となります。
①人員削減の必要性
②解雇回避努力
③解雇対象者の合理的な選定
④労働組合や労働者との協議
これら4つの要素については、それぞれを分断するのではなく総合的に捉えて解雇が合理的で相当といえるかを判断します。そのため、人員削減の必要性が高度な場合には、これと相関関係にある解雇回避努力の程度はそこまで高度に求められません。
他方で、人員削減の必要性がそれ程高くなければ、その分解雇回避努力の要請は強く求められます。
この4つの要素の中で最も重要な要素は、解雇回避努力の要素です。解雇回避努力を尽くすことなく、いきなり解雇をすると解雇権の濫用と評価されます。
具体的には、解雇をする前に以下の解雇回避努力を行ったといえるのかを判断します。
- 広告費・交通費・交際費といった経費削減
- 時間外労働の制限や禁止
- 賞与カット・昇給停止・役員報酬の減額などの対応
- 転勤や出向などによる対応
- 休業手当を支給しながら一時休職させる
- 非正規社員の契約を解消させる
- 希望退職者の募集・退職金を上乗せした退職勧奨
- 不採算部門の切り離し、売却
- 不動産などの資産売却
解雇が無効とされる場合の問題
以上解説したように解雇処分が有効となるためのハードルは非常に高いです。
無計画に問題社員を解雇処分に付すと、事後的に労働者の方から不当解雇であると主張されることがあります。
不当解雇であると主張される場合に会社が強いられる負担を見ていきます。
バックペイ
解雇が無効となる場合、解雇後も引き続き雇用契約が存在していることになりますから、企業は解雇後の給与を支払わなければなりません。
その理由は以下のとおりです。
そもそも、労働者は、労働を提供することの対価として給与を得ますから、仕事をしなければ賃金を得ることはできません(ノーワーク・ノーペイの原則)。
民法536条2項本文では、『債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは,債務者は,反対給付を受ける権利を失わない。』と規定されています。
不当解雇の事案では、労働者は仕事をしようと思っても、会社が解雇処分を理由にこれを拒否します。つまり、従業員は債権者である会社の責任によって労働という債務の提供を果たすことができません。そのため、従業員は会社に対して賃金の支払いを求める権利を失いません。
解雇後の給与相当額は、労働者の就労の意思が認められる限り負担し続けなければならず、会社にとって大きな経済的負担となります。
解決金
解雇が無効である以上、従業員は雇用契約に基づく地位を有していることになります。
そうすると、会社は従業員を復職させなければなりません。
しかし、実際のところ、解雇処分を通じて労使間の関係は相当程度悪化していることが多く、復職させることが困難であることがほとんどです。
そこで、会社が従業員を復職させないために解決金を支払うことがあります。解決金の金額は、解雇の違法性の程度に応じて給与の1年分から1ヶ月分までの範囲内で決定されます。
時間外等割増賃金の請求
解雇処分を受けたことがきっかけとなり、これまでの残業代等の請求を受けることがあります。かつては、残業代等の消滅時効は2年とされていました。しかし、民法の改正により残業代等の消滅時効は5年となりました。当面の間は3年とされていますが、数年先には5年となります。これはすなわち、改正前と比べて、企業の負担は2.5倍増加することになります。
退職勧奨のすすめ
解雇を無計画に行うことで、予想しない経済的な負担が生じるおそれがあります。
さらに、会社の社会的信用を毀損するリスクもあります。
会社としてはこのようなリスクを回避する必要がある一方で、問題行為を繰り返し行う問題社員に対して適切な対応をする必要もあります。
そこで、問題社員に対する適切な対応として、解雇ではなく退職勧奨を行うようにします。
退職勧奨とは、従業員に対して自主退職をするように促す行為です。
退職勧奨において、行き過ぎた言動がなされると退職勧奨ではなく退職強要となってしまいますので、言動やその実施方法には注意が必要です。
具体的には、退職勧奨の実施方法としては、これまでの問題行為を取り上げた上で、何度も注意・指導を行い雇用継続のための努力を重ねてきたものの改善されなかったという、これまでの経緯を率直に伝えた上で自主退職するように促します。この際には、解雇やクビというワードはNGワードです。
あくまでも従業員の自由意志による退職を促すものですので注意してください。従業員が退職勧奨に対して躊躇することも予想されるため、解決金の支払いや退職金の上乗せなどのパッケージを用意しておくことも必要となります。
有期契約の雇い止め

雇用期間を定めた労働契約(有期契約)を雇用期間の満了を理由に終了させることを雇い止めと呼びます。
雇い止めによる契約終了は原則として違法ではありません。
ただし、有期雇用が、実質的に無期雇用と評価できるような場合や、契約更新を期待することが合理的であるような場合には、例外的に雇い止めが違法と判断されることがあります。
雇止めの違法性を判断するにあたっては、
- 雇用の臨時的か常用的か
- 更新回数
- 雇用期間の通算期間
- 更新手続の実施状況(形式的か厳格か?)
- 雇用継続の期待を抱く言動
- 契約内容
などの諸事情を考慮して決します。
雇い止めの有効性判断は、以下の契約類型に分類して考えると分かりやすいです。
- 純粋有期契約タイプ
- 実質無期契約タイプ
- 期待保護(反復更新)タイプ
- 期待保護(継続特約)タイプ
純粋有期契約タイプ
このタイプは、契約期間の満了後に契約が更新されることを期待することが合理的ではない契約類型です。
例えば、
①業務内容や契約上の地位が臨時的なもので継続することが予定されていない場合
②期間満了により契約が終了することを当事者間で明確に認識している場合
③更新手続が、曖昧ではなく厳格に実施されている場合
④過去に同程度の立場にある従業員を雇い止めにしている場合
です。
特に、②が重要です。
雇用契約書には、更新の有無を明確に記載して、更新する場合の判断基準を明記します。仮に更新を予定していない場合には、雇用契約書には、更新しないとはっきり記載します。このような明確な記載がなければ、契約更新に対する合理的な期待が生まれる可能性もありますので注意が必要です。
実質無期タイプ
実質無期タイプの場合、雇い止めは制限され、ほとんどの事案で雇い止めが認められていない傾向です。
実質無期タイプとは、実質上雇用期間の定めのない契約と変わらない有期契約をいいます。
具体的には、
業務内容が正社員のものと変わらない場合
更新手続が極めてルーズでほとんど行われていない
更新回数が数回ではなく非常に多い、あるいは、通算期間が非常に長期である場合
同様の地位にある労働者が過去に雇い止めをされた先例がない場合
には、実質無期タイプに分類されます。
この事案においては、雇い止めが有効とされるためには、解雇の有効性の判断に類似した合理的な理由と相当性があることを求められ、非常にハードルが高くなっています。
期待保護(反復更新)タイプ
実質的に無期契約とまでは言えないものの、契約期間の満了により契約が終了せずに更新されるだろうと期待することが合理的な場合です。
実質無期タイプとは異なり、更新手続が厳格に行われているものの、更新回数が多かったり、契約期間の通算期間が長期の場合には、これにあたります。
このタイプの場合には、解雇濫用の考え方が妥当しますが、実質無期タイプよりも緩やかな基準により雇止めが認められる傾向です。
ただし、更新回数が複数あったとしても雇用の通算期間が1年に満たない場合には、解雇権濫用の考え方は妥当しにくいと考えます。
また、たとえ更新回数が複数あり、通算期間が1年を超えていたとしても、雇用契約書に更新回数や契約期間の上限が明確に定められているような場合には、その上限を超える更新を拒絶することは許容されると考えます。
期待保護(継続特約)タイプ
更新回数は少なく、雇用の通算期間も短いものの、雇用契約の締結時において、契約更新に関する特約を結んでいる場合です。
この場合においても、解雇権濫用の考え方は妥当しますが、契約内容の特殊事情を考慮しながら雇い止めに合理的な理由があるのかを判断します。
試用期間満了による本採用拒否
試用期間とは
試用期間とは、本採用の前に行われる正社員としての適格を有しているかを判断するための雇用期間を言います。試用期間を設ける場合、雇用契約書や就業規則に試用期間の定めを設けます。
使用期間は通常3か月とすることが多いですが1ヶ月や半年としているケースもあります。また、試用期間中の状況をみて、試用期間を延長することもあります。
試用期間の法的性質
試用期間の法的性質について、解約権留保付の雇用契約であると考えられています(三菱樹脂事件・最高裁昭和48年12月12日)。
分かりにくいので、具体的に説明します。
採用決定当初、企業は、対象となる従業員が、従業員としての資質、性格、能力といった適格を有しているかの判断するための資料・情報を十分に持ち合わせていないことが多いです。
そのような状況でいきなり本採用をしてしまうと、十分な資質や能力を持たない従業員を採用してしまい、様々な労務トラブルに招いてしまいます。
そこで、試用期間を通じて適格性に関する情報や資料を十分に収集し、その結果、従業員としての適格性がないと判断できれば最終的な採用を拒否します。
このような理由から、試用期間は解約権を留保した契約と解されています。
本採用拒否が認められる場合
先程述べました試用期間は、従業員の適正を判断するための観察期間であり、試用期間の目的を果たすために解約権が留保されていますので、正社員の解雇等の場合よりも、会社には契約解消に関する裁量は広く与えられています。
ただ、本採用の拒否は全くの自由というわけではありません。
つまり、面接時に把握できなかったものの、試用期間の仕事ぶりを通じて、勤務態度、能力、出勤状況等の情報を知るに至り、引き続き雇用をすることが不適格と判断できる場合には、解約権を行使して本採用を拒否さることができるということです。
内定取消し
内定通知後、就労を開始するまでの間に、この内定を取消すことが法的に認められるのでしょうか。
内定とは
企業が採用面接の結果、被採用者に対して内定通知をすることによって雇用契約が成立すると考えられています。なぜなら、企業による従業員の募集は雇用契約の申し込みの誘引とされ、これを受けた応募は、雇用契約の申込みと解されています。そして、企業による内定通知は、応募に対する承諾と解されるため、この時点で雇用契約の申込みと承諾が合致したといえるからです。
雇用契約が成立したとしても、これは始期付解約権留保付労働契約と解されています。
始期付解約権留保付というのは、就労が開始する時期まで、契約を解約することができる権利が企業に対して与えられているという意味です。
ただ、形式的に内定通知が発せられた外観があれば常に雇用契約が成立するわけではありません。少なくとも内定通知を受けたことで、他社に就労する機会を放棄したといえることを要します。
内定取消しの適法性
内定取消しも無制約ではありません。
解約権留保の趣旨や目的に照らし、客観的に合理的と認められ社会通念上相当と認められることを要します。
具体的には、
- 提出書類に虚偽記載がある
- 大学を卒業できない
- 身体や精神の故障により就労開始日からの就労開始ができない
- 従業員としての適格性や会社の社会的信用を毀損するような行為があった場合
- 企業の経営悪化
などの理由による内定取消しが考えられます。
内定の取消しがなされる場合を明確にしておくためにも、誓約書や入社承諾書などに取消事由を列記しておきます。
ただ、取消事由に該当したとしても、採用内定通知の時点で、企業が既に知っていた、あるいは、知ることができたような場合には、その事情を理由に内定取り消しをすると違法と判断されることがあります。
さらに、企業の経営悪化による内定取消の場合、整理解雇と枠組みに準じた考察が必要となります。
最後に
解雇をはじめとした労働契約の解消には、様々な問題をはらんでいます。安易に解雇処分や契約の解消を行うと、思ってもないような負担を強いられることもあります。
解雇等の対応をする際には、まず弁護士にご相談するなどして慎重に進めていきましょう。
当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。
お気軽にご相談下さい。