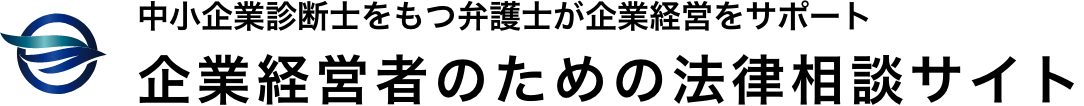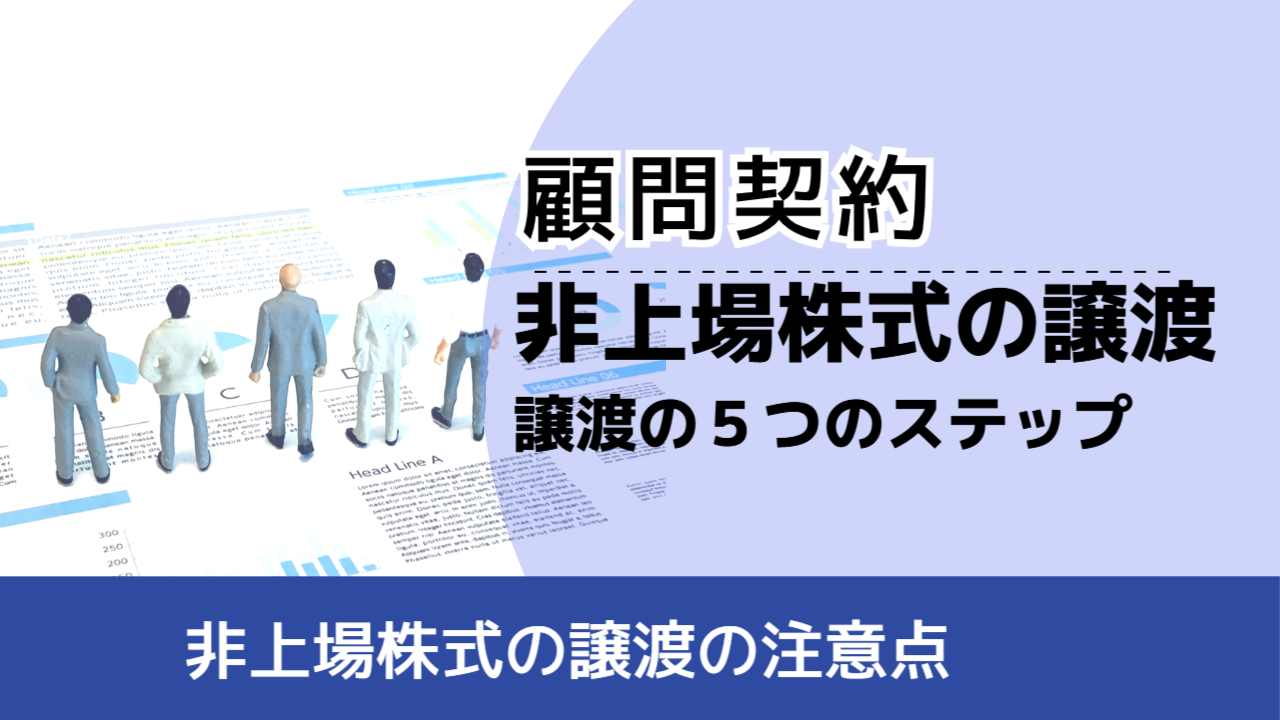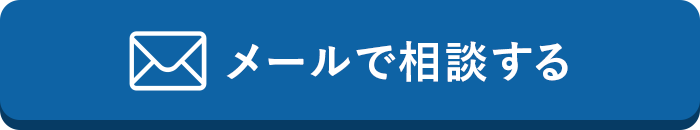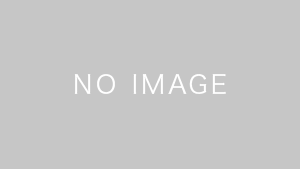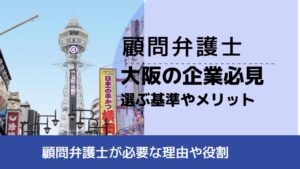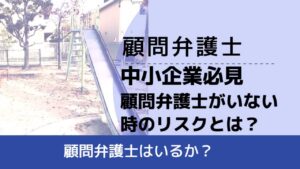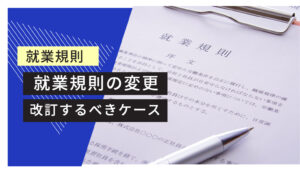非上場株式の譲渡は、上場株式と異なり、特有の手続きや税金の知識が求められます。
「譲渡したいけれど、何から始めたら良いかわからない」という方も少なくないのではないでしょうか。
本記事では、非上場株式の譲渡方法について、手続きの流れから税金、注意点までを詳しく解説します。この記事を読めば、非上場株式の譲渡に関する疑問が解消されるでしょう。
非上場株式とは?上場株式との2つの大きな違い
株式には、大きく分けて「上場株式」と「非上場株式」の2種類が存在します。上場株式とは、東京証券取引所などの金融商品取引所に上場されており、不特定多数の投資家が市場を通じて自由に売買できる株式を指します。一方、非上場株式は、証券取引所を介さずに譲渡されるため、市場価格が存在しないのが特徴です。そのため、その評価は特定の目的や状況に応じて個別に行われます。
以下の項目では、非上場株式と上場株式の違いについて具体的に見ていきましょう。
違い①:市場での売買ができない
上場株式は、東京証券取引所のような公開市場を通じて、誰もが証券会社を介して自由に売買できます。これにより、不特定多数の投資家が参加し、価格は市場の需給によって形成されます。一方、非上場株式にはこのような公開市場が存在しないため、証券会社を介して手軽に売買することはできません。そのため、希望するタイミングや価格で売却するのが難しい場合があります。
非上場株式を売買する際は、売り手と買い手が直接交渉して取引を行う「相対取引」が基本です。相対取引とは、金融商品取引業者(証券会社など)を介さずに、当事者同士が直接株式を譲渡する手法を指します。買い手と売り手を自ら探し、譲渡価格や諸条件を交渉して合意に至るプロセスが求められます。
このように、取引市場の有無は、株式の売買のしやすさ、すなわち「流動性」において、上場株式と非上場株式の最も大きな違いと言えます。
違い②:多くの株に「譲渡制限」が設けられている
非上場株式の大きな特徴の一つは、その多くに「譲渡制限」が設けられている点です。譲渡制限株式とは、会社法に基づき、定款で株式の譲渡に会社の承認を要すると定められた株式を指します。
すなわち、株主が自身の意思で株式を第三者に自由に売却・譲渡することはできず、必ず会社の承認を得る必要があります。非上場企業の多くは、その発行するすべての株式に譲渡制限を設けているのが一般的です。全株式に譲渡制限が付されている会社を非公開会社といいます。非上場会社=非公開会社ではないため注意しましょう。
このように、非上場株式では譲渡制限が付されていることが一般的であるため、譲渡手続きが上場株式よりも煩雑になります。

非上場株式を譲渡するメリット・デメリット
非上場株式の譲渡は、これまで投資してきた資金を回収し、まとまった譲渡益を得る機会となり得ます。しかし、その一方で、非上場株式の譲渡には、その特有の難しさやリスクも伴います。
そこで、以下の項目では非上場株式の譲渡をするメリットとデメリットの両方ついて詳しく解説していきます。
【メリット】投資資金を回収し、まとまった利益を得られる
非上場株式を譲渡する最大のメリットは、キャピタルゲインを取得することができる点にあります。
株式を譲渡やその他の方法で処分することを「イグジット」と呼びます。会社の成長のために投資を行い、株式の価値をスタートアップ時よりも上昇させることで、売却によってまとまった利益(キャピタルゲイン)を獲得することができます。このキャピタルゲインは、創業者や投資家にとって、これまでの努力が資金という形で報われる瞬間となります。
【デメリット】希望の価格やタイミングで売却できるとは限らない
非上場株式には市場が存在しないため、上場株式のようにリアルタイムで適正な株価が形成されることはありません。したがって、売却価格は売り手と買い手との相対交渉によって決定されます。非上場株式の特性上、希望する価格での売却が難しい場合がある点がデメリットの一つです。
特に、非上場企業の株式は買い手が見つかりにくい傾向にあり、譲渡先が限定されるケースも珍しくありません。その結果、交渉が難航したり、売り手が期待する価格よりも低い金額での売却を余儀なくされたりする可能性も考えられます。
また、売却したいタイミングで、すぐに買い手が見つかるとは限りません。買い手を見つける活動には数年単位の時間を要することもあす。これらの要因から、非上場株式の譲渡には、希望の条件でスムーズに進まないリスクが常にあると言えます。
【デメリット】手続きが複雑で専門知識が必要になる
上場株式が証券会社を通じて手軽に売買できる一方、非上場株式の譲渡には、会社法に基づく複雑な手続きが必要です。当事者間での相対取引が基本となるため、売り手と買い手自身が多くの法的な手続を経る必要があります。
具体的には、まず会社の定款を確認し、譲渡制限の有無を調べることから始まります。その後も、煩雑な書類作成や法的な手順が複数存在します。非上場株式の譲渡における主な法的手続きは以下の通りです。
- 会社の定款を確認し、株式譲渡制限の有無を調べる
- 譲渡承認請求
- 株主総会又は取締役会の承認決議
- 株式譲渡契約書の作成と締結
- 株主名簿の名義書換請求
さらに、適正な株価の算定は会社の事業規模や収益によって異なり、専門的な評価方法の理解が不可欠です。譲渡益が発生した場合の所得税等の税金の計算と申告も、非常に専門的な知識を要します。これらの法的な面だけでなく、会計や税務に関する専門知識も不可欠となります。専門知識がないまま手続きを進めると、後々トラブルに発展したり、予期せぬ税金が発生したりするリスクが高まります。そのため、正確な知識と慎重な対応が求められます。
【5ステップで解説】非上場株式の譲渡手続きの全手順
非上場株式の譲渡は、上場株式のように公開市場で自由に売買できるものではなく、会社法に定められた特別な手続きを経る必要があります。
以下では、非上場株式の譲渡に必要となる手続き全体の流れを把握しやすいよう、主要なステップを5つに分けて解説します。
ステップ1:会社の定款を確認し、「譲渡制限」の有無を調べる
非上場株式の譲渡手続きを進める際は、まず会社の定款(ていかん)を確認する必要があります。
定款とは、会社の組織や活動に関する根本的な規則を定めた書類であり、株式の譲渡に関する規定も記載されています。非上場株式であったとしても必ずしも譲渡制限株式とは限らないため、保有株式が譲渡制限株式であるか否かを把握するため、定款の規定を確認します。
定款が手元にない場合でも、会社法に基づき、株主は会社に対し定款の閲覧や謄写(コピー)を請求することができますので、閲覧謄写を求めて、定款の内容を確認しましょう。
ステップ2:譲渡先(買い手)を探し、株価を交渉する
非上場株式は、上場株式のような公開市場が存在しないため、ご自身で譲渡先(買い手)を探す必要があります。譲渡先の主な候補は以下の通りです。
- 会社の経営陣
- 他の株主
- 親族
- 取引先
- M&A仲介会社を介して買取希望者を探索する
買い手候補が見つかったら、次の段階は株価の交渉です。非上場株式には市場価格がないため、決まった価格が存在するわけではありません。売買価格は、売り手と買い手の当事者間の合意によって決定されるのが原則です。
交渉を円滑に進め、お互いが納得できる価格を見出すためには、客観的な根拠に基づいた株価の算定が不可欠となります。株価の算定根拠として決算書が挙げられます。決算書の情報等を基に、インカムアプローチ、コストアプローチ、マーケットアプローチといった各手法により株価を算出します。これを参照しながら価格交渉を行うのが通常です。
また、株式の評価額だけでなく、譲渡の時期や支払い条件など、他の諸条件についても合意形成が必要です。双方が全ての条件に合意に至った後、次のステップである「株式譲渡承認請求」に進みます。
ステップ3:会社に対して「株式譲渡承認請求」を行う
非上場株式の多くは「譲渡制限株式」であるため、第三者に譲渡する際には、会社法に基づき会社からの承認が不可欠です。この承認を得るための正式な手続きが「株式譲渡承認請求」です。この請求は、株式を譲渡したい株主、または譲受人が会社(通常は代表取締役)に対して行います。
株主は会社に対し、①譲渡しようとする株式の種類・数、②譲渡の相手方の氏名又は名称、③譲渡承認を拒否された場合に会社又は指定買取人による買い取りを求めるときはその旨を明らかにして、譲渡承認請求を行います。会社の事前承認を得ることなく第三者に譲渡された場合には、株式取得者が譲渡承認請求を行うことができます(会社137条1項、138条2号)。
請求を受けた会社は、取締役会設置会社であれば取締役会、そうでなければ株主総会の決議により、譲渡を承認するか否かを決定します。会社法第145条では、会社が原則として請求から2週間以内に、その決定内容を請求者へ通知する義務があると定めています。この期間内に通知を怠ると、譲渡が承認されたものとみなされる「みなし承認」となるため、会社側も迅速な対応が求められます。
ステップ4:会社から承認を得て「株式譲渡契約」を締結する
会社から株式譲渡の承認が得られたら、次の段階として、譲渡人(売り手)と譲受人(買い手)の間で、正式な「株式譲渡契約」を締結します。これは、会社株式の売主から買主への譲渡内容を定める重要な契約書であり、口頭での合意ではなく、書面で確実に作成することが不可欠です。契約内容を書面化することで、後々の認識の齟齬やトラブルを未然に防ぎ、円滑な取引を担保することができます。
株式譲渡契約書には、通常、以下のような主要項目を具体的に記載します。
- 株式の譲渡:譲渡する株式の種類と数を明記します。
- 譲渡代金:株式の売買価格を明記します。
- 支払期限や支払方法:代金の支払方法や支払期日を明記します。
- 株券発行会社であれば株券の引き渡しをすることを明記します。
- 譲渡承認:会社の譲渡承認を得ることを条件とする
- 表明保証:譲渡対象株式を適法かつ有効に保有し株主名簿上の株主名簿であることを表明します
- 名義書換え:株主名簿の書換えに必要な手続きに協力することを約束する
- 契約解除条項:契約解除の条件や損害賠償に関する規定
これらの項目を盛り込み、双方が合意した上で契約を締結します。契約締結後、合意内容に基づいて譲渡代金の決済が行われ、株券発行会社の場合は株券の引き渡しが完了します。株券不発行会社であれば、株券の引き渡しは不要です。また、契約書に譲渡承認決議の議事録を添付する場合もあります。
ステップ5:株主名簿の名義書換を請求する
株式譲渡契約の締結後、非上場株式の譲渡手続きにおいて、最後の重要なステップとなるのが「株主名簿の名義書換」です。これは、株式を取得した買い手が、自身が会社の正式な株主であることを法的に認めてもらうための手続きです。
この名義書換を行わないと、会社法130条1項の規定に基づき、新しい株主(買い手)は、会社に対して株主であることを主張できません。そのため、株主総会での議決権行使や配当金の受領といった株主としての権利を、会社や第三者に対して主張できないという問題が生じます。そのため、株式を取得したら速やかに名義書換の請求を行うことが非常に重要です。
原則として、この名義書換請求は、株式を譲渡した売り手(旧株主)と、株式を取得した買い手(新株主)が共同で会社に対して行う必要があります(会社法133条1項、2項)。
この株主名簿の名義書換をもって、非上場株式の譲渡に関する一連の法的手続きがすべて完了します。
非上場株式の株価はいくら?主な3つの算定方法
非上場株式の公正な取引を行うためには、客観的な根拠に基づいた株価算定が不可欠です。評価額が実際の取引時価と大きく乖離しないよう、専門的な視点での評価が求められます。以下では、非上場株式の価格を計算する
インカムアプローチ(DCF方式)
インカムアプローチとは、将来予測される利益やキャッシュフローを着目して株価を評価する手法です。つまり、企業活動を通じて得られる収益の見込みを踏まえて株価を導く手法といえます。
インカムアプローチの中でもDCF方式が主要な手法の一つといえます。
DCF(Discounted Cash Flow)法とは、将来生み出すと予想されるフリーキャッシュフローの金額を算出した上で、それを加重平均資本コストで割り引くことで企業の現在価値を計算する方法です。
DCFは、企業の将来の収益力を反映させる方法であり、事業を継続させる企業の株式評価に適した手法といえます。裁判例においても、継続企業における株価評価では、DCF法による手法が重視される傾向にあります。
DCF法で重要な要素であるFCF(フリー・キャッシュフロー)とは、営業キャッシュフローから投資キャッシュフロー(設備投資等の支出額)を控除した後の残額をいいます。このフリーキャッシュフローは、中期事業計画による予測損益計算書や予測貸借対照表等の資料に基づく合理的な予測により算出します。事業計画を策定しない場合でも過去の財務データを踏まえて将来キャッシュフローを算出することもあります。ただし、あくまでも過去のデータによる将来予測となり、会社側の意向や恣意が介在する余地があるため、対立のポイントになることも多くあります。
コストアプローチ(純資産方式)
コストアプローチとは、会社の純資産額を根拠に株価を算定する手法です。コストアプローチには①簿価純資産方式と②時価純資産方式があります。
①簿価純資産方式とは、貸借対照表の純資産額に発行済株式数で除した金額をそのまま株式の現在価値とする方法です。会社の資産の含み益や含み損がある場合には、簿価の純資産額では実在の株価を反映しないものになるという不都合があります。他方で、時価評価をする作業を要しないため、計算過程が簡明で明確であるという点で優れているといえます。
他方で、②時価純資産方式は,貸借対照表上の資産・負債を時価に引き直した上で、1株当たりの純資産額を計算する方法です。不動産や有価証券などの資産や負債を時価評価することで、より実態に沿った純資産額を計算することが可能になります。ただ、時価評価の計算方法や計算結果が複雑となったり、その内容が恣意的ではないかとの疑念を抱かれることもあり、相手方の対立を招くこともあります。
マーケットアプローチ
マーケット・アプローチとは、市場で取り引きされている株式の価値を参考にして株価を評価する手法です。その株式の売買事例が多くある場合には、その株価を基準に計算することもできます。しかし、ほとんどの非上場株式は、取引事例が少ないことがほとんどですので、類似業種の株式の取引事例を参照して株価評価することになります。
マーケットアプローチには、市場株価法、類似上場会社法、取引事例法がありますが、このうち類似上場会社法がスタンダードな計算法になります。
類似上場会社法とは、対象企業に類似する上場会社の株価を選定した上で、その上場会社の株価等を基に評価倍率を算定し、対象会社の対応する財務数値にその評価倍率を掛けることで対象会社の株価を算定する方法です。類似上場会社は1社だけでなく複数社選定されることが一般的です。
非上場株式譲渡の3つの注意点
非上場株式の譲渡は、これまで解説したような複雑な手続きを要するだけでなく、思わぬトラブルや金銭的な損失につながるリスクをはらんでいます。
非上場株式の譲渡におけるリスクを未然に防ぎ、円滑かつ確実に譲渡を成功させるためには、以下で説明する3つの注意点を事前にしっかりと把握しておくことが不可欠です。
注意点1:低額・無償で譲渡すると課税される
非上場株式を時価の2分の1未満の価額で譲渡すると、売主と買主の税負担が大きくなることがあります。例えば、個人間の低額譲渡の場合、時価と譲渡価額の差額がみなし贈与となり、買主には贈与税が課税されます。贈与税は連帯納付義務とされているため、買主が贈与税を支払わない場合には、売主がその贈与税を納付しなければなりません。また、売主が個人で買主が法人である場合の低額譲渡であれば、時価と譲渡価額の差額がみなし譲渡となり所得税が課税されます。一方、買主の法人にも、時価と譲渡価額の差額が受贈益として法人税が課税されます。
このようき「低額譲渡」と判断された場合、予期せぬ贈与税や所得税が発生する可能性があるため、注意が必要です。
注意点2:会社から譲渡の承認が得られない場合の対処法
会社が譲渡承認を拒否する場合には、指定買取人をするか(会社140条4項)、会社自身が対象株式を買い取る必要があります(会社140条1項)。
会社が買い取る場合には、株主総会の特別決議で対象株式を会社が買い取る旨、買い取る対象株式の種類・数を決定した上で(会社140条1項・2項、309条2項1号)、その内容を、譲渡承認を拒否する通知(会社法139条2項)の日から40日以内に通知しなければなりません(会社141条1項、145条2号)。
その際には、一株当たりの純資産額に対象株式数を乗じて得た額を本店所在地の供託所に供託し、供託を証する書面を併せて交付する必要もあります(会社141条2項)。
買い取り価格は、まず株主と会社または指定買取人との間で協議により決定されます。もし協議が成立しない場合は、買い取り通知があった日から20日以内に、株式売買価格決定の申立てを行う必要があり、その期間内に申立てをしない場合には、供託した金額が売買価格となるため注意が必要です。
注意点3:買い手が見つからないケースも想定しておく
非上場株式は、上場株式のような公開された取引市場が存在しないため、希望するタイミングや価格で買い手が見つからないというリスクを伴います。多くの場合、「売りたくても売れない」状況に陥る可能性があり、結果として譲渡が成立せず、資産を現金化できない事態も想定されます。
このような事態にある場合には、会社に対して自己株式の取得を打診したり、既存株主に買取りを打診するなどして、売却手続を進められるように努めましょう。
| 対策 | 内容・効果 |
| 自己株式の取得を打診する | 会社自身に自社の株式を買い取ってもらうことで、株主は株式を現金化できます。 |
| 既存株主への譲渡 | 他の既存株主に対し、株式の譲渡を持ちかける手段です。 |
| 専門機関への相談 | M&A仲介会社などの専門機関に相談し、ネットワークを活かして買い手を探し、譲渡実現をサポートしてもらいます。 |
非上場株式の譲渡は難波みなみ法律事務所へ
本記事では、非上場株式の譲渡について、その特徴や上場株式との違い、具体的な手続きのステップ、適正な株価算定方法や注意点まで網羅的に解説しました。
非上場株式の譲渡は、多岐にわたる専門知識と複雑な手続きが求められます。そのため、独断で進めると、思わぬトラブルや税務上のリスクにつながる可能性があります。特に、適正価格から著しく乖離した取引は追加課税の対象となったり、会社から譲渡承認が得られなかったり、また、買い手が見つからなかったりといったリスクも想定されます。
手続きや価格交渉に不安がある場合や、スムーズかつ有利に譲渡を進めたいとお考えであれば、専門家である弁護士への相談が賢明な選択と言えるでしょう。