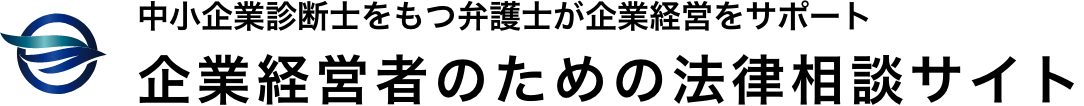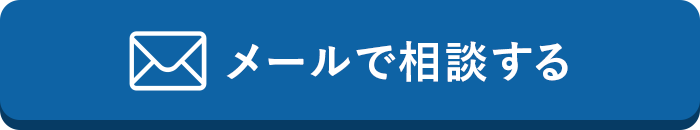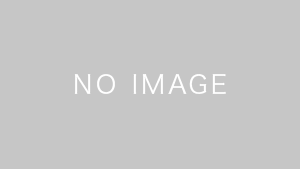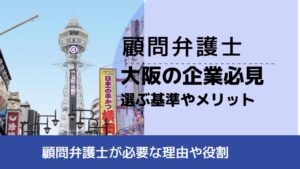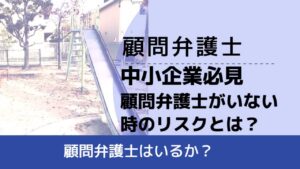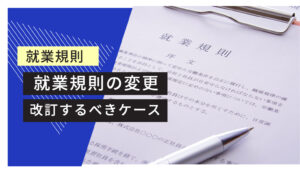2006年の会社法施行後は株券不発行会社がスタンダードとなり、商法改正で最初に株券不発行が原則化される前から営業する会社も、不発行への移行が進んでいます。
株券不発行のメリットは、株券の発行や保管、そして株主の管理などに必要なコストを削減できる点です。同時に、株券の代わりに発行株式の管理手段となる「株主名簿」の取扱いや、株主への説明が課題となります。
ここでは、株券不発行制度の基本とともに、株券発行会社から株券不発行会社への移行方法を解説します。移行に伴う法務担当者向けの注意点も、下記で押さえることができます。
株券不発行制度の基本
株券不発行制度とは、株式会社において株券を発行しないことを原則とする制度です(会社法第214条)
2004年より前の商法では、すべての株式会社において株券発行が義務とされていましたが、実務上の問題点を受けて株券不発行が原則となり、2006年の会社法施行時にも不発行の原則は引き継がれました。
以下では、株券不発行制度の背景をさらに深く掘り下げ、株券を発行する場合との具体的な違いを比較して解説していきます。
株券不発行会社が原則化された背景
株券の発行は、上場企業のように株式取引が頻繁に行われる会社なら必須ですが、株式の移動がほとんどない非公開会社ではメリットが少ないといわざるを得ません。加えて、株券の発行には以下の負担やリスクが伴い、多くの企業にとって課題となっていました。
- 株券の印刷費用
- 保管場所の確保
- 紛失、盗難、偽造のリスク
- これらに伴う事務処理の煩雑さ
こうした実情を踏まえ、より効率的で現代のビジネス環境に適した企業運営を可能にすることを目指して、まずは商法改正で株券ペーパーレス化から実現しようとしたのが、現在の株券不発行制度の始まりです。
現在の株券不発行制度は、企業側の負担軽減だけでなく、株式の流通や管理の簡素化にも寄与するもので、会社法の大きな転換点のひとつと言えるでしょう。
株券とは?株券と株式の関係を理解する
株券とは、株式会社に出資した株主であること物理的に証明する手段です。物理的な株券を占有することで、反証が出ない限り株主の地位にあるものと認められます。商法改正・会社法施行より前は長らく発行され続けたもので、現在の会社法では株券の記載事項について次のように定めます(第216条)
| ・株券発行会社の商号 ・当該株券に係る株式の数 ・譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨 ・種類株式発行会社は、当該株券に係る株式の種類とその内容 |
一方、株式とは、株主の地位および権利そのものです。
株主が議決権や配当金を得るための根拠であるとも言い換えられます。
つまり、株券と株式の関係は
- 会社に出資することで「株式」を得て、株主となる
- 株式を所有し、株主であることを「株券」の占有で主張できる(株式発行会社の場合)
上記のように言えます。

株券発行会社と不発行会社の違い
株券発行会社と株券不発行会社では、株式譲渡の方法と、株主である旨を主張する手段に違いがあります。会社設立や変更で重要なのは、登記義務や定款に関することです。
両者の違いを表で整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 株券発行会社 | 株券不発行会社 |
|---|---|---|
| 株券の発行 | 物理的に発行する | 発行しない |
| 株式の管理 | 株券+株主名簿で管理 | 株主名簿で管理 |
| 株式の譲渡 | 株券の占有の移転 | 株主名簿の書き換え |
| 登記義務 | あり | なし |
| 定款の定め | 定めることができる | 定めない |
株券発行義務の有無の違い
株券発行会社では、株式の発行・併合・分割の各タイミングで株券を発行しなければなりません。公開会社では当該事由があったときに「遅滞なく」株券を発行し、非公開会社でも「株主から請求があれば」株券を発行しなければならないとされます(会社法第215条)
一方の株券不発行会社は、株券ではなく「株主名簿」で株式を管理します。株券を発行する代わりに、株主の氏名と住所・保有株式数・株式番号が記載されたリスト(株主名簿)を持つのです。株式取引があったとときは、当事者の承認や会社の意思決定機関の決議を経て、株主名簿を書き換えます(会社法第121条〜123条)
登記義務および定款の定めの違い
株券発行会社では、その旨の登記義務があり(会社法第911条3項10号)、定款で定めるのが普通です。法改正による不発行原則化の前から株券発行を続けている会社については、法務局の職権で「株券を発行する」旨が登記されています。
株券不発行会社では、不発行の旨について登記する必要はなく、定款の特段の定めをすることもありません。2006年の会社法施行以は、株券不発行しないことが会社設立のスタンダードとされているためです。
株主名簿とは
株券不発行会社では、株券を使わず「株主名簿」のみで株式・株主を管理します。株主名簿とは、会社が株主を把握するための法定帳簿であり、下記の情報が記載されます。
- 株主の氏名、住所
- 各株主の保有株式数
- 各株主の株式を取得した日
- (株券発行会社である場合)株券の番号
株式の移動が起きたときは、当事者の合意や会社の意思決定機関の決議を経て、株主名簿を書き換えることで管理を継続することが可能です。
株券不発行会社に移行するメリット・デメリット
株券不発行会社への移行は、株券の発行費用や保管、流通に伴う手間が省けるなど、運営の合理化につながるメリットがあることは確かです。一方で、株主名簿の管理義務を履行するための体制の構築を強いられるのは、決して無視できないデメリットです。
メリット:コスト削減や管理不全によるリスクがなくなる
企業側にある株券不発行のメリットは、株券の発行および保管のコストを削減し、株式・株主の管理不全によるリスクを低減できることです。
株券不発行とすれば、株券の発行に伴う印刷代や印紙税、発行した株券を厳重に保管するための貸金庫代、そして発行・保管・既存株券の回収に必要な人件費は不要になります。その代わり、信託銀行などを株主名簿管理人とするための費用・報酬が発生するものの、目に見えないコストや費用の重複などがなくなる分、低額で済むでしょう。
そして、信託銀行などの信頼できる機関に株主名簿管理を任せることで、株券回収ミスなどによって株主が不明になるなどの会社経営そのものを揺るがすリスクも低減できます。
株主側にとっても、株券を手元で管理する必要がなくなることで、財産管理の事務をなくせるメリットがあります。株主名簿の管理のしくみを万全にすることで、会社に「自らの地位と権利を守ってくれる」との信頼を寄せてくれる期待もあります。
デメリット:株主名簿の管理徹底が必須になる
株券不発行会社にとって、株主名簿は株主の権利を法的に証明する唯一の手段です。名簿管理に問題が起きると、株式(株主の権利)を回復させる手段がなくなり、大問題に発展するかもしれません。前提として、すべての株式会社には株主名簿の作成と本店での備え置きが義務付けられており、これを怠って管理不全に陥らせた場合、100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条)
株主名簿の管理不全を通じて起こるトラブルとしては下記のようなものが考えられます。
| ・株主名簿の管理不足が引き起こす可能性のあるトラブル ・配当金の支払い不達 ・株主総会の招集通知不達 ・株主の住所変更が反映されないことによる重要通知の不達 |
注意したいのは、株式の発行状況に変化が生じたときです。売買取引や発生による株式の移転があったときや、自社株買い・新規発行・株式併合・株式分割などを実施したときは、会社は株主名簿の名義書換手続きを正確かつ迅速に行わなくてはなりません(会社法第132条)この手続きを怠った場合も、株主や社外とのトラブルに発展しなかったとしても、100万円以下の過料に処されます。
したがって、常に正確な株主情報を維持するための管理体制の構築や、変更が生じた際の迅速な対応には、相応の人的・時間的コストがかかることを理解しておく必要があります。
株券不発行会社への移行の流れ
株券を発行している会社が株券不発行会社へ移行するときは、定款変更のための決議を経て、情報開示と変更登記を実施する必要があります。最も時間を要するのは株主総会への決議であり、定款変更が完了するまで全体で2か月程度かかる可能性があります。
ここでは、株券不発行会社への移行の流れを4段階で解説します。
STEP1:株券不所持の申出(必要に応じて)
株券不発行への移行の事前準備として、発行済の株券を回収しておくと良いでしょう。移行が完了すると株券は無効になりますが、効果のない株券が株主の手元にあると、株主自身の財産管理や会社の問い合わせ対応で混乱が生じる可能性があるためです。
株券の回収は、株主側から会社に対し、それぞれ株券不所持の申出(会社法第217条各項)を行ってもらう方法で進めます。株主名簿での管理体制があることなどを伝える内容で、株主に申出を促すと良いでしょう。
なお、株券不発行の申出を受けた会社は、次の順で対応する旨が法律で定められています。
- 申出に際し「申出にかかる株式の数」を特定したうえで、株券を提出してもらう
- 1にかかる株券を発行しない旨を株主名簿に記載する
STEP2:株主総会の特別決議による定款変更
株券不発行会社への移行は、定款の変更から始まります。具体的には、定款に「株券を発行しない」旨の規定を設けるか、既存の「株券を発行する」旨の規定を削除することが求められます。
そして、定款変更は会社法において重要事項と位置付けられており、原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法第466条・第309条第2項11号)。
特別決議までは、会社法に則り、下記の順で準備を進めましょう。
- 総会の開催日時と場所を決定する
- 定款変更に関する議案の概要を議題として設定する
- 開催日時、場所、議題などを記載した招集通知を総会開催日2週間前までに株主へ発送する(会社法第299条第4項)
STEP3:株主への通知と公告の実施
株主総会の特別決議で定款変更が承認されたら、次に、株主等に対する公告と通知を実施します。定款変更に関する通知と公告は、以下のルールで行わなくてはなりません(会社法第218条1項)
- 公告および通知の期限:定款変更の効力が生じる日の2週間前まで
- 通知の方法:株主等に対し「個別に」行う
- 通知の対象者:株主および登録株式質権者
なお、通知および公告には、以下の事項を記載する必要があります。
- 株券(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式の株券)を発行を廃止する旨
- 定款変更の効力発生日
- 定款変更の効力発生日において発行済の株券は無効となる旨
STEP4:定款変更の効力発生・登記申請
株券不発行の効力が発生した後は、速やかにその変更登記を行う必要があります。変更登記の期限は効力発生日から2週間以内で、申請先は本店所在地を管轄する法務局です。
定款変更後の登記申請では、添付情報として次の書類が必要です。
- 株主総会の議事録
- 公告をしたことを証する書面(または株式の全部につき株券を発行していないことを証する書面)
株券不発行会社への移行後に法務担当者が注意すべき3つのこと
株券不発行会社への移行後に注意したいのは、株式および株主の唯一の管理手段となる株主名簿の取扱いです。また、株主に対しても、不安感を抱かせないようなコミュニケーションを取るべきだといえます。
法務担当者が注意すべきことは、下記の3点です。
- 株式譲渡における手続きの変更点を把握する
- 株主への丁寧な説明とコミュニケーションを心がける
株式譲渡における手続きの変更点を把握する
株券不発行会社では、株式の譲渡に関する手続きが大きく変わります。
株券不発行会社の場合、当事者間の合意に加え、会社が管理する株主名簿への名義書換が必須となります。この株主名簿の記載は、会社や第三者に対して株主であることを主張するための重要な要件となるため、その管理の徹底がより一層求められます。
とくに中小企業の多くが発行する「譲渡制限株式」の場合、譲渡手続きは複雑になります(下記参照)。株式の移転と株主名簿書換だけではなく、譲渡承認に必要となるプロセスも留意しておきましょう。
- 譲渡承認請求:株式を譲渡しようとする株主、または譲受人から会社へ請求
- 譲渡承認決議:取締役会または株主総会で承認決議
- 株式譲渡契約の締結
- 株主名簿の書換請求
- 株主名簿の更新
株主への丁寧な説明とコミュニケーションを心がける
株券不発行会社への移行に伴い、物理的な株券がなくなると、株主は自身の権利証明や株式譲渡の手続きに関して不安を抱く可能性があります。とくに長期にわたる出資者は、高齢であることが多い点も踏まえて、制度変更に戸惑いを覚えがちです。
会社側は、上記を踏まえて株主に寄り添い、丁寧な説明とコミュニケーションを心がけなくてはなりません。
何よりも重要なのは「株券が廃止された後も、株主としての権利には一切変更がないこと」および「今後は株主名簿によって一元的に管理され、それによって会社の業務効率化などの面からも株主にメリットがあること」を、分かりやすい言葉で丁寧に説明することが重要です。
具体的な案内の方針としては、下記のようなものが考えられます。
- 株券不発行による業務効率化、コスト削減などのロジックを説明する
- 株主名簿の記載内容、管理方法について説明する
まとめ|株券不発行会社への移行は計画的な準備が成功のカギ
株券不発行会社への移行は、企業にとって株券の印刷費用や保管コスト、印紙税といった物理的費用を削減できるだけでなく、株券の紛失や盗難のリスクを解消できるなど、多くのメリットをもたらします。
一方で、物理的な株券が存在しなくなるため「株主名簿」の管理が株主の権利を証明する唯一の手段となる点には要注意です。株主名簿の記載事項に不備があった場合や、更新を怠った場合には、当事者間のトラブルでは済まされず、会社法に基づく過料が課される可能性もあります。
株式不発行会社への移行などを通じた「スマートな会社作り」を円滑に進めることができれば、企業価値の向上にもつながります。複雑な法的手続きに不安がある場合や、社内のリソースが限られている場合は、司法書士などの専門家へ相談してみましょう。