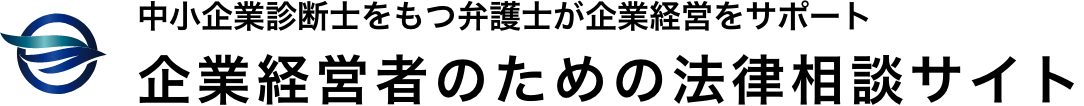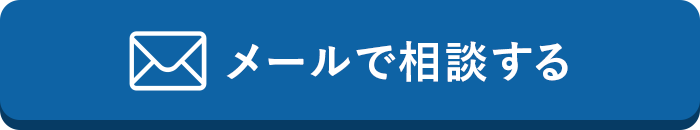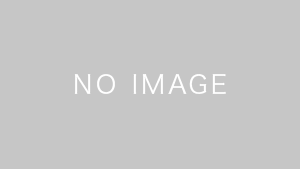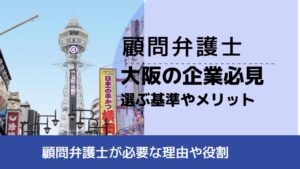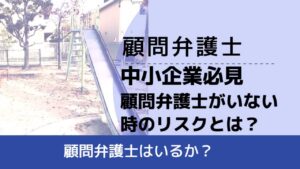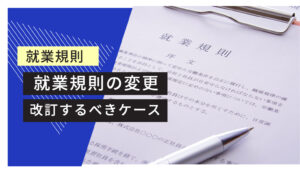企業の成長には資金調達が不可欠ですが、経営権の維持もまた重要な課題です。そこで注目されるのが議決権制限株式です。
この議決権が制限された株式は、出資を募りながらも、経営への影響を最小限に抑えることを可能にします。しかし、その詳細な仕組みや、導入における注意点を理解しておくことが重要です。
本記事では、議決権制限株式の定義から、メリット・デメリット、事業譲渡に活用する時の選択肢までを徹底解説します。
議決権制限株式とは?
議決権制限株式とは、株主総会での議決権の全部または一部の行使が制限されている株式のことです。以下の項目では、議決権制限株式の基本的な意義や仕組みを解説します。
株主総会での議決権が制限された株式のこと
会社の所有者である株主は、経営に関する重要事項を決定する「議決権」を持っているのが原則です。この株主総会での議決権は、取締役の選任や定款の変更といった、会社の根幹に関わる事柄に賛否を投じる権利です。
議決権制限株式とは、その名の通り、株主総会での議決権が「全部」または「一部」に制限された特殊な種類の株式です。これは、通常の株式とは異なり、株主が経営に与える影響力を限定する目的で発行されます。
例えば、「完全無議決権株式」は、全ての議案に対して議決権を行使できない株式であることを意味し、株主が会社の経営に全く関与しないことを意味します。また、議決権を制限できる事項や条件には制限がないため、決議事項の一部についてのみ制限することもできますし、保有する株式の一部を議決権制限株式に変更することもできます。
議決権制限株式の目的とは?
通常の株式(普通株式)で資金調達を行うと、新たな株式の発行により発行済株式総数が増加し、その結果、経営者(創業者など)が保有する議決権の比率が相対的に低下します。
この議決権比率の低下は、株主総会における重要事項の意思決定を不安定にする可能性があります。これにより、経営陣の意に反する決定が下されたり、最悪の場合、会社の経営権を失うリスクに直面することもあります。
議決権制限株式を活用することで、既存経営者の議決権比率への影響を最小限に抑えながら、資金調達を行うことができます。遺留分等の相続対策をしながら、後継者への事業承継を実現するために議決権制限株式を活用することもあります。
会社法で定められた発行上限とは?
公開会社が議決権制限株式を発行する場合、会社法には重要な上限が定められています。具体的には、会社法第115条の規定により、議決権制限株式は原則として発行済株式総数の2分の1までとされています。
ただし、非公開会社(発行する全部の株式について譲渡制限が付されている株式会社)の場合にはこのルールは適用されません。そのため、非公開会社は、発行済株式総数の2分の1を超える議決権制限株式の発行が可能です。
| 会社の種類 | 発行上限 | 根拠・条件 | 目的・特徴 |
| 公開会社 | 発行済株式総数の2分の1まで | 会社法第115条の規定 | 株主による経営監視機能の維持、株主総会の形骸化防止 |
| 非公開会社 | 定款に別段の定めがあれば2分の1超も可能 | 定款の定め | 柔軟な資本政策や事業承継戦略の実行 |

経営者が知っておくべき議決権制限株式のメリット・デメリット
議決権制限株式は、企業が資金を調達しながら経営の安定性を維持するための有効な選択肢といえます。しかし、議決権制限株式を活用するにあたって、そのメリットとデメリットの両面を深く理解しておくことが重要です。
【メリット】経営の主導権を維持したまま資金調達が可能になる
企業の持続的な成長には、外部からの資金調達を必要とするケースもあります。しかし、議決権の制限のない普通株式を発行して資金を調達すると、経営陣が保有する議決権の比率が相対的に低下するリスクがあります。これにより、経営の主導権が揺らぎ、本来目指す経営方針を維持できなくなる可能性も考えられます。
議決権制限株式は、このような課題を解決する有効な手段です。投資家から出資を受けた場合でも、発行される株式には議決権が付与されないため、発行済株式総数が増えても経営陣が保有する議決権比率への影響を抑えることができます。これにより、資金調達によって経営の安定性が損なわれる事態を防ぎながら、経営の主導権を維持できます。
【メリット】円滑な事業承継や相続対策に役立つ
議決権制限株式は、円滑な事業承継や相続対策において、有効な手段となります。例えば、後継者には、会社の経営を担う上で不可欠な議決権のある普通株式を集中させ、他の相続人には議決権制限株式を相続させるといった対応が可能です。これにより、経営権が分散するのを防ぎ、後継者による安定した会社経営を実現できます。
また、議決権制限株式に「剰余金の配当優先」などの有利な条件を付加することで、経営に直接関与しない相続人との財産的な公平性を確保しやすくなります。これは、相続時のトラブルを未然に防ぎ、円滑な事業承継を促す上で重要な要素です。さらに、議決権がない株式は、一般的に評価額が低くなる傾向があるため、相続財産全体の評価額を抑える効果も期待できます。結果として、相続税の負担軽減にもつながり得るでしょう。これらの点から、事業承継における戦略的な選択肢として活用できるのです。
【デメリット】議決権がないため魅力がないことも
議決権制限株式のデメリットとして、出資者とっての魅力が低下する点が挙げられます。一般的に、投資家は出資を通じて企業の成長に貢献し、経営に参加する権利である議決権を重視する傾向があります。そのため、議決権が制限された株式は、出資を検討する投資家から敬遠される可能性があります。結果として、普通株式に比べて資金調達の難易度が上昇したり、株価が低く評価(ディスカウント)されたりする傾向が見られます。
このデメリットを補うために、配当優先権を付与するなどすることもあります。ただし、配当実績の乏しい中小企業においては、配当優先の議決権株式は活用しにくいこともあります。
【デメリット】株式の価値評価が複雑になりやすい
議決権制限株式を導入することで、株価算定が複雑になることもデメリットの一つといえます。
ただし、国税庁が公表している「種類株式の評価について」により、議決権制限株式の評価方法の指針が示されています。具体的には、会社の無議決権株式及び議決権のある株式は、原則として議決権の有無に関わらず株価評価することとし、選択により無議決権株式の評価を5%減額し、議決権株式を5%上乗せした金額により評価できるものとされています。他方で、無議決権株式ではなく、議決権の制限がされた株式の評価方法については明記されていませんが、原則通り議決権のある普通株式と同様の評価方法により評価されるものと解されています。
【デメリット】発行手続きや既存株主への説明が必要になる
議決権制限株式のような種類株式の発行には、定款の変更が伴うことがほとんどです。この定款変更を行うためには、株主総会における特別決議が不可欠です。特別決議では、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要とされ、一般的な普通決議よりも可決のハードルが大幅に高くなります。
また、議決権制限株式の発行は、会社の資本構成や既存株主の権利に大きな影響を与えるため、その目的や条件について、既存株主へ丁寧に説明し、理解と合意を得るプロセスが非常に重要です。この合意形成を怠ると、後にトラブルへ発展する可能性もあります。
事業承継のために議決権制限株式を発行するパターン
議決権制限株式の発行は、会社法に則った厳密な手続きが求められます。そのため、法的な要件を満たし、既存株主への影響も考慮しながら、慎重に進める必要があります。
議決権制限株式を発行する場合には、新規発行する場合だけでなく、既発行の普通株式や種類株式を議決権制限株式に変更する場合があります。それぞれのパターンで取るべき手続が異なるため、パターンに分けて解説します。
定款の変更をする
まず、議決権制限株式を発行するには、会社の定款の変更が必要です。具体的には、以下の事項を定款に明記しなければなりません。なお、事業承継を円滑に進めるために議決権制限株式の発行するときは、議決権の制限だけでなく、会社が種類株式に損害が生じる可能性のある行為を及ぶ場合でも種類株式総会の決議を要しない旨を定めておくべきです(会社322条2項)。
- 株主総会において議決権を行使することができる事項
- 議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
| 【無議決権株式の場合】 第〇〇条 当社の議決権制限株式は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 |
| 【一部制限する場合】 第〇〇条 当社の議決権制限株式について、議決権を行使することができる事項は次のとおりとする。 ①〇〇に係る決議 ②〇〇に係る決議 2 議決権制限株式は、前項以外については議決権を有しないものとする。 |
この定款変更には、株主総会における「特別決議」という、通常の決議よりも厳格な承認プロセスが求められます。特別決議は、原則として、議決権を行使できる株主の議決権の過半数が出席し、かつ、その出席株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって成立します。
株主総会で定款変更が承認された後、その効力発生日から2週間以内に、管轄の法務局にて変更登記を申請する義務があります。
株主全員に議決権制限株式を無償割当する
まず、既存の株主全員に持株比率に応じて議決権制限株式を無償で割り当てる方法です。これにより、経営者は、無償で取得した議決権制限株式を非後継者の相続人に承継し、後継者に普通株式を承継することで事業承継を行います。
無償割当により、株式の総数が増加することで、一株あたりの評価額は下落しますが、既存株主に平等に割り当てられるため、株主が保有する株式全体の価値に変動はありません。
また、株式の発行にあたって、経営者が会社に出資する必要がないため、資金を準備する必要もないため、事業承継対策として利用し易い選択肢といえます。
経営者のみに議決権制限株式を新規発行する場合
経営者に議決権制限株式を割り当てした上で、遺言や生前贈与により、普通株式を後継者に、議決権制限株式をその他の相続人に承継させるパターンです。
事業承継のために議決権制限株式を発行する場合、経営者の資産状況によっては、より多くの議決権制限株式を引き受ける必要が生じる可能性があります。例えば、経営者の財産が株式のみで、相続人が子供と2人(後継者と非後継者)と仮定すると、非後継者の遺留分4分の1を確保するために、発行済株式の3分の1に相当する議決権制限株式を発行する必要があります。これに伴って、経営者は、会社に対して多くの資金を出資する必要に迫られることもあります。加えて、議決権制限株式の発行価格が適正でない場合には、一株あたりの評価額が低下することになりかねず、経営者以外に株主がいる場合には、ほかの株主に損失を及ぼすことにもなります。
そのため、経営者に議決権制限株式を発行するパターンは、株式の全部または大部分を経営者が保有している場合には適切な選択肢といえます。
発行済みの普通株式の一部を議決権制限株式に変更する場合
経営者が保有している株式の一部を議決権制限株式に変更する方法です。この方法を行うためには、経営者も含めた全ての株主の同意を得る必要があると考えられています。
この方法により、経営者が持っている普通株式を後継者に承継した上で、議決権制限株式を非後継者に承継することで事業承継を行います。
この方法は、無償割り当ての方法と同じように、出資するための資金を手配する必要がない点で利点があります。また、株式総数が変わらないため、その他の株主から賛同を得やすい傾向にあります。
ただ、経営者の他に株主がいる場合には、経営者の株式の一部を議決権制限株式に変えることにより、経営者の議決権比率が低下してしまうリスクがあることには留意するべきです。
そのため、この方法は、経営者がすべての株式を保有しているような場合に利用することを検討するべきかと考えます。
全部取得条項付株式を利用する場合
全部取得条項付株式を利用することで事業承継を行うこともできます。
具体的には、全ての既発行の普通株式を全部取得条項付種類株式に内容を変更した上で、既存株主に対して普通株式を発行するとともに、会社が株式を取得する対価として議決権制限株式を発行するという方法です。
しかし、この方法は、定款変更、全部取得条項付種類株式への変更、新株発行、全部取得条項付種類株式の取得と議決権制限株式の交付を行うために、それぞれ株主総会の特別決議等を必要とするため、手続が煩雑になります。また、全部取得条項付種類株式への変更に反対する株主には株式買取請求権が認められるため、株式の買取資金を準備しておく必要もあります。
そのため、全部取得条項付株式を利用した事業承継は他の方法と比べると選択しにくい方法といえます。
議決権制限株式を利用した事業承継は難波みなみ法律事務所へ
議決権制限株式のメリットとして、経営の安定性を保ちつつ大規模な資金調達が可能となる点、円滑な事業承継や相続対策に有効である点などが挙げられます。特に、同族企業の事業承継において、経営権の集中を図りながら関係者間の公平性を保つ上で、有効な選択肢となり得ます。
一方で、株式の価値評価が複雑になりやすい点、定款変更や株主総会の特別決議といった発行手続きの煩雑さ、既存株主への丁寧な説明と合意形成が求められる点も考慮が必要です。
ただ、議決権制限株式の導入に際しては、法務や税務に関する専門的な知識が求められるため、弁護士へ相談することを強くお勧めします。