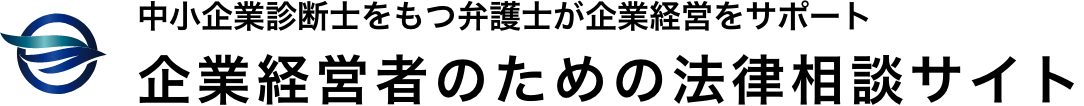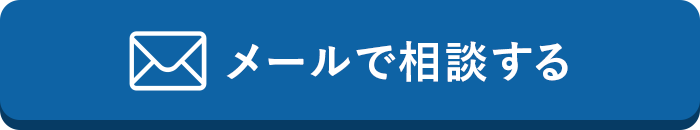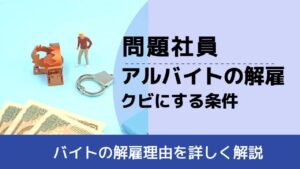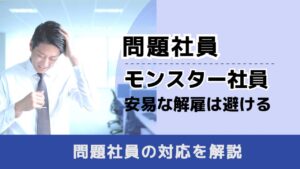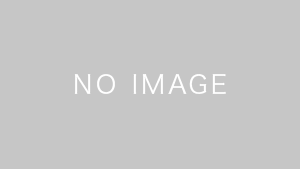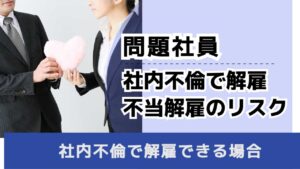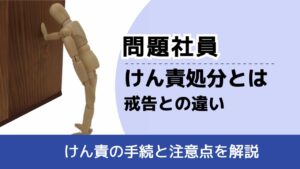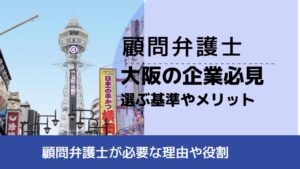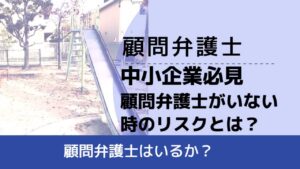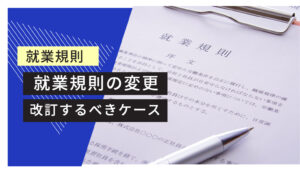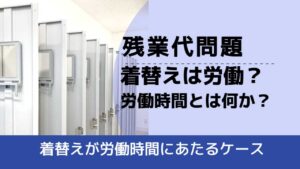企業の労務担当者の皆様、管理監督者に対する深夜割増賃金の支払いは本当に不要なのでしょうか?
「管理職だから」「役職手当を支給しているから」という理由だけで、時間外手当や深夜手当を支給しないのは、実は違法となるケースがあります。労働基準法上の管理監督者の定義を正しく理解し、適切な労務管理を行うことは、企業にとって非常に重要な課題です。
この記事では、管理監督者の深夜割増賃金について、法的な根拠から具体的な注意点まで、わかりやすく解説します。ぜひ、御社の労務管理体制を見直すきっかけとしてください。
結論:管理監督者にも深夜割増賃金の支払いは必要です
まず結論からお伝えしますと、労働基準法上の管理監督者に該当する従業員に対しても、深夜労働に対する割増賃金の支払いは、法律で明確に義務付けられています。
では、なぜ、時間外労働や休日労働の割増賃金は不要なのに、深夜労働の割増賃金は必要となるのでしょうか。以下では、この疑問に対する法的な根拠と具体的な運用ルールについて、詳しく解説していきます。
「残業代は不要なのに深夜手当は必要」な理由
労働基準法第41条は、「管理監督者」に対し、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を除外すると定めています。この条文に基づき、管理監督者には原則として、法定労働時間を超える時間外労働や、法定休日における労働に対する割増賃金(残業代、休日手当)の支払い義務がないとされています。これが、「管理監督者には残業代が不要である」と一般的に認識されている理由です。
管理監督者に適用される労働基準法の規定は、以下の表のようにまとめられます。
| 規定の種類 | 管理監督者への適用状況 | 根拠条文 |
| 労働時間 | 適用除外 | 第41条 |
| 休憩 | 適用除外 | 第41条 |
| 休日 | 適用除外 | 第41条 |
| 深夜業(深夜手当) | 適用される | 第37条第4項 |
しかし、ここで重要なのは、労働基準法第41条による適用除外の対象に「深夜業」に関する規定は含まれていないという点です。深夜業については、同法第37条第4項において、深夜労働(原則として22時から翌朝5時までの間)を行った場合、通常の賃金に加えて割増賃金を支払うことが別途義務付けられています。
したがって、管理監督者であっても深夜時間帯に労働を行った場合は、他の一般従業員と同様に、法律で定められた深夜割増賃金を支払う義務があります。最高裁判所の判例でも、管理監督者に対する深夜割増賃金の支払い義務が明確に示されています。
最高裁判例平成21年12月18日
労働基準法41条にいう「労働時間,休憩及び休日に関する規定」には,深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。以上によれば,労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく,管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。
押さえておきたい判例のポイント
ことぶき事件(最高裁判所第二小法廷平成21年12月18日判決)では、管理監督者である労働者(美理容会社の総店長)が、深夜割増賃金の支払いを求めて提訴した事案です。
最高裁判所は、このような管理監督者であっても、深夜割増賃金を請求できると明確に判断しました。その理由は以下の通りです。
- 労働基準法第41条が適用除外とするのは、労働時間、休憩、休日の規定に限られること。
- 深夜業に関する割増賃金の規定は労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働の規制をする点で、労働時間に関する他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
- そのため、深夜業の規定は労働基準法第41条の適用除外には含まれません。
これらの判例は、企業が管理監督者に対しても深夜割増賃金の支払い義務を適切に果たすべき、法的な根拠となります。司法の判断を尊重し、適正な賃金支払いを徹底することが、企業に強く求められています。

多くの企業が誤解している管理監督者の賃金ルール
「管理監督者には残業代が不要である」という認識は多くの企業で広く浸透していますが、これが「全ての割増賃金が支払不要である」という誤解につながるケースも少なくありません。特に、深夜割増賃金まで支払う必要がないと誤解している企業も存在します。
また、役職手当や管理職手当といった名目で手当を支払っている場合、「すでに手当の中に深夜割増分も含まれている」と考える企業も存在します。しかし、単に役職手当を支給しているだけでは、深夜割増賃金の支払い義務を果たしたとは認められません。個別の手当に深夜割増分が含まれていると認められるためには、その手当が深夜労働の対価である旨が明確に定められ、かつ、金額も深夜割増賃金相当分として十分に支払われている必要があります。
年俸制を導入している管理監督者についても、同様の誤解が見られます。「年俸額に全ての割増賃金が含まれている」という考え方に基づき、深夜割増賃金を別途支払わないケースも存在します。しかし、年俸制であっても、深夜労働に対する割増賃金の支払い義務は免除されません。労働基準法の規定に従い、深夜割増賃金は別途支払う必要がある点を認識しておくことが重要です。
自社の管理職は「管理監督者」?法律上の3つの判断基準
企業内で「部長」や「課長」といった役職がついていても、労働基準法で定める「管理監督者」に該当するとは限りません。管理監督者であるか否かは、役職名だけでなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の待遇といった実態に基づき、総合的に判断されることが重要です。
これから詳しく解説する以下の3つの判断基準を参考に、自社の管理職がこれらを満たしているかを慎重に見極める必要があります。
①経営に関わる重要な職務内容・責任と権限があるか
「管理監督者」であるか否かを判断する上で、経営者と一体的な立場で事業運営に深く関与しているかどうかが重要な要素です。管理監督者の判断要素の中で最も重要視されるのがこの①の要素になります。
具体的には、経営会議への参加を通じて経営方針について発言権を持ち、事業計画の策定や部門全体の統括、経営戦略の企画・立案などに深く関与していることが求められます。
さらに、部下の採用・解雇、人事考課、昇給・昇格、賞与といった労働条件の決定、あるいは部下のシフトの決定など、労務管理に関する実質的な指揮監督の権限を有しているかも重要な判断基準となります。これらの権限が経営者から具体的に委ねられている実態があるかを確認してください。
一方で、上司の決裁がなければ業務を進められない、上司の命令を部下に伝達するに過ぎない、または定型業務が中心で経営に関する重要な決定への影響力がほとんどない、といった場合は、たとえ役職名が管理職であっても、労働基準法上の管理監督者とは認められにくいでしょう。
| 項目 | 認められる主な条件 | 認められにくい主な条件 |
| 経営への関与 | 経営会議での発言権、事業計画策定、部門統括、戦略企画・立案への深い関与 | 定型業務が中心、経営に関する重要な決定への影響力がほとんどない |
| 労務管理の権限 | 部下の採用・解雇、人事考課、昇給・昇格、賞与決定、勤務割決定など実質的な指揮監督権限 | 上司の決裁なしには業務を進められない、上司の命令を部下に伝達するに過ぎない |
②出退勤時間を自分で決められる勤務形態か
労働基準法上の管理監督者は、労働時間に関する厳格な規制の対象外とされています。そのため、始業・終業時刻や出退勤について、自身の裁量で自由に決定できるかどうかが重要な判断基準となります。出退勤の時間を自身でコントロールできず、一般の従業員と同様に厳格な制限を受けている場合は、管理監督者性が否定される可能性が高まります。
例えば、以下のような場合は、勤務形態に関する裁量がないと判断されやすくなります。
- 遅刻や早退によって賃金が控除される
- タイムカードで出退勤時間を管理されている
- 上司の承認がなければ出退勤時間を変更できない
ただ、タイムカードなどで勤怠を記録している場合でも、それが健康管理や在籍確認を目的としたものであり、実態として労働時間に関する裁量を持っているならば、直ちに管理監督者性が否定されるわけではありません。しかし、他の従業員と同じように出勤時間が制限されているようなケースでは、裁量があるとは認められにくいのが実情です。企業は、形式的な役職名だけでなく、管理職が実態として自身の労働時間を自由にコントロールできる状況にあるかを確認することが重要です。
③役職に見合った十分な賃金が支払われているか
管理監督者には、労働時間、休憩、休日に関する規制が適用されない代わりに、その地位にふさわしい賃金上の優遇措置が講じられていることが求められます。この点は、厚生労働省も管理監督者の判断基準の一つとして示しています。
明確な金額基準はありません。しかし、判断基準としては、基本給や役職手当といった個別の賃金がその地位にふさわしい水準であるか、また、一般従業員と比較して賃金総額が十分に高額であるかという点が重要です。特に、時間外手当が支給される部下の賃金総額と比較して、管理監督者の賃金がそれを下回る「逆転現象」が発生している場合、管理監督者性が否定される可能性が極めて高くなります。
【具体例あり】管理監督者の深夜割増賃金の計算方法
管理監督者の深夜割増賃金は、労働基準法に基づき、深夜労働の時間と割増率を正確に把握し、計算することが求められます。
ここでは、月給制の管理監督者を例に、具体的な計算手順とモデルケースをご紹介します。
深夜割増の対象となる時間帯と割増率
労働基準法第37条により、深夜労働には通常の賃金に割増率を上乗せして支払うことが義務付けられています。この深夜労働とは、原則として午後10時から翌朝5時までの時間帯における労働を指します。この時間帯に労働した場合、通常の賃金に対し25%以上の割増率が適用されます。
月給制の場合の計算手順
管理監督者の深夜割増賃金は、以下の3ステップで計算できます。
ステップ1:1時間あたりの基礎賃金を算出
月給から、家族手当や通勤手当など、労働基準法施行規則で定める「除外手当」を差し引いた額を、月平均所定労働時間で割ることで基礎賃金を算出します。
ステップ2:計算式に当てはめる
算出した1時間あたりの基礎賃金に、深夜労働の割増率0.25と実際の深夜労働時間数を乗じて深夜割増賃金を計算します。
計算式:`1時間あたりの基礎賃金 × 0.25 × 深夜労働時間数`
ステップ3:具体的な計算例
具体的な計算例として、月給50万円(除外手当なし)、月の所定労働時間160時間、深夜労働が月に20時間発生した場合を考え、深夜割増賃金を算出してみましょう。
この例では、管理監督者に対して月15,625円の深夜割増賃金が発生することになります。
① 前提条件
給与 500,000円
月の所定労働時間 160時間
深夜労働時間 20時間
② 計算結果
1時間あたりの基礎賃金 50万円÷160時間=3,125円
深夜割増賃金 3,125円×0.25(割増率)×20時間=15,625円
役職手当などに深夜手当を含める際の注意点
深夜手当を手当(固定深夜手当)などに含めることは可能ですが、有効と認められるためには法的な要件を満たさなければなりません。
その際、最も重要なのは、「通常の労働時間の賃金に当たる部分」と「深夜割増賃金に当たる部分」を明確に区別できることです。この明確区分性の要件を満たさなければ、単に役職手当を支給するだけでは、深夜割増賃金の支払い義務を果たしたとは認められません。
明確区分性を満たすためには、就業規則や賃金規程、雇用契約書などで、「手当のうち、具体的な金額(例:〇〇円)を、何時間分(例:〇時間分)の深夜手当として支給する」と明記し、労働者に周知徹底することが求められます。単に「役職手当に含まれる」と漠然と定めるだけでは不十分です。
深夜手当を役職手当に含める際に満たすべき「区分性の要件」のポイント
- 「通常の労働時間の賃金」と「深夜割増賃金」を明確に区別すること
- 就業規則、賃金規程、雇用契約書等に以下を明記し、労働者に周知徹底すること
- 深夜手当といったように手当の名称を分かりやすくする(他の手術が混在しないようにする)
- 具体的な金額(例:深夜業手当〇〇円のうち△△円)
- それに対応する深夜労働の時間数(例:〇時間分)
- 単に「〇〇手当に含まれる」といった漠然とした定めでは不十分であること
- 上記の要件を満たさない場合、深夜割増賃金の支払い義務を果たしたとは認められず、未払い賃金のリスクが生じること
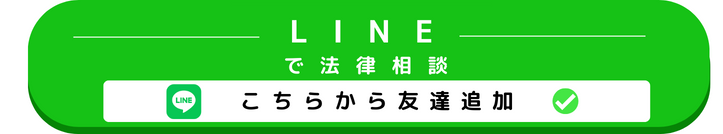

管理監督者の労務管理で企業が遵守すべきこと
管理監督者に関する労務管理において、企業が遵守すべき事項は多岐にわたります。特に深夜割増賃金支払い義務の正しい理解は重要です。
管理監督者であっても、労働時間の把握や健康管理を怠ることはできません。労働者の健康確保や未払い賃金トラブルの防止のため、以下の労務管理上の遵守事項を徹底することが、企業のコンプライアンス維持と従業員の心身の健康を守る上で極めて重要です。
労働時間把握の義務化は管理監督者も対象
2019年4月に施行された働き方改革関連法により、労働安全衛生法が改正されました。この改正によって、管理監督者を含むすべての労働者の労働時間を客観的な方法で把握することが、企業に義務付けられています。
この義務化の主な目的は、長時間労働を是正し、労働者の心身の健康を確保することです。「管理監督者には残業代が発生しないため、労働時間の把握は不要である」という誤解が多く見受けられますが、これは間違いです。労働時間の把握は、給与計算だけでなく、過重労働による健康障害の防止のためにも、管理監督者に対しても適用される重要な義務です。
深夜労働の抑制と健康への配慮
深夜労働は、従業員の心身に大きな負担をかけ、生産性の低下や健康障害のリスクを高めることが明らかになっています。
長時間労働に伴うリスクを抑制するため、企業は深夜労働の抑制に努める必要があります。深夜労働の抑制には、以下のような具体的な対策が有効です。
- 業務プロセスの見直し
- 人員配置の適正化
- DXツールを活用した業務効率化
就業規則や賃金規程の整備・見直し
管理監督者に対して深夜割増賃金を適切に支払うためには、就業規則や賃金規程を整備し、必要に応じて見直すことが不可欠です。
これらの規程には、管理監督者にも深夜割増賃金を支払う旨を明確に規定し、従業員との間で認識の齟齬が生じないようにすることが重要です。特に、特定の手当に深夜手当を含めて支給する場合には、その根拠となる具体的な金額や、対応する深夜労働時間数を明記し、通常の賃金部分と深夜割増賃金部分とを明確に区別できる「区分性の要件」を満たす必要があります。
規程を見直したり、新たに制定したりした際は、労働基準法に基づき、その内容を全従業員に周知することが義務付けられています。具体的には、従業員がいつでも確認できる状態にするため、以下のいずれかの方法で周知することが求められます。
- 事業所の見やすい場所への掲示
- 書面での交付
- 電磁的方法(社内ネットワークなど)による閲覧
未払いがあった場合の罰則と企業リスク
管理監督者への深夜割増賃金の支払いを怠ると、企業は労働基準法違反となり、重大な罰則や経営上のリスクに直面します。
例えば、労働基準法第119条に基づき、違反した事業主には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。これは単なる行政指導にとどまらず、刑事罰の対象となり得る深刻な問題です。
最も大きなリスクは、過去に遡って、未払いの深夜手当の支払いを請求されることです。賃金請求権の時効は3年のため、長期間にわたる未払いがあれば、多額の支払い義務が発生する可能性があります。その上、未払賃金には、遅延損害金が付加されます。在職中であれば年3%、退職後であれば年14.6%の遅延損害金が発生します。さらに、未払い賃金の支払いに加えて、裁判所の命令により、未払い額と同額の「付加金」の支払いが課される可能性もあります。また、名ばかり管理職に長時間労働を強いている場合には、時間外手当や休日手当の請求も受けるため、さらに経済的な負担は増えることになります。
さらに、労働基準監督署による是正勧告や指導の対象となるだけでなく、企業の社会的信用も大きく損なわれます。これにより、いわゆる「ブラック企業」というイメージが定着し、優秀な人材の採用活動に悪影響を及ぼしたり、既存従業員の離職率増加につながったりする恐れもあります。コンプライアンス意識の欠如は、最終的に企業の経営基盤を揺るがしかねないため、適切な賃金支払いを徹底することが重要です。
| リスクの種類 | 具体的な内容 |
| 刑事罰 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条) |
| 金銭的リスク | 過去3年間の未払い賃金請求、同額の付加金支払命令(裁判所) |
| 社会的信用失墜 | 「ブラック企業」イメージの定着、採用難、離職率増加 |
管理監督者の問題は難波みなみ法律事務所へ
本記事では、管理監督者に対する深夜割増賃金の支払い義務について、法的根拠から具体的な計算方法、企業が遵守すべき労務管理上の注意点までを詳しく解説しました。結論として、労働基準法上の管理監督者に該当する従業員に対しても、深夜労働に対する割増賃金の支払いは、法律で明確に義務付けられています。しかし、多くの企業でこの点が誤解されているケースが少なくありません。
管理監督者の深夜労働ルールを正しく理解し、適切に運用することは、企業がこれらの法的・経営的リスクを回避する上で不可欠です。法令を遵守し、従業員の健康を守り、健全な職場環境を構築することが、企業全体の生産性向上と持続的な発展につながるでしょう。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。