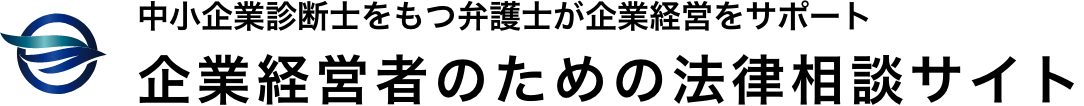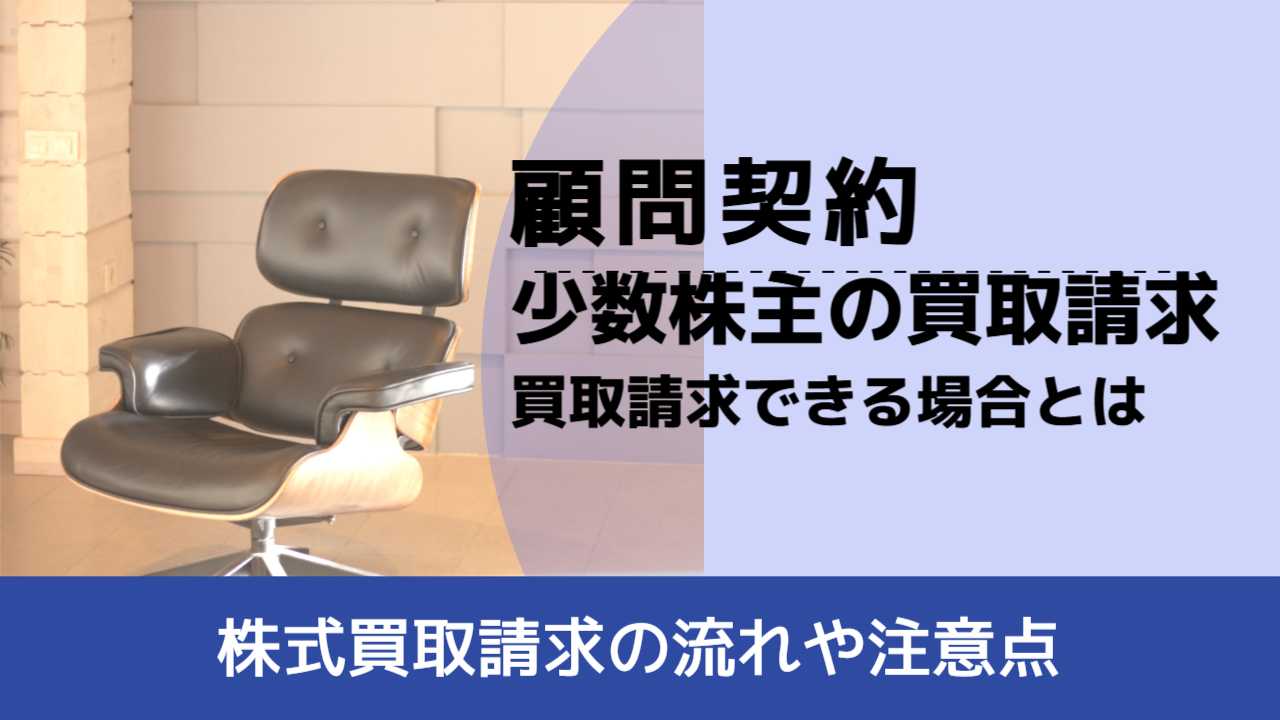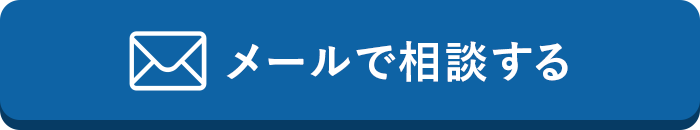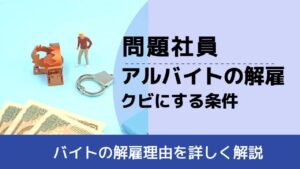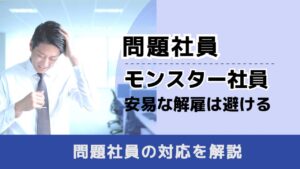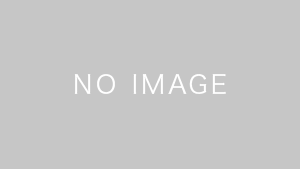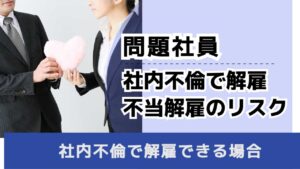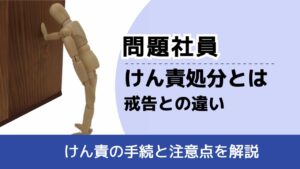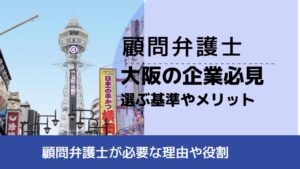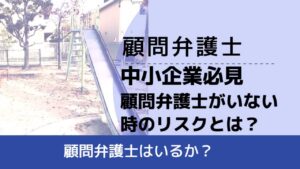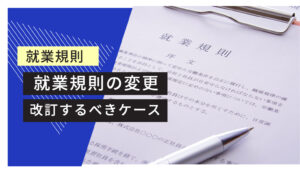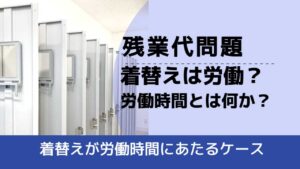中小企業の少数株主にとって、保有する株式の扱いは悩ましい問題です。会社の規模によっては、株式を売却したくても、買い手が見つからないケースも少なくありません。このような状況で検討したいのが、会社に対して株式買取請求を行うという選択肢です。
もっとも、買取請求の手続きは複雑で、専門的な知識も必要になります。そこで本記事では、少数株主が株式買取請求を行う際の流れや、適正価格で株式を売却するためのポイントについて、わかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
会社の決定に納得できない…少数株主が使える「株式買取請求権」とは?
非上場会社においては、市場での株式売買が難しいケースも少なくありません。このような状況で、株式買取請求は保有する株式を現金化する有効な手段となります。ただし、株主買取請求の権利は、いつでも自由に株式の買い取りを請求できるわけではない点には、注意が必要です。
株式買取請求権は法律で認められた少数株主の権利
この株式買取請求権は、会社法に明確に定められた少数株主の正当な権利です。
株式会社の運営は多数決の原理に基づくため、合併や事業譲渡といった重要な意思決定において、少数株主の意見が反映されず、意に反する不利益を被る可能性があります。
そこで会社法は、投下資本の回収をする機会を保障し、その財産的な利益を保護する目的で、会社に対し「公正な価格」で株式の買い取りを請求できる権利を認めています。これは、多数決の原則が生じさせる不公平を調整して、少数株主が円滑に会社から退出できるための重要な法的制度です。
なぜ株式買取請求権が必要なのか?
株式会社の意思決定は、株主総会における多数決の原理に基づいて行われるのが原則です。これは、株主の議決権が保有する株式数に比例するため、特に多数派の株主の意見が、会社の経営方針に強く反映されることを意味します。
そのため、M&A(合併や株式交換など)や事業譲渡といった会社の経営を大きく左右する重要な決定が、一部の少数株主の意に反して可決されるケースも発生し得ます。
このような状況において、少数株主が自身の投下資本を回収する機会を保障する必要があります。そこで、会社法は、多数決の原則によって生じる不公平を是正し、少数株主が不利益を被ることなく円滑に会社から退出できるよう、株式買取請求権を制度として設けています。

株式買取請求権を行使できる具体的なケース
株式買取請求は、いつでも行使できるわけではなく、会社法等で規定されたケースに限り認められています。
会社法に定められた具体的なケースとして、どのような状況で株式買取請求権の行使が認められるのかを詳しく解説します。
会社のM&A(合併・株式交換など)に反対する場合
M&A(組織再編行為)は、会社の組織を根本的に変更する重要な経営戦略の一つです。
M&A(組織再編行為)の主な種類
- 合併
- 会社分割
- 株式交換
- 株式移転
このような組織再編が行われる際、これに反対する株主は、会社法に基づき株式買取請求権を行使することが可能です。
これらの組織再編行為は、株主が保有する株式の価値や株主としての地位に重大な影響を及ぼす可能性があるため、少数株主にとって大きな関心事となり得ます。例えば、合併によって会社の事業内容や経営方針が大きく変わる場合などが考えられます。
このように、会社法はM&Aに同意できない株主に対し、保有株式を公正な価格で会社に買い取ることを求める株式買取請求権を認めています。
事業譲渡に反対する場合
会社が事業の全部、またはその重要な一部を第三者に譲渡する「事業譲渡」を行う際には、株主総会の特別決議による承認が必要とされます(会社法第467条1項)。この事業譲渡は、会社の経営基盤や収益性に大きな影響を及ぼし、株主の利益を損なう可能性も考慮されるため、事業譲渡に反対する株主には、「株式買取請求権」が認められています。
株式併合(スクイーズアウト)が行われる場合
株式併合とは、複数の株式を1株に統合する手続きであり、大株主が会社の経営権を完全に掌握し、少数株主を強制的に退出させる「スクイーズアウト」の手法として用いられます。株式併合は、株主総会の特別決議で可決されることで実行可能です。具体的には、議決権の3分の2以上の株式を保有する株主がいれば、株式併合を行うことができます。
株式併合が行われると、保有株式数が少ない少数株主は、併合後に1株未満の「端株」しか保有できなくなる場合があります。これにより、事実上、議決権などの株主としての権利を失うことにもなりかねません。このような株式併合によって不利益を受ける少数株主を保護するため、会社法では株式買取請求権の行使が認められています。ただ、株式買取請求を行使できるのは株式併合に反対した株主に限られます。
会社との価格協議が進展しない場合には、裁判所における手続きを経て公正な価格を決めることになります。
株式に譲渡制限が付与される場合
会社の定款変更によって、それまで自由に譲渡できた株式全部に「譲渡するには会社の承認が必要」といった譲渡制限が新たに設けられるケースは、株式買取請求権の行使が認められる具体的な状況の一つです。このような定款変更は、株主総会の特別決議によって行われます。
譲渡制限が設けられると、株主は株式を自由に売却し、現金化することが困難になります。これにより、投下資本の回収が著しく困難となります。例えば、会社が承認しない限り、保有株式を第三者に売却できなくなるため、株式の流動性が失われることになります。
【5ステップで解説】株式買取請求の具体的な手続きと流れ
少数株主が持つ重要な権利である株式買取請求権ですが、その行使には会社法で定められた手続きを減る必要があります。これらの手続きを正確に踏まなければ、せっかくの権利を行使できなくなる可能性もあるため、十分な注意が必要です。
以下の項目では、この株式買取請求の手続きを、会社からの通知から最終的な裁判所への申し立てに至るまで、時系列に沿って5つのステップで具体的に解説します。
株式買取請求権を行使できる「反対株主」の範囲
株式買取請求権を行使できる株主は、問題となる行為に対する「反対株主」です。その行為に関する議決権を持たない株主や単元未満株式の株主も含まれますので、注意が必要です。
Step1:株主総会で反対の意思を表明する
株式買取請求権を行使するための重要な前提条件として、明確に「反対」の意思を表明する必要があります。
株主総会を欠席したり、議決権を行使しなかったり(棄権)しただけでは、反対の意思表示とは認められず、株式買取請求権の行使ができませんので、注意が必要です。
株主総会で議決権を行使できる株主は、株主総会に先立って反対する旨を会社に通知した上で、総会において反対する必要があります。他方で、議決権を行使できない株主の場合は、反対の通知を要することなく買取請求を行使することができます。
会社法には、反対の意思表示方法について厳格な規定はありませんが、口頭ではなく書面で行うのが望ましいとされています。特に、株主総会に先立って書面で反対の意思を通知する際には、後日の証拠となるよう、内容証明郵便などを利用し、その記録を必ず保管しておくことが重要です。議決権行使書面や電子投票による反対も、有効な意思表示として認められます。
他方で、委任状を用いて反対の意思を表示することは控えるべきです。委任状は、会社に対する意思表示ではないからです。
| 種類 | 意思表示の方法 |
| 認められない意思表示 | 株主総会の欠席、議決権の棄権 |
| 認められる意思表示 | ・株主総会に先立って書面で反対の意思を会社に通知し、総会で反対の議決権行使を行う ・株主総会に実際に出席し、反対の議決権行使を行う ・議決権行使書面や電子投票による反対 |
Step2:会社からの通知・公告を確認する
会社法に基づき、会社は合併や事業譲渡、定款変更といった重要な決定を行う場合、原則としてその効力発生日の20日前までに、株主へ通知または公告を行わなければなりません。新設合併等においては株主総会の決議の日から2週間以内とされています。
この通知は株主総会前に行うことも認められており、株主総会の招集通知に株式買取請求権の発生原因となる行為について記載されている場合には、その招集通知は株主に対する通知となります。
Step3:会社に対して株式の買取を請求する
株主総会における反対の意思表示を終えたら、次に会社に対して正式に株式の買取を請求します。
株主は、合併等の効力が生じる20日前から効力発生日の前日までの間に、会社に対し、株式買取請求権を行使する必要があります。株式買取請求を行使する際には、口頭ではなく書面により行うことが、事後の紛争を回避することにつながります。書面には、株式買取請求を行使することを明記するとともに、対象となる株式の数、株式の種類や種類ごとの数を明記します。
また、株券発行会社であれば株券の提出が必要となります。
Step4:会社と買取価格について協議する
株式買取請求を行使することで株式の売買契約は成立します。その株式の買取価格は「公正な価格」とされますが、会社側から提示される金額がこの公正な価格とは限りません。そこで、株式買取請求を行使した株主は、買取価格について会社と協議を行います。協議の方法は、法律上特段のルールはないため、会社側と必ず面談しなければならないわけでもなく、電話や書面を通じて協議することも可能です。
買取価格について合意できた場合には、会社は効力発生日から60日以内に買取代金の支払をしなければなりません。
しかし、多くのケースで会社側は、株主にとって不利な低い価格を提示してくる傾向が見られます。このような状況では、協議が不調に終わる可能性も十分に考えられます。効力発生日から30日以内に合意できないときは、株主又は株式会社の双方は、効力発生日から30日の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができます。
Step5:協議がまとまらない場合は裁判所に価格決定を申し立てる
会社との買取価格に関する協議が不調に終わった場合、最終的な解決手段として、裁判所に対して「株式価格決定の申立て」を行うことができます。
裁判所の手続きでは、裁判所が買取価格を決定するもの(非訟手続)ですが、反対株主と会社の双方は公正な価格を主張とその疏明を尽くすことになります。公正な価格を主張疏明をするために、公認会計士が作成する株価算定書を提出することも珍しくありません。裁判書の手続きにおいても話し合いによる解決が図られない場合には、裁判所が指定した鑑定人が株価を鑑定し、裁判所は、この公的な鑑定の内容を踏まえて価格の決定することが一般的です。
裁判所によって決定された価格は、会社と株主の双方を法的に拘束するものであり、この手続きを通じて最終的な買取価格が確定します。これにより、少数株主は自身の投下資本を適切に回収することが可能となります。
保有株式はいくらで売れる?買取価格の決まり方
株式買取請求における買取価格は、原則として株主と会社の協議によって決定されます。しかし、非上場株式の場合、市場価格のような客観的な指標がないため、協議がまとまらないことも少なくありません。そのような場合、買取価格には「公正な価格」が求められます。
以下では、この公正な価格の内容や計算方法を解説します。
買取価格の基本原則は「公正な価格」
株式買取請求において、会社法では買取価格が「公正な価格」でなければならないと明確に定められています。この「公正な価格」とは、M&Aや事業譲渡、株式併合といった会社の組織再編行為が仮に行われなかったとした場合に、その株式が本来有していたであろう客観的な価値(ナカリセバ価格)を指します。他方で、組織再編によりシナジー効果が生じている場合には、シナジーを踏まえた価格が公正な価格となります。
価格の算定基準日は反対株主が株式買取請求をした時点となります。
非上場株式の株価を算定する主な方法
市場に取引価格が存在しない非上場株式の価値を算定する際には、会社の事業内容や財務状況に応じた多角的なアプローチが求められます。一般的に、株価算定には以下の3つの主要なアプローチが用いられます。
裁判所が株式の買取価格を決定する際には、以下のいずれか一つの評価方法に限定されることはありません。会社の規模や事業特性、将来性などの状況を総合的に考慮し、複数のアプローチを併用したり、それぞれの評価結果を調整したりすることで、「公正な価格」が判断されます。
インカム・アプローチ
将来得られる収益やキャッシュフローに着目して評価する方法です。具体的な手法としては、将来のフリーキャッシュフローを適切な割引率で現在価値に換算する「DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)」や、将来受け取る配当金額から株式価値を算定する「配当還元方式」などがあります。
会社の収益性や成長性が評価に強く反映される点に特徴があり、インカムアプローチを中心に株価算定されることが一般的です。
マーケット・アプローチ
マーケット・アプローチは、資産の市場性に着眼して株価を計算する方法です。評価対象企業自体の株式の市場価格や過去の取引価格を基に計算する方法や、類似する上場企業の株価等をベースに一定の倍率を算定した上で、その倍率を評価対象企業の経営指標に掛けることで株価を算出する方法(マルチプル法)が挙げられます。
コスト・アプローチ
会社の保有する資産や負債を基に評価する方法です。最も一般的なのは「純資産価額方式」で、会社の総資産から負債を差し引いた純資産額を基準に株価を評価します。この場合、資産や負債は帳簿価額ではなく、時価(相続税評価額など)に引き直して評価されるのが一般的です。
少数株主にとって不利な価格調整はされないのが原則
会社側が株式の買取価格交渉において、少数株主であることを理由に「マイノリティ・ディスカウント」を主張する場合があります。これは、保有株式が少数であり、経営への影響力がないことなどを理由に、算定された株価から一定割合を減額するものです。
しかし、これまでの裁判例を見ると、M&Aなど会社の都合で株式を手放すことになった少数株主を保護するという株式買取請求権の趣旨に基づき、マイノリティ・ディスカウントは原則として認められない傾向にあります。単に少数株主であるという理由で価格が減額されることは、権利行使の機会を保障する会社法の趣旨に反すると判断されるためです。
株式買取請求を成功させるための注意点
少数株主にとって、株式買取請求権は、会社経営の意思決定に納得できない場合に保有株式を現金化できる重要な権利です。しかし、この権利を適切に行使し、公正な価格での買取を実現するためには、会社法に定められた法的な手続きを正確に踏むことが不可欠です。
株式買取請求を成功させるためには、特に以下の3つの重要なポイントを押さえることが鍵です。これらの点を疎かにすると、不利な状況に陥りかねません。
手続きの期限は厳守する
株式買取請求権の行使においては、会社法で定められた厳格な期限を遵守することが極めて重要です。各手続きには期間が設けられており、わずか1日でもこの期限を過ぎてしまうと、権利が失われるリスクに直面します。
以下に、主な手続きとその期限をまとめます。
| 手続き名 | 期限 | 備考 |
| 反対の意思表示 | 会社からの通知確認後、株主総会前まで、または株主総会当日 | 会社へ反対を通知するか、総会で表明します。 |
| 株式買取請求 | 組織再編の効力発生日の20日前から前日まで | 具体的な株式買取を請求する期間です。 |
| 価格決定の申立て | 会社との協議期間満了後30日以内 | 会社との価格協議が合意に至らない場合に行います。 |
これらの期限を厳守できなければ、会社の決定に従わざるを得なくなるか、著しく不利な条件で株式を売却せざるを得なくなる可能性があります。そのため、会社から送付される通知書の内容を注意深く確認し、弁護士などの専門家と相談しながら、計画的にスケジュールを管理していくことが不可欠です。
反対の意思表示は正確に行う
株式買取請求権を行使するためには、会社法が定める手続きに則り、明確かつ正確に「反対」の意思表示を行うことが重要です。この意思表示が不正確であったり、手続きに不備があったりすると、せっかくの権利を行使できなくなる可能性があります。
特に、株主総会の場で議案に反対票を投じる際は、単に投票するだけでなく、議事録に残るよう「第〇号議案に反対します」といった形で、明確に反対の旨を発言することが重要です。これにより、後日「反対の意思が不明確だった」といった会社の主張を防ぐことができます。
事前に会社へ反対の意思を通知する場合、その通知は必ず記録が残る方法で行うべきです。議決権行使書面を用いるケースもありますが、実務上は、内容証明郵便を利用するのが一般的でしょう。これにより、会社側が「通知を受け取っていない」と主張するようなトラブルを防止できます。書面には、反対する議案、株主名、所有株式数などを正確に記載することも忘れてはなりません。これらの正確な手続きが、公正な価格での買取実現につながります。
交渉や手続きの記録は必ず残す
会社との交渉や手続きに関する記録は、将来的なトラブル、特に裁判に備えるための重要な証拠となるため、すべての記録を保管することが不可欠です。民事裁判においては、相手に無断で録音した会話であっても、原則として証拠能力が認められる傾向にあることは、覚えておくと良いでしょう。ただし、著しく反社会的な手段を用いた録音は例外となる可能性があります。
具体的には、以下のような記録を詳細に残しておくことが望ましいです。
- 会社からの通知書やメールの文面
- 電話での会話内容(日時、相手、要点を含むメモ)
- 交渉時の議事録
特に電話や直接のやり取りは、後日、「言った・言わない」の争いになりやすいため、録音や議事録作成を検討することも有効です。録音データは発言者や内容が判別できる音質で残し、必要に応じて文字起こしすることも推奨されます。これらの記録は、弁護士などの専門家に相談する際に、これまでの経緯を正確に伝え、的確なアドバイスを得るためにも大いに役立ちます。
少数株主の買取請求は難波みなみ法律事務所へ
株式買取請求の手続きは、会社法に関する専門知識が不可欠な上、厳格な期限管理も求められるため、個人で進めるには非常に複雑で難しいケースが少なくありません。特に、非上場株式の適正な買取価格を自ら算定することは容易ではなく、会社側が提示する価格が「公正な価格」であるか判断に迷うこともあるでしょう。また、会社側と対等に交渉を進めるためには、法的な知識や交渉経験が必要となり、精神的な負担も大きいものです。
このような複雑な手続きや交渉の課題に直面した際は、弁護士などの専門家へ相談することが有効な選択肢となります。弁護士は会社法に関する深い知識と経験を有しており、株主の代理人として、公正な買取価格の算定支援や、会社との交渉を有利に進めるための助言を提供します。これにより、株主は自身の正当な権利を主張し、大切な資産を適正な価格で現金化できる可能性が高まります。