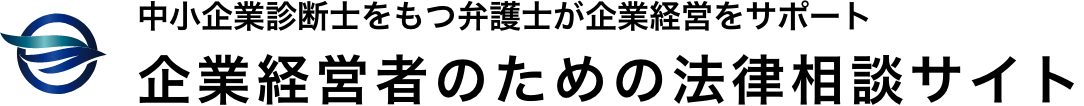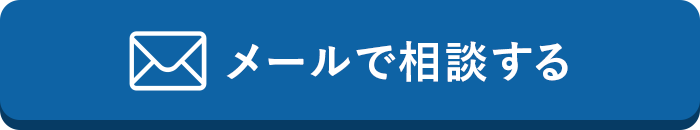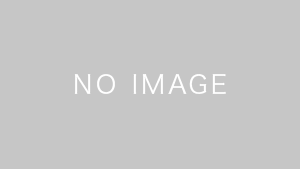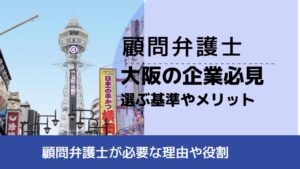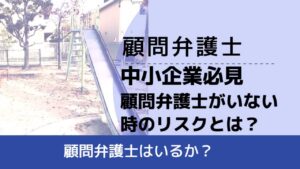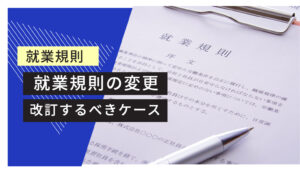退職時に従業員に誓約書を書いてもらうことがあります。
企業側にとって、企業独自のノウハウや顧客情報を守るために、退職時の誓約書は重要な役割を果たします。しかし、その内容や運用方法によっては、法的効力が認められないケースも存在します。
本記事では、退職時に交わされる誓約書について、企業が知っておくべき法的効力や適切な運用方法を解説します。ぜひ参考にしてください。
なぜ退職時に誓約書が必要なのか?企業の資産を守る重要性
従業員の退職は、企業にとって避けられない事柄である一方で、適切なリスク管理を求められる重要な局面でもあります。
退職に伴い、企業が長年培ってきた無形の資産が外部へ流出したり、競合他社に悪用されたりするリスクに直面する可能性があるからです。
この企業の資産には、物理的な資産だけでなく、企業独自のノウハウや技術情報、顧客リスト、営業戦略、優秀な人材に関する情報など、企業の競争力の源泉となる多岐にわたるものが含まれます。
これらの重要な資産は、従業員が在職中に業務を通じて取得したり、深く関与したりするものです。もし退職時に何ら制限を設けなければ、以下のような具体的なリスクが生じる可能性があります。
誓約書を作成しない時のリスク
- 顧客情報や営業秘密等の機密情報の流出
- 顧客や優秀な人材の引き抜き
- 競業行為によるノウハウの悪用
退職時に従業員と誓約書を交わすことは、これらのリスクを未然に防ぎ、企業の知的財産や営業秘密等の機密情報、そしてブランドイメージといった無形の資産を保護するための極めて重要な契約です。これにより、企業の持続的な成長と健全な事業運営を守る基盤が確立されます。
退職時に交わす誓約書の目的と法的効力の基礎知識
退職時に従業員と交わす誓約書は、企業にとって単なる形式的な書類ではありません。
以下の項目では、企業が誓約書に何を盛り込み、どのような法的効力を持たせることを意図しているのか、その基礎知識を詳しく解説していきます。
会社の機密情報やノウハウの流出を防ぐ
企業にとって、長年にわたり培ってきた顧客情報、技術情報、営業ノウハウは、競争力の源泉です。これらが退職者を通じて競合他社へ流出すれば、売上低下や市場での競争優位性の喪失といった、深刻な経営上のリスクに直面する可能性があります。
退職時に秘密保持に関する誓約書を取り交わすことは、退職者に対し、退職後も守秘義務を負うことを書面で明確に認識させ、安易な情報漏洩を防ぐ心理的な抑止力となります。万が一、機密情報やノウハウが不正に利用された場合、誓約書は契約違反を追及する法的な根拠となり、情報漏洩に対し、差し止め請求や損害賠償請求といった対抗措置を取る上で不可欠です。
さらに、不正競争防止法で保護される「営業秘密」に該当せず、形式知化されていないノウハウや情報などであっても、誓約書を締結することでこれを保護対象とすることが可能です。これにより、企業独自の幅広い資産を守り、将来的なトラブルを未然に防ぐ重要な手段となります。ただし、秘密保持義務の対象となる情報については、抽象的に定めるのではなく、具体的に特定することが求められます。
顧客や優秀な人材の引き抜きを防止する
企業にとって、顧客情報や顧客との関係性は、企業にとって重要な資産です。もし退職者が顧客情報等を利用し、企業の重要な顧客を引き抜くような事態が生じれば、企業の売上や事業基盤に深刻な影響を与えかねません。
また、顧客だけでなく、企業の中核を担う優秀な従業員が引き抜かれることも大きな損失です。経験豊富な人材の流出は、事業体制の機能不全を招き、長年培ってきたノウハウの外部流出も助長し、結果として企業の競争力を著しく低下させる要因となり得ます。
これらのリスクを未然に防ぐため、退職時の誓約書に引き抜き防止条項を設けることが有効です。
退職後のトラブルを未然に回避する
退職時に交わす誓約書は、退職後のトラブルを未然に回避する上で重要な役割を果たします。書面によって退職後の義務やルールが明確になることで、企業と退職者の間で生じがちな「言った言わない」といった認識の齟齬を防ぎ、双方の合意形成を明確にする効果が期待できます。
退職者が誓約書に署名する行為は、単なる形式的な手続きではありません。それは、退職後のルールを認識させ、「約束を破ってはならない」という強い心理的な抑止力として機能します。その結果、安直なルール違反が未然に防がれる効果も期待できるでしょう。
誓約書の法的拘束力はどこまで認められるか
誓約書は、署名・捺印があれば、原則として当事者間を法的に拘束する合意文書となります。そのため、退職者との間でトラブルが生じた際には、契約内容を証明する重要な証拠として裁判で活用されることがあります。
しかし、その内容が労働者の職業選択の自由を不当に制限したり、公序良俗に反すると判断されたりする場合には、その条項が無効となる可能性があります。特に、秘密保持義務や競業避止義務などの退職後の行動を制限する条項は、慎重に判断される傾向にあります。
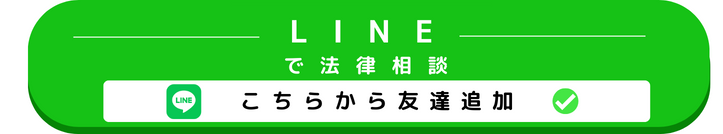

【要注意】法的に無効にならないための誓約書作成ポイント
退職時に企業が交わす誓約書は、企業の重要な資産を守るために重要な文書です。しかし、その内容が合理的でなければ、法的に無効と判断されてしまうリスクが伴います。
以降の項目では、法的に有効な条項を作成するための具体的な注意点を解説していきます。
競業避止義務|職業選択の自由を侵害しない範囲設定とは
退職時に課される競業避止義務は、憲法で保障された「職業選択の自由」を制限する側面があるため、無制限に競業避止義務を課すことはできません。
裁判所は、企業が守ろうとする利益(営業秘密や顧客情報など)と、退職者が被る職業選択上の不利益とのバランスを総合的に考慮して判断します。退職者の自由を不当に制限する内容であれば、その義務は無効と判断されるリスクがあるため注意が必要です。
競業避止義務の規定を設けるにあたっては以下の要素に考慮しなければなりません。
例えば、何らの役職もない平社員に対して、広い範囲の競業避止義務を課すことは、退職者の不利益が大きすぎるため無効となる可能性は高いでしょう。他方で、営業秘密に接していた役職者に対して、1年間に限り大阪府内で退職者が担当していた取引先への営業行為を禁じるといった場合には、有効となる可能性があります。
秘密保持義務|対象となる「秘密」の範囲を具体的に明記する
退職時の誓約書に秘密保持義務を定める際、その対象となる情報の範囲を明確に規定することは非常に重要です。
例えば、「会社の全ての情報」といった包括的で曖昧な表現では、従業員が具体的に何を漏洩してはならないのか理解しづらくなります。このような不明確な定義は、いざという時にその条項が無効と判断されるリスクがあるため、注意しなければなりません。過去の裁判例でも、秘密情報の「定義」が有効性の重要な要素とされています。
法的に有効な秘密保持義務とするためには、保護したい情報の範囲を具体的に列挙することが不可欠です。例えば、顧客リスト、原価情報、技術ノウハウ、未公開の事業計画、人事評価データなど、企業の競争優位性に関わる具体的な情報を明記すべきでしょう。
営業秘密とは
不正競争防止法における「営業秘密」として保護されるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
ただ、営業秘密については不正競争防止法により保護されているものの、営業秘密の漏洩を防止するためにも、対象となる営業秘密を具体的に特定することが重要です。
貸与品の返還義務|PC・スマホ等の返却を確実に約束させる
退職時には、従業員に貸与していた企業資産を確実に返還させることが重要です。具体的には、以下の貸与品が挙げられます。
貸与品の一覧
- PC
- スマートフォン
- 社員証
- 鍵
- セキュリティカード
- 業務関連書類
これらの貸与品が未返還のまま放置されると、企業の財産が失われるだけでなく、内部に保存された会社情報や顧客データが外部に流出し、情報漏洩のリスクを高める可能性があります。誓約書では、こうした貸与品のリストを具体的に明記し、従業員が「聞いていない」と主張する事態を防ぐことが求められます。
誹謗中傷の禁止|SNS時代に必須の項目
SNSや口コミサイトの普及に伴い、退職者による安易な書き込みが企業の評判に深刻なダメージを与えるリスクが高まっています。これは企業の信用や企業価値の低下だけでなく、採用活動への大きな打撃、売上・業績の悪化、既存社員のモチベーション低下など、多岐にわたる深刻なリスクを招く可能性があります。投稿内容の真偽に関わらずネガティブな情報が広がり、風評被害につながるケースも少なくありません。
このようなリスクを回避するためには、退職時の誓約書に「誹謗中傷の禁止」条項を明確に盛り込むことが重要です。単に「悪口を言わない」といった抽象的な表現ではなく、企業の社会的評価を不当に貶める行為を明確に禁止対象として定義することが不可欠です。
損害賠償・違約金|不当に高額な設定は無効のリスク
誓約書に違反した場合、企業が被った実損害については、退職者に対し損害賠償を請求できます。
ただ、秘密保持契約により、退職者に対して競業避止義務や秘密保持義務を負わせるだけでなく、それに対するペナルティが明記しておくことで、これら義務の遵守を期待することができます。
しかし、違約金が高ければ高いほど、退職者に対する心理的なプレッシャーが大きくなりますが、あまりにも高額な違約金や損害賠償の予約は公序良俗に違反して無効になります。
なお、労働基準法16条は「使用者は,労働契約の不履行について違約金を定め,又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めているため、違約金や損害賠償の予定に関する規定は、労基法16条に反すると考える見解もあります。
退職者から署名を拒否された際の適切な対応フロー
退職時に従業員が誓約書への署名を拒否するケースは少なくありません。以下の項目では、署名を拒否された際に企業が取るべき具体的な対応フローを解説します。
まずは従業員が懸念する点をヒアリングする
従業員が退職時に誓約書への署名を拒否する場合、そこには必ず何らかの理由があります。例えば、ハラスメントや労働条件の悪化による会社への不信感、また、競業避止義務など退職後の行動を過度に制限する特定の条項に対する不満などが考えられます。企業としては、まずこれらの具体的な理由を正確に把握することが重要です。
署名を拒む従業員に対し、なぜ署名したくないのか、具体的にどの条項に懸念や不安を感じているのかを詰問するような態度ではなく、冷静かつ丁寧に聞き出す姿勢が不可欠です。高圧的な態度や一方的な説得は、かえって従業員の態度を硬化させたり、別のハラスメントになるなど、不要なトラブルを招きます。
誓約書の内容が妥当であることを丁寧に説明する
従業員からの懸念点をヒアリングした後は、企業として誓約書を求める背景と、その内容が法的に妥当であることを丁寧に説明することが重要です。
誓約書は、企業が長年培ってきた機密情報や知的財産といった正当な利益を守るために不可欠なものであり、退職者の今後のキャリアを違法不当に縛るものではないことを真摯に伝える必要があります。
退職者が特に懸念している条項については、なぜその規定が必要なのかという企業の視点を具体的な事例を交えて説明し、一方的な要求ではないことへの理解を求めることが肝要です。この際、高圧的な態度を避け、あくまで対話を通じて疑問点を解消しようとする姿勢を見せることが大切です。
必要に応じて内容の修正・譲歩を検討する
従業員が誓約書への署名を拒否する理由が合理的であると判断された場合、企業は一方的に要求を突き放すのではなく、柔軟な対応を検討することが重要です。
修正内容に合意した際は、必ず新たな誓約書を作成し、変更点を明確に記載した上で再提示してください。口頭での約束は後のトラブルの原因となるため、書面で最終的な合意内容を残すことが極めて重要です。
企業としては、事業運営上、絶対に譲れない一線、例えば中核となる機密情報の漏洩防止などは維持しつつ、柔軟な譲歩案を事前に検討しておくことが求められます。
署名が任意であることを伝え、強要は避ける
退職時に企業から誓約書の提示があったとしても、その署名は法的に強制されるものではなく、あくまで退職者本人の任意であることを明確に伝えることが重要です。誓約書への署名を拒否された際に執拗に署名を求めることは、民法第96条1項に定められる「強迫による意思表示」と判断されるリスクを伴います。
さらに、「署名しなければ退職を認めない」「退職金を支払わない」といった発言は、従業員に対するパワハラと受け取られかねず、新たな労務トラブルに発展する可能性を秘めています。このような行為は、企業の信頼を著しく損ない、社会的な評価を低下させる要因にもなりかねません。
誓約書への署名をもらえなかったとしても、多くの場合、就業規則や入社時に締結された雇用契約の中に、秘密保持義務や貸与品の返還義務に関する規定がすでに盛り込まれています。これにより、たとえ誓約書に署名がなくても、従業員には一定の義務が残ります。強要によって関係を悪化させるよりも、円満な退職を目指し、対話と理解を通じて合意形成を図ることが、企業にとって最善の策となるでしょう。
もし誓約書の内容が破られたら?企業が取るべき法的措置
退職時に交わした誓約書の内容が、万が一退職者によって破られた場合、企業としては冷静かつ段階的に対応を進めることが重要です。
以下では、誓約書違反が発覚した際に企業が取るべき具体的な対応フローを解説します。警告から最終的な法的措置に至るまでの流れ、そして弁護士などの専門家へ相談することの重要性についても述べます。
違反行為の証拠を収集・確保する
誓約書の内容が破られた場合、その追及には憶測ではなく客観的な証拠の収集が不可欠です。具体的な証拠がなければ、その後の法的措置は困難となるため、迅速かつ正確な情報収集が求められます。
元従業員が使用していたパソコンのログやメール送受信履歴といったデジタルデータも、違反行為を裏付ける重要な証拠となり得ます。これらのデジタルデータの保全・調査(デジタルフォレンジック)も検討すべきです。ただし、証拠収集の際は、不正アクセスやプライバシー侵害などの違法な手段を用いないよう、細心の注意を払いましょう。
内容証明郵便で警告・是正を求める
退職者が誓約書の内容に違反していると確認できた場合、企業がまず取るべき対応として、内容証明郵便の送付は非常に有効です。
内容証明郵便は、企業が違反行為に対して毅然と対応をしているという明確な意思を示すこととなり、相手方に心理的な圧力を与える効果も期待できます。また、裁判になった際には、企業が適切な対応を取っていたことを示す証拠にもなります。
差止請求や損害賠償請求を検討する
内容証明郵便による警告にもかかわらず、退職者による誓約書違反が是正されない場合、企業は裁判所を通じた法的措置を検討する必要があります。主な措置として、差止請求と損害賠償請求が挙げられます。
差止請求は、競業行為や秘密情報の不正利用といった違反行為が現に行われている際に、その行為の停止を求める手続きです。緊急を要するケースでは、民事保全法23条2項に基づく「仮の地位を定める仮処分命令」の申し立てが有効とされます。これにより、本訴訟を待たずに迅速に違反行為の停止を命じてもらうことが可能になります。
損害賠償請求は、違反行為によって企業が被った具体的な損害を金銭的に補填することを求める手続きです。これには、企業が本来得られたはずの利益である「逸失利益」や、信用低下による損害などが含まれます。
いずれの手続きも専門的な知識や経験が求められるため、自己判断だけで進めるのではなく、専門家である弁護士に相談して計画的に対応していくのが大切です。
誓約書に関する弁護士への相談メリット
誓約書が無効となるリスクを回避し、法的有効性を確保するためには、弁護士の専門的な知見が欠かせません。
弁護士に相談や依頼する具体的なメリットを、以下の項目で詳しく解説します。
実態に即した有効な誓約書の作成サポート
インターネット上には誓約書のテンプレートが多数存在しますが、これらを安易に流用することはリスクを伴います。テンプレートの内容が、抽象的な内容に留まっていたり、具体的な資産の実態に合致していないなどの問題を含んでいることも多いため、誓約書が無効となったり、目的を達成できないリスクがあります。
そこで、弁護士に誓約書の作成を依頼することで、これらのリスクを回避できます。弁護士は企業の事業内容を詳細にヒアリングし、競業避止義務の期間や範囲、秘密情報の定義などを、その事業内容に合わせて個別に最適化(カスタマイズ)します。
退職者との交渉やトラブル発生時の代理対応
感情的になりがちな退職者との交渉は、企業担当者にとって大きな負担となることがあります。特に、誓約書への署名拒否や内容の修正要求など、感情的な対立が生じやすい場面では、冷静かつ法的な視点での対応が不可欠です。弁護士が交渉を代理することで、こうした難しい状況に客観的に対処し、企業側の主張を法的に裏付けながら、円滑な合意形成を進められます。
また、万が一、退職者が誓約書の内容に違反した場合でも、弁護士は迅速かつ適切な法的措置を講じることが可能です。
これら一連の法的な手続きを、弁護士が専門的な知識と経験に基づいて効率的に進めます。これにより、企業担当者は精神的・時間的な負担から解放され、本来の業務に集中できます。また、弁護士が代理人として関与すれば、相手方への強い牽制となり、トラブルの深刻化を防ぐだけでなく、企業にとって有利な条件での和解に繋がる可能性も高まります。
誓約書の作成は難波みなみ法律事務所へ
本記事では、退職時に企業が従業員と交わす誓約書について、その重要性、法的な有効性を確保するためのポイント、そして署名拒否や違反といったトラブルへの対応フローを解説しました。
企業が長年培ってきた機密情報、独自のノウハウ、顧客データ、そして優秀な人材は、競争力を支える重要な無形資産です。退職時の誓約書は、これらの資産が外部へ流出したり、競合他社に悪用されたりするリスクから、企業の利益を守るための重要な防衛策として機能します。
誓約書の作成や誓約書の違反行為については、専門的な知識と経験が求められるため、無計画に進めていくことは厳禁です。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。