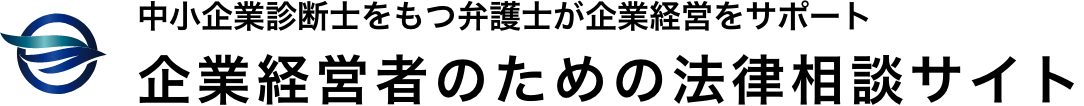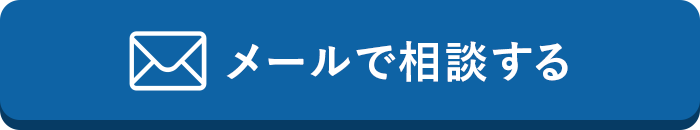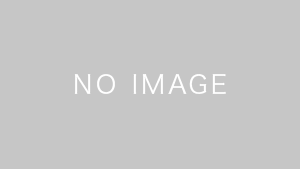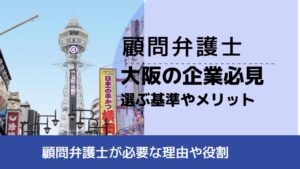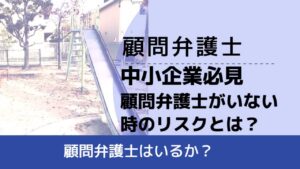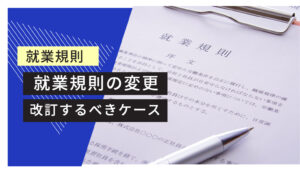従業員を懲戒解雇した場合、当然に退職金は支払わなくても問題ないと思っていませんか。
しかし、懲戒解雇=退職金不支給ではありません。退職金は、退職後の生活を支える労働者の賃金であり、重要な権利の一つです。それにもかかわらず、懲戒解雇した一事をもって退職金の全部または一部を不支給にできると、労働者が深刻な不利益を受けます。
そこで、退職金の全部または一部を不支給にできる場合とは、長年の功労を抹消できるような重大な背信行為がなければ認められません。
本記事では、解雇をした社員の退職金の問題を中心に解説します。
解雇をした社員にも退職金を払う必要がある
社員を解雇したとしても、企業はその社員に対して原則として退職金を支払う義務を負います。
常に退職金を支払う必要があるわけではありません。
まず、就業規則や労働契約書等に退職金の規定があることが必要です。また、長年の功労を消すような重大な事情がある場合に限り、退職金の不支給または減額とすることは認められます。しかし、このような事情がないにもかかわらず、単に解雇をしたことのみを理由に退職金を不支給とすることはできません。

退職金請求を受けた時の注意点
解雇をした社員から退職金の請求を受けた時、まずは次の点を確認した上で、退職金の請求に応じるべきか検討しなければなりません。
| ✓チェックポイント ・退職金規定があるか ・退職金を不支給または減額する規定があるか ・社員の問題行為が不支給・減額とするべき理由になるのか |
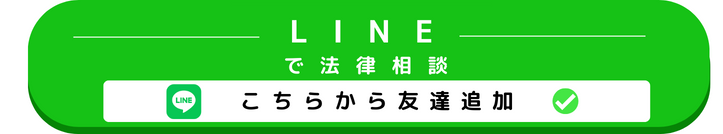
退職金規定があるか
社員が退職金の請求をするためには、労働者に対して退職金が権利として与えられていることが必要です。
退職金が権利として認められるためには、次に挙げる書類に退職金の規定が具体的に定められていることが必要です。
就業規則で定められている
就業規則で退職金の内容が定められている場合です。
ただ、退職金が権利として認められるためには、退職金の具体的な計算方法が規定されていることが必要です。単に、会社の業績に連動して退職金を支払うといった程度の内容であれば十分とは言えません。
雇用契約書に定められている
就業規則や退職金規定がなくても、雇用契約書や労働条件通知書等に退職金の具体的な定めがあれば、退職金の請求が認められます。
就業規則や退職金規定がないからといって安易に労働者の退職金請求を拒否するべきではありません。
雇用契約書等を再確認して、退職金の定めの有無をチェックしましょう。
退職金を支払う労使慣行がある場合
就業規則や雇用契約書のいずれにも退職金規定がなくても、退職金を支払う労使慣行がある場合には退職金の請求は認められます。
通常、就業規則と雇用契約書のいずれにも退職金の定めがなければ退職金の請求は認められません。しかし、会社が退職金の基準を定めており、この基準に基づいて退職金の支払いが繰り返し行われている場合には、労使慣行として退職金の請求が権利として認められる可能性があります。
退職金を不支給減額できる条件
退職金規定があるからといって、常に満額の退職金を支払う必要はありません。
次の条件に当てはまる場合には退職金を不支給としたり、減額させることができます。
| ① 退職金を退職金を不支給減額できる規定があること ② 労働者に退職金を不支給減額とするだけの非違行為があること |
不支給や減額の規定があること
解雇の際に退職金の全部または一部を不支給とするためには、退職金規定に不支給の定めがあることが必要です。
なぜなら、退職金は賃金の後払いとしての役割に加えて退職後の生活の糧になるものです。それにもかかわらず、何の根拠規定もなく退職金を減額されると、労働者は大きな不利益を受けてしまいます。
そのため、退職金の全部または一部を不支給とするためには、あらかじめ退職金規定等に不支給とする具体的な定めを設けておくことが必要です。
解雇に限定せずに規定する
退職金の不支給・減額規定が懲戒解雇をした時に限定していると、懲戒解雇せずに離職した場合には退職金を不支給としたり、減額させることができません。
例えば、懲戒解雇せずに労働者が退職した後に、労働者の問題行為が発覚することがあります。その場合、既に労働者は離職している以上、退職後に懲戒解雇とすることができません。それにもかかわらず、退職金規定の不支給条項が懲戒解雇を条件としていると、たとえ懲戒解雇に匹敵する問題行為があっても、退職金を減額・不支給とすることはできません。
そのため、退職金規定には、懲戒解雇だけでなく、懲戒解雇にあたる事由がある場合には、退職金を支給しない、または、減額するといった定めにしておくことが必要です。
| (退職金の不支給等) 1 社員が第3項に定める各号に該当する場合、使用者は退職金の全部又は一部を支給しないことがある。 2 使用者が退職した社員に対して、退職金が支給された後に、第3項2号に該当する事由が発覚した場合、使用者は社員に対して退職金の全部又は一部の返還を求めることができる。 3①懲戒解雇されたとき ②在職中に懲戒解雇事由に相当する行為があったとき |
退職金を減額できる程の悪質な事情があること
懲戒解雇をしたり、懲戒解雇にあたる事由があれば、当然に退職金の全部または一部を減額できるわけではありません。使用者に対する長年の功労を抹消できる程の著しい背信行為があることが必要です。
退職金は、賃金の後払いとしての役割に加えて、使用者に対する功労に報いる機能を果たしています。
そのため、それ程深刻ではない理由で退職金を減額、不支給とすることができてしまうと、労働者には思いがけない不利益が生じてしまいます。
そこで、退職金の機能を踏まえてもなお、退職金を減額不支給しなければならない程に悪質な理由があることが必要です。
最高裁の判例の言い方では、これまでの勤続の功労を抹消したり、減少させるような著しい背信行為がある場合に限り、退職金の全部または一部を不支給とすることが認められています。
懲戒解雇をした場合の全部又は一部の不支給
懲戒解雇が有効であれば、退職金の一部または全額の不支給が認められることがほとんどです。逆に、懲戒解雇にできるだけの十分な理由がなければ、退職金の不支給も認められない可能性が高いでしょう。
全額不支給とする場合
退職金の全額を不支給にすることができる場合とは、社員の問題行為により会社に重大な問題・損失が発生していることが必要です。
例えば、会社の財産を横領したり、会社の顧客の奪取や営業機密の持ち出しにより損失を生じさせた場合には、全額不支給とすることも認められる可能性があります。
| 事件名 | 内容 |
| 東京メデカルサービス・大幸商事事件(東京地裁平成3年4月8日) | 【利益相反取引】 勤務先の経理部長でありながら、許可を得ることなく、他の会社の代表取締役となり、勤務先に関連する取引をして利益をあげるということは、重大な義務違反行為であり懲戒解雇は有効であるから、退職金請求権は発生しない。 |
| 千代田事件(東京地裁 平成19年5月30日) | 【横領と偽造】 会社の売上金を横領した上で、証拠隠滅のために伝票を偽造するなどした社員を懲戒解雇とした上で、非違行為の悪質性の高さから、勤続の功を抹消してしまうほどのものではないとまでは言い切れないものというべきである。 |
| 日音事件(東京地裁平成18年1月25日) | 【競業他社への転職と機密情報の持ち出し】 会社を一斉に退社することでで本社営業部と新宿支店の機能を麻痺させたこと、無断で在庫商品を社外に運び出したり、パソコン内の顧客台帳・リース台帳等のデータをフロッピーに移記したうえこれを持ち出していた上で、これらデータを消去していること等を踏まえ、それまでの勤続の功を抹消してしまうほどの著しく信義に反する行為があったと認めるのが相当である。 |
一部不支給とする場合
他方で、退職金の全額を不支給にできるだけの重大な問題が生じていない場合には、全額不支給ではなく一部不支給とするべきでしょう。つまり、過去の労働に対する評価をすべて抹消できる場合でなければ、全額不支給は認められません。たとえば、私生活上の問題行為であり、会社の社会的な評価が悪化していない場合には、一部不支給に留めるべきでしょう。
| 小田急電鉄事件(東京高判平成15年12月11日) | 【私生活上の痴漢】 私生活上の痴漢であり会社の社会的評価は毀損されていないこと、20年余りの勤務態度が非常に真面目であったことを踏まえて、退職金の3割の限度で支払うべき。 |
| ヤマト運輸事件(東京地裁平成19年8月27日) | 【酒気帯び運転】 帰宅途中の酒気帯び運転であるところ、他に懲戒処分を受けた経歴がないこと,事故は起こしていないこと、反省の様子も看て取れないわけではないことから、退職金の3分の1は支払うべき。 |
| 日本郵便株式会社事件(東京高判平成25年7月18日) | 【私生活上の酒気帯び運転】 事故が業務外のものであること、酒気帯び運転に対しては罰金刑が科されたにすぎないこと、交通事故は物損事故であり、物損事故の被害者に対して損害賠償が支払われていること、勤務先に損害が発生したことを認めるに足りる証拠はないことから、退職金の3割の支払いを認めた。 |
普通解雇や整理解雇の場合は不支給にできない
懲戒解雇ではなく普通解雇や整理解雇の場合、退職金の不支給は認められないことが多いです。
普通解雇の場合
普通解雇は懲戒解雇と同様、雇用契約を一方的に終了させる処分である点で共通しています。
しかし、普通解雇は、能力不足や協調性欠如などの労働契約の債務不履行です。普通解雇は、懲戒解雇のような重大な非違行為まで無いことがほとんどです。そのため、退職金の不支給規定を適用することは難しいことが多いでしょう。
ただし、本来、懲戒解雇にすることができるケースで、社員に対する配慮等から普通解雇とすることがあります。その場合には、退職金の不支給も認められる場合があります。
整理解雇の場合
整理解雇は、経営上の理由により余剰労働者の人員整理をいいます。整理解雇は、会社側の事情により社員を解雇する場合ですから、社員側の責任は問われていません。
そのため、整理解雇の場合、退職金を不支給とすることはできないのが原則です。むしろ、整理解雇の場合、通常の退職金に上乗せした割増退職金が支給されることがあります。
退職後に懲戒事由が分かった場合
退職後に懲戒事由が判明した場合でも、退職金の全部または一部を不支給とすることができます。また、退職金を既に支払っている場合でも、その全部または一部の返還を求めることもできます。
ただし、あらかじめ退職金規定には、懲戒解雇だけでなく、懲戒解雇に当たる事情がある場合にも不支給とすること、退職金の支払後に返還を求めることができることを定めておくことが必
退職金制度の変更による退職金の減額
退職金制度の変更は、労働者から個別の同意を得る場合と就業規則を変更をする場合があります。
会社の経営不振等を理由に、退職金を減額させるような退職金制度の変更をすることがあります。退職金制度の変更内容としては、以下のものが挙げられます。
| ・算定基礎給の変更 ・算定方法の変更 ・支給率の変更 ・特別加算制度の変更 ・退職金制度の廃止 |
労働者の個別の同意
労働者が自由な意思により退職金の減額に同意した場合には、退職金の減額が認められます。
退職金の減額について、口頭の同意や同意書へのサインをもらえば、簡単に退職金の減額が認められるわけではありません。
退職金は、労働者にとって重要な権利であり、そな減額は労働者に対して重大な不利益をもたらします。
そのため、同意による退職金の減額は、労働者の自由な意思によることが必要であり、自由な意思による同意といえるためには、次の事情を踏まえて判断されます。
- 減額の幅が大きすぎないか
- 減額の理由がやむを得ないものか
- 会社から従業員に対して十分な説明をしたか
- 減額に対して何らかの手配をしているか
就業規則で退職金の計算式が定められている場合
就業規則で退職金の計算式が定められている場合、労働者から個別の同意を得ても、それが就業規則の内容を下回る内容であれば、同意は無効となります。つまり、
この場合には、後述する就業規則の変更が必要となります。
就業規則の変更による減額
就業規則を変更する場合、労働者の同意を得ることなく退職金の減額をすることができます。
就業規則の変更には労働者の同意が必要
就業規則を変更することで、労働条件を不利益に変更するためには、従業員全員の同意を得る必要があります。
| ✓労契法9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。 |
就業規則の変更に同意を得ていない場合
就業規則の不利益変更は、労働者全員の同意がなければできません。しかし、常に労働者の同意がなければ変更できないとするのも不都合です。
そこで、次の条件を満たす場合には、労働者の同意を得なくても、不利益変更を伴う就業規則の変更を行うことができます。
- 労働者の受ける不利益の程度が大きすぎないか
- 従業員が退職金の減額を受け入れざるを得ない程に高度な必要性があること
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合等との交渉の状況
- その他の就業規則の変更に係る事情
例えば、企業が倒産せざるを得ない程に経営不振に陥っており、高度の業務上の必要性があることを要します。単に収支が悪化している程度では、必要性は満たされないでしょう。
| 労契法10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。 |
自己都合離職か会社都合離職か
多くの企業では、自己都合離職と会社都合離職によって計算方法や算定割合を変えています。
厚生労働省の統計によれば、定年退職による離職の退職金が最も高額であり、次いで会社都合離職、自己都合離職と続きます。
| 定年退職 1872万円 会社都合 1197万円 自己都合 447万円 参照)中央労働委員会・令和3年賃金事情等総合調査 退職金、年金及び定年制事情調査 |
会社都合離職について
会社都合の離職とは、解雇や雇止め、会社の退職勧奨による退職を含めます。
解雇には懲戒解雇、普通解雇、整理解雇が含まれます。ただ、懲戒解雇の中でも、労働者側の責任が重大な場合の重責解雇は、自己都合離職となります。
自己都合の離職とは
自己都合の離職とは、自発的な意思で退職する場合や雇用期間の満了により労働契約が終わる場合を指します。退職勧奨により退職する場合は、会社都合離職となります。
退職金の減額の問題は弁護士に相談しよう
退職金の金額は、労働者の退職後の生活を支える非常に大事な権利です。その分、労働者の退職金に対する関心度もとても強いです。それにもかかわらず、安易に退職金制度を廃止したり、減額をしてしまうと、労働者の反発を招きます。
そのため、会社は、退職金の減額や廃止をするにあたっては、慎重な判断を求められます。勇み足で退職金の減額をすることは控えましょう。適切に弁護士に相談することが重要です。
初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。