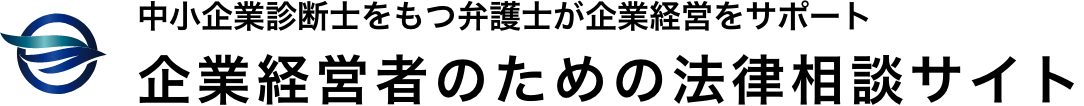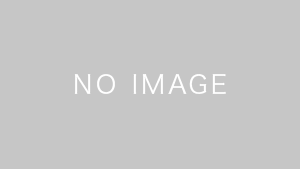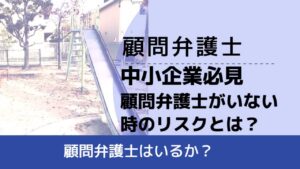社員のやる気の低下は、多くの企業が抱える共通の課題となっています。特に、解雇という手段は、経営者にとって最後の選択肢となりますが、法的リスクを伴うため慎重な判断が求められます。
本記事では、パフォーマンスが低い社員を改善するための具体的なステップと、解雇を検討する際に企業が注意すべき法的要件について詳しく解説します。不当解雇と判断されるリスクを回避し、適切な対応策を講じるために、ぜひ本記事をご一読ください。
「やる気のない社員」を放置する3つの経営リスク
「やる気のない社員」の影響は組織全体に波及し、深刻な経営リスクにつながる可能性があります。やる気のない社員を放置することは、周囲の社員のモチベーション低下を招き、ひいては真面目な社員の退職や組織全体の生産性低下といった問題を引き起こしかねません。
以下の項目では、やる気のない社員を放置することで企業が直面する具体的なリスクを詳しく解説していきます。
周囲の社員のモチベーションが低下し、職場全体の生産性が落ちる
やる気のない社員がいると、周囲の従業員に深刻な悪影響を与えます。ため息や不満の声、非協力的な態度が日常的に見られるようになると、真面目に働く社員は不公平感を感じやすくなり、停滞した雰囲気が職場全体に広がりがちです。
また、やる気のない社員が担当すべき業務を、他の社員がカバーせざるを得ない状況も頻繁に発生します。これにより、業務効率が低下するだけでなく、努力している社員の士気を著しく低下させてしまいます。
優秀な人材の離職につながる
低いパフォーマンスの社員が、真面目に努力する社員と同じ待遇を受けている場合、職場内で深刻な不公平感が生まれます。特に、評価基準が不明瞭な状況では不満が蓄積しやすくなります。このような環境では、社員は努力が報われないと感じ、仕事へのモチベーションを維持することが困難になるでしょう。
結果として、自身の能力を最大限に活かし、キャリアアップを目指したいと考える優秀な人材ほど、失望感を抱きやすくなり、より良い条件や成長機会を求め、転職を検討し始める傾向があります。
対外的な会社の信頼を損なう
やる気のない社員は、顧客対応の質を著しく低下させることになります。例えば、電話対応が横柄になったり、メールの返信が遅れたりといった不適切な対応は、顧客満足度を低下させる直接的な原因です。そのため、やる気のない社員による事務的・不親切な対応は不信感を生み、クレームの増加につながりかねません。
また、業務への責任感の欠如は、遅延やミスを引き起こし、納期遅延にもつながります。

やる気のない社員の特徴
「やる気のない社員」とは具体的にどのような行動や態度を示すのでしょうか。ここでは、客観的に判断できる具体的な行動特性をいくつかの観点からご紹介します。
仕事に無気力で消極的
意欲の低い社員は、常に受け身の姿勢をとる傾向があります。会議や打ち合わせの場でも、意見を求められても「特にありません」と回答することが多く、発言を控える傾向が見られます。
また、業務改善や効率化に対する意識も低く、現状のやり方をただ繰り返すだけで、より良くしようという意欲が見られない点も特徴です。
目標達成への意欲も感じられず、表情や態度からは覇気がなく、職場全体の雰囲気に悪影響を与える可能性も指摘されています。
指示されたことしかしない
やる気のない社員は、上司や同僚からの明確な指示がなければ行動を起こせない、主体性に欠ける人材です。与えられたタスクは最低限こなすものの、自発的に仕事を見つけたり、業務改善の工夫をしたりすることはほとんどありません。
このような社員は、自発的な行動に欠け、指示された範囲内でしか動かないため、自身のスキルアップにも関心は薄い傾向にあります。最小限の労力で職務を全うしようとするため、追加の業務や同僚に対する手助けを避ける傾向もあります。
仕事への責任感がない
仕事への責任感に欠ける社員は、業務上のミスや問題が発生した際、自身の非を認めず、他人や環境に原因を転嫁する他責思考に陥りがちです。そうした社員は、業務遂行における基本的な責任を十分に果たさないことがあります。具体的には、以下の行動が見られます。
- 納期や約束を守らない
- 報告・連絡・相談(報・連・相)を怠る
また、トラブルが発生した際も、自ら解決しようとせず、すぐに諦めて業務を投げ出したり、周囲に丸投げしたりする傾向が見られます。このような態度は、周囲の従業員の負担を増やし、組織全体の協力体制を著しく阻害する要因となります。
会社や上司への批判ばかりする
やる気のない社員は、会社や上司の不満や愚痴を繰り返す傾向があります。自身の成果が出ない原因を会社の方針や上司のマネジメントといった外部要因に求める傾向があります。
こうしたネガティブな言動は、周囲の社員に不満を伝染させ、職場全体の士気を著しく低下させるおそれがあります。
「やる気がない」という理由だけで社員を解雇するのは違法
「やる気がない」といった主観的で抽象的な理由のみで社員を解雇することは不当解雇と判断される可能性が高いといえます。以下では、やる気のない社員を解雇するための条件を説明します。
「解雇権濫用法理」とは
「解雇権濫用法理」とは、会社が従業員を解雇する権利(解雇権)の濫用を制限するための法的なルールです。解雇は、労働者の生活基盤を奪う重大な処分であるため、労働契約法では労働者を手厚く保護しています。
労働契約法16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
この条文が示す通り、解雇が法的に有効と認められるためには、「客観的に合理的な理由」が存在し、かつ「社会通念上相当」であるという、非常に厳しい2つの要件をクリアする必要があります。
会社側の都合や主観的な判断だけで、一方的に従業員を解雇することはできないという原則が明確に定められているのです。
| 要件 | 説明 |
| 客観的に合理的な理由 | 解雇の原因となる事柄が、客観的な事実に基づいていること。 |
| 社会通念上相当 | その解雇が社会一般の常識に照らして重すぎないこと。 |
「やる気がない」だけでは不当解雇になる理由
「やる気がない」という言葉は、個人の内面に関わる主観的で抽象的な表現であり、客観的な指標で測定することは非常に困難です。そのため、「やる気がない」という理由だけで「客観的に合理的な理由」を裏付けることは極めて難しいのが現状です。単に「やる気がない」といった主観的な表現だけでは、具体的な根拠を欠くと見なされ、解雇の有効性が否定される可能性が高いでしょう。
実際に解雇の有効性が裁判で争われる場合、企業側は以下の点を客観的な証拠に基づいて証明する必要があります。
- 無断欠勤や遅刻などの勤怠不良
- 業務命令違反
- 取引先からのクレーム
- 協調性の欠如を示す具体的な問題行動
さらに、会社には解雇を回避するための努力義務が課せられています。具体的な改善指導や配置転換、業務内容の変更といった措置を講じることなく、安易に「やる気がない」と判断し、解雇に踏み切った場合、その解雇は「社会通念上の相当性」を欠くと判断されるリスクが高いといえます。
不当解雇と判断された場合の会社側のデメリット
不当解雇と判断された場合、会社は様々な負担を受けることになります。
まず、最も大きな負担となるのは金銭的な問題です。解雇が無効とされた場合、会社は解雇期間中の賃金(バックペイ)を従業員に支払う必要があります。例えば、月給30万円の従業員の場合、裁判が長期化し12ヶ月後に決着すれば、約360万円が発生することもあります。
さらに、従業員が復職を望まないケースでは、退職に代わる解決金の支払いを要求されることも少なくありません。加えて、悪質な解雇と判断されれば、慰謝料として50万円から100万円程度の支払いが命じられる可能性もあります。これらの費用に弁護士費用も加算されると、会社が負担するべき経済的な負担はかなり大きいものとなります。
金銭的な負担に加え、企業の社会的信用も大きく損なわれます。不当解雇の事実がSNSなどで拡散されると、「ブラック企業」という評判が広がり、新規顧客の獲得や採用活動に悪影響を及ぼす可能性があります。また、裁判や労働審判への対応には、経営者や人事担当者が多大な時間と精神的な労力を費やさなければなりません。その結果、本業に集中できなくなり、他の社員のモチベーション低下や優秀な人材の離職につながる可能性も否定できません。
やる気のない社員への対応|解雇を検討する前に踏むべきステップ
前述の通り、「やる気がない」という漠然とした理由だけで社員を解雇することは、法的に認められない可能性が高いといえます。したがって、解雇という最終手段を検討する際には、企業が社員の能力向上や問題解決のために尽力したという客観的な事実や証拠を丁寧に積み重ねておくことが極めて重要です。以下の項目では、企業が取るべき正しいステップを4段階に分けて詳しく解説します。
ステップ1:問題行動の客観的な記録と証拠収集を行う
やる気のない社員への対応においては、まず主観的な「やる気がない」という評価ではなく、客観的な事実に基づいた問題行動の記録と証拠収集に着手すべきです。これは、将来的に指導や処分、あるいは解雇に至る際の正当性を法的に担保するために不可欠となります。感情的な判断や曖昧な認識での対応は、後の法的紛争において企業側が不利になる可能性を高めます。
具体的には、無断欠勤、遅刻、タイムカードの不正打刻、勤務態度の不良、業務上のミス、ハラスメント、顧客からのクレーム、協調性を欠く言動といった問題行為を裏付ける客観的な資料を残しておきます。客観的な資料がある場合には紛失しないようにしっかりと保全しておきます。資料として残りにくい事情については日報や報告書などの記録として残しておきましょう。
記録する際は、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識し、日時、場所、具体的な言動、そしてそれによって会社の業務にどのような不都合が生じたのかを詳細に記述することが重要です。
ステップ2:面談で改善指導を行い、指導記録を残す
前段階で集めた客観的な事実に基づいて、対象となる社員と面談し、具体的な改善指導を行います。この際、「やる気がない」といった抽象的な表現は避け、社員本人が納得しやすいよう、具体的な問題行動を明確に指摘することが重要です。
面談において、双方向で具体的で測定可能な改善目標を設定した上で、会社が定期的な面談を実施して達成度をフィードバックするなどして、業務改善に向けたプログラムを行います。
面談の終了時には、その日時、同席者、指導内容、社員の反応、そして合意した改善目標などを詳細に記録し保管してください。
ステップ3:本人の適性を考慮し、配置転換や業務内容の変更を検討する
ステップ3の業務改善プログラムを実施しても、目標がほとんど達成できていない場合には、本人の適性を踏まえて、配置転換や業務内容の変更を検討することがあります。
そこで、社員との面談を通じて、本人のキャリア希望、得意な業務、そして今後の展望などを丁寧にヒアリングすることが不可欠です。
ヒアリングで得られた情報をもとに、社内で受け入れ可能な部署や業務がないか具体的に検討し、配置転換や業務内容の変更を打診します。ここで注意を要するのは、やる気のない社員を自主退職に追い込みたいがために、いわゆる追い出し部屋のような場所に配置転換するようなことは避けましょう。
ステップ4:就業規則に基づき、段階的な懲戒処分を実施する
度重なる指導や配置転換を試みても、社員の改善が見られない場合、就業規則に定められた懲戒処分の実施を検討します。懲戒処分は、会社が従業員の企業秩序に違反する問題行為に対して課す制裁です。その種類や事由は就業規則に明記されていなければ、懲戒処分を行うことはできません。
懲戒処分は、社員の問題行動の程度に応じ、軽いものから段階的に行うのが原則です。一般的には戒告や譴責といった軽度の処分から始め、改善が見られない場合は減給、出勤停止といった重い処分へと移行します。
| 段階 | 懲戒処分の種類 | 内容(例) |
| 軽度 | 戒告 | 口頭または書面による注意 |
| 軽度 | 譴責 | 始末書を提出させ、将来を戒める |
| 中度 | 減給 | 給与の一部を減額する |
| 重度 | 出勤停止 | 一定期間の出勤を停止し、その間の給与を支給しない |
この際、処分の重さは、社員の違反行為の内容や態様、処分歴その他の事情に照らし、社会通念上相当なものでなければなりません。軽微な遅刻に対して、いきなり懲戒解雇を下すような不均衡な処分は、懲戒権の濫用と判断され、無効となるリスクが高まります。また、やる気のないという主観的な事情のみで懲戒処分することは控えるべきです。やる気のなさから表出された客観的な問題行為、例えば、遅刻や欠勤、同僚に対する暴言やハラスメントといった客観的な事情を根拠に懲戒処分を検討するべきです。
なお、懲戒処分を実施する際は、対象となる社員に弁明の機会を与えるなど、就業規則に定められた適正な手続きを踏むことも忘れてはなりません。
指導しても改善が見られない場合には退職勧奨を行う
これまでの改善指導や段階的な懲戒処分を経てもなお、社員の勤務態度に改善が見られない場合、次の選択肢として検討されるのが「退職勧奨」です。
しかしながら、退職勧奨の進め方によっては、違法な「退職強要」と判断され、損害賠償を請求されるリスクも伴います。そこで以下の項目では、退職勧奨の具体的な進め方と、法的なトラブルを避けるための注意点について詳しく解説します。
退職勧奨による合意退職を目指す方法
退職勧奨は、企業が従業員に対し、あくまで自主的な退職を促すものであり、会社が一方的に雇用契約を終了させる解雇とは根本的に異なります。これは労使双方の合意形成を目指す手続きであるため、従業員が最終的に退職を選択できる判断ができるよう、慎重に進める必要があります。
面談では、まずこれまでの指導記録や客観的な事実に基づき、会社が期待するパフォーマンスに達していないこと、そして改善の機会を経ても改善が見られないことを冷静に伝えるべきです。その上で、従業員の今後のキャリアを考慮した提案である旨を伝えながら、退職に応じるメリットとなる条件を提示することが重要になります。従業員にとって有利な条件を検討し提示すると良いでしょう。例えば、以下のようなものが挙げられます。
- 退職金の割り増し
- 再就職支援
- 残っている有給休暇の全消化
- 退職日までの出勤の免除
面談で即座に決断を迫ることは避け、従業員が十分に検討する時間を与えることが求められます。退職の合意に至った場合は、後のトラブルを避けるため、「退職合意書」を作成し、退職日や退職条件といった合意内容を書面で明確に残すことが不可欠です。これにより、将来的な紛争のリスクを大幅に低減できます。
退職勧奨の注意点
退職勧奨は、社員に自主的な退職を促す「お願い」であり、社員にはそれに応じる義務がありません。そのため、会社側が一方的に退職を強制することは許されず、言葉遣いや態度には細心の注意を払わなければなりません。
特に、執拗な面談の繰り返し、長時間にわたる説得、あるいは威圧的な言動を伴う行為は、「退職強要」とみなされ、違法となるリスクがあります。
社員が明確に退職勧奨を拒否した場合は、それ以上の勧奨を続けるべきではありません。執拗に勧奨を続ける行為は、社員に精神的苦痛を与え、パワーハラスメントと判断される可能性が高まります。また、退職はあくまで社員の自由な意思に基づくものであるべきであり、退職届の提出を強要することは絶対に避けてください。
普通解雇を実行する際の手続きと注意すべきポイント
指導や退職勧奨を尽くしても状況が改善せず、やむを得ず普通解雇を選択する際には、法的に定められた手続きや注意点を理解しておく必要があります。
30日前の解雇予告、または解雇予告手当の支払い
普通解雇を実行する際には、労働基準法第20条に基づき、従業員に対して解雇する旨を少なくとも30日前までに予告する義務があります。
もし会社が30日前に解雇を予告しない場合、または予告期間が30日に満たない場合は、その不足日数分の「解雇予告手当」を従業員に支払わなければなりません。
解雇理由証明書の準備と交付
従業員を普通解雇する際には、労働基準法第22条第2項に基づき、労働者から請求があった場合、会社は「解雇理由証明書」を遅滞なく交付する義務があります。この証明書は、従業員が解雇の正当性を争う際に重要な証拠となるため、その内容は極めて慎重に作成する必要があります。
解雇理由証明書には、就業規則に定められている解雇事由のいずれに該当するのかを明記し、その根拠となる具体的な事実を客観的に記述することが求められます。
これまでの指導記録や証拠と矛盾がないよう、事実に基づいた正確な記述が不可欠です。万が一、記載内容が事実と異なっていたり、曖昧な表現であったりすると、後の労働審判や訴訟において、会社側が不利になる可能性があります。
感情的にならず、客観的事実に基づいて解雇を通知する
解雇通知を行う面談の場では、経営者個人の感情を交えた発言は避けるべきです。失望や怒りといった感情的な言葉は控えなければなりません。まずは、解雇通知を交付します。解雇通知書に解雇理由を具体的に記載することまでは要求されていませんが、適切に解雇手続を履践したことを示すために、解雇通知書には解雇理由は具体的に記載しておくことが望ましいです。その上で、口頭でも、解雇理由となる客観的な事実を冷静かつ淡々と説明することが重要です。
労働問題に詳しい弁護士に相談するメリットとタイミング
労働問題に詳しい弁護士への相談は、企業が法的リスクを回避し、適切な対応を進める上で非常に有効です。主なメリットは以下の3点です。
一つ目は、法的リスクの客観的な評価です。専門的な法律知識に基づき、問題のある社員への対応が法的に妥当であるかを客観的に評価してもらえます。不当解雇のリスクを回避するための証拠収集や、その有効性についても具体的な助言を得られるでしょう。
二つ目は、解雇に向けた適切な手順に関する助言です。解雇や退職勧奨の手続き、従業員との交渉方法について適切な指導を受けられます。弁護士が代理人として交渉を代行することも可能であり、企業側の精神的・時間的負担の軽減につながります。
三つ目は、訴訟リスクへの備えです。労働審判や訴訟に発展した場合でも、弁護士が全面的にサポートするため、安心して対応を進められます。
社員への改善指導で効果が見られない段階や退職勧奨や解雇を具体的に実行する前の段階で、弁護士に相談することが理想です。解雇処分後に問題が顕在化した後に弁護士に相談してからでは時機に遅れてしまうおそれがあります。
やる気のない社員の対応は難波みなみ法律事務所へ
やる気がないことだけを理由に社員を解雇すると、不当解雇となるおそれがあります。無計画に解雇手続を進めれば、社員から不当解雇の主張を受けてしまい、バックペイ等の経済的な負担を受けるだけでなく、企業としての社会的な信用を毀損されるリスクがあります。
しかし、モチベーションの低い社員を漫然と放置することは他の社員の士気を低下させ、全社的な業務効率を悪化させます。そこで、会社としては、業務改善のプログラム、配置転換や業務内容の変更、場合によっては懲戒処分の実施といった各プロセスを経た上で、退職勧奨を行うなどの対応を行うことが求められます。
これら各プロセスを適切に進めるためにも、できるだけ早い時期に弁護士に相談することを検討しましょう。