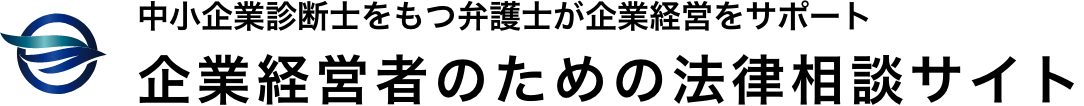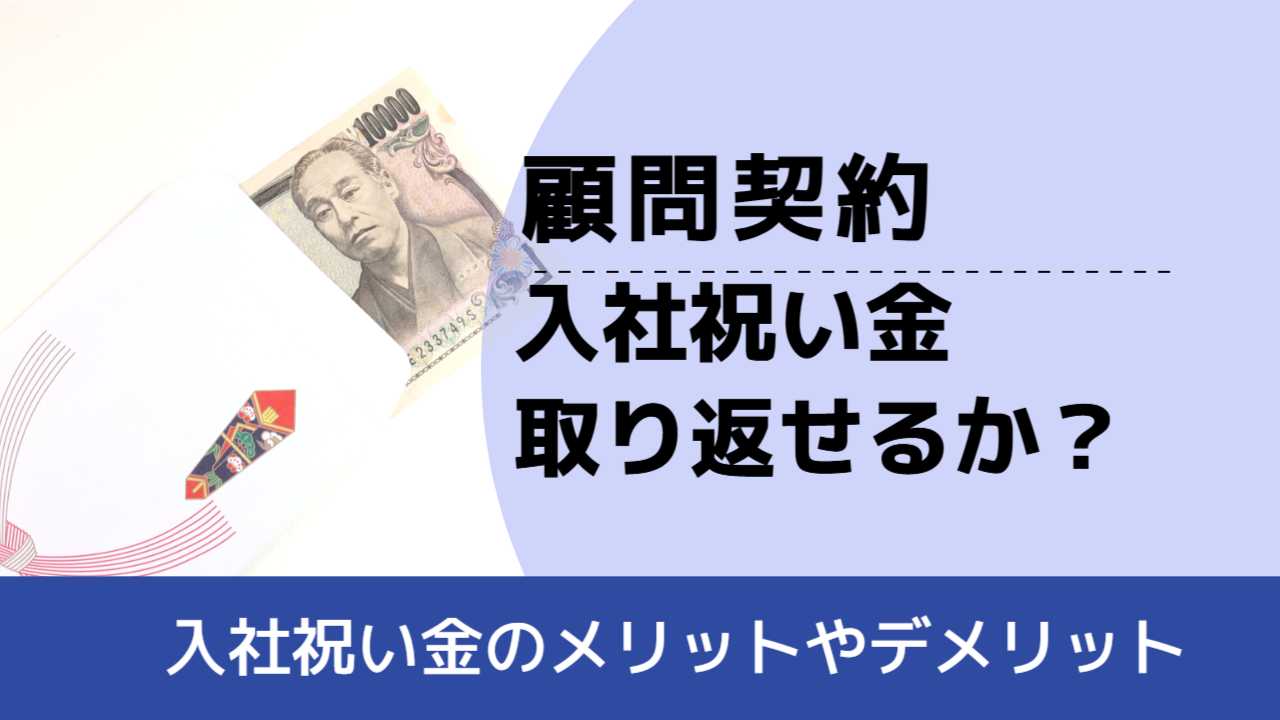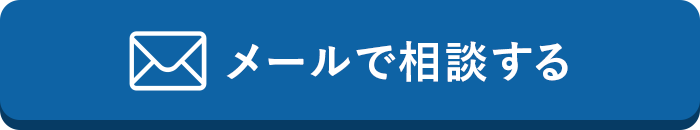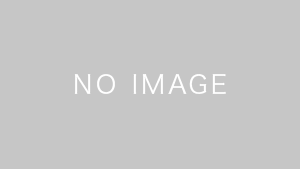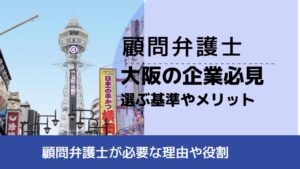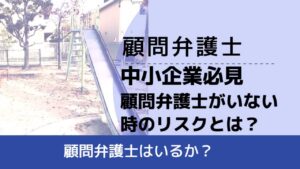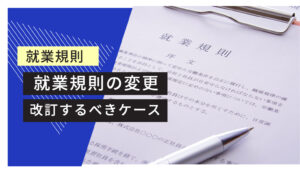近年、人材獲得競争が激化する中で、「入社祝い」金制度を導入する企業が増えています。この制度は、新しい社員の入社を「祝い」、定着を促進する効果が期待されていますが、導入にあたっては、メリットだけでなく注意すべき点も存在します。
本記事では、入社祝い金制度の導入を検討する際に必要な情報をまとめました。制度の概要から、支給条件の設定方法、規程の作成、さらには法的な注意点まで、具体的に解説します。
そもそも入社祝い金とは?採用における役割を再確認
以下では、入社祝い金のより詳細な定義や目的、導入が進む背景について詳しく解説していきます。
入社祝い金の定義と支給する目的
入社祝い金とは、企業が新たに採用した従業員に対し、入社を祝う意味合いで支給する一時金、または特別手当の一種です。この制度は、単に金銭的なメリットを提供するだけでなく、激化する採用競争において、他社との差別化を図り、求職者にとって魅力的な職場であることをアピールする強力な手段となります。
支給の主な目的は、内定者の入社意欲をさらに高め、内定辞退を未然に防ぐことにあります。また、新しい環境での生活を始める新入社員に対し、経済的な支援を行うことで、引っ越し費用や新生活用品の購入など、入社時の負担を軽減する狙いもあります。
なぜ、入社祝い金を導入する企業が増えているのか
近年、入社祝い金を導入する企業が増加しています。その背景には、日本の労働市場における深刻な人手不足と、それに伴う人材獲得競争の激化があります。
総務省の統計によると、企業の約5割が人手不足を感じており、特に中小企業では68.0%の企業が人手不足と回答しています。また、帝国データバンクが2025年1月時点で実施した調査では、正社員不足の企業が53.4%、非正社員不足が30.6%に達し、これはコロナ禍以降で最も深刻な水準となっています。
このような状況下で、企業は数多くの求人の中から自社を選んでもらうため、採用活動の差別化を図る必要に迫られています。入社祝い金は、求職者の目を引く有効な施策の一つとして機能しています。さらに、転職活動にかかる費用や、入社直後の新生活における経済的な不安を払拭する効果も期待できます。

企業が入社祝い金を導入するメリット・デメリット
入社祝い金制度は、求職者にとって魅力的な制度である一方で、導入を検討する際には、そのメリットとデメリットを両側面から理解しておくことが不可欠です。
このセクションでは、入社祝い金がもたらすプラスとマイナスの点について詳しく解説します。
【メリット】応募者数の増加と採用競争力の強化
入社祝い金制度は、企業の採用活動において、応募者数の増加に大きく貢献します。求人情報が溢れる現代において、「入社祝い金あり」という明確なインセンティブは、求職者の目を強く引き、応募を促すきっかけとなります。
また、転職活動には、交通費や面接のための準備費用など、求職者にとって少なからず経済的な負担が伴います。入社祝い金は、これらの費用負担を軽減する効果があり、応募への心理的なハードルを下げることにつながります。これにより、潜在的な候補者層からの応募を促進し、母集団の形成に大きく貢献します。
さらに、競合他社との差別化要因としても機能します。入社祝い金を提供することで、自社の採用市場における魅力を高め、優秀な人材を獲得するための強力な武器となり得ます。
【メリット】内定辞退の防止と早期定着率の向上
入社祝い金は、複数の企業から内定を得ている候補者が最終的な意思決定を下す際の「最後の一押し」として機能し、内定辞退の防止に大きく貢献します。入社に伴う引っ越し費用や新生活の備品購入など、求職者が抱える経済的な負担を軽減することで、内定承諾への心理的なハードルが下がり、入社への不安を和らげる効果が期待できます。
また、入社祝い金を「試用期間終了後」や「入社後6ヶ月の在籍」など、特定の条件を満たした後に支給することで、早期離職の抑制にも繋がります。段階的な支給は、従業員のモチベーションを維持するとともに早期離職の抑制にも繋がります。
【デメリット】採用コストの増大
入社祝い金は、従来の採用コストに直接上乗せされるため、企業の費用負担を増大させる要因となります。このような追加コストは、採用全体の予算を圧迫しかねません。その結果、求人広告の出稿強化や採用イベントへの参加など、他の重要な施策に投じられる予算が減少する恐れがあります。
さらに、せっかく支給した入社祝い金を受け取った従業員が早期に離職してしまった場合、その祝い金は回収不能なコストとなり、採用や教育に費やした時間や費用が無駄になる可能性も考慮すべき点です。
【デメリット】「祝い金目当て」の応募を招くリスクと既存社員への配慮
入社祝い金は応募者を引きつける強力なインセンティブとなりえますが、その一方で、企業や仕事内容よりも金銭そのものを主目的とする求職者を集めてしまうリスクも存在します。このような動機で入社した従業員は、入社後のミスマッチを感じやすく、早期離職につながる可能性が高まるでしょう。結果として、採用や教育に費やしたコストが無駄になりかねません。
こうしたリスクを回避するためには、入社祝い金の支給条件を「入社後一定期間の勤続」とするなど、明確に定めることが重要です。また、支給を複数回に分けることで、短期的な金銭目的での入社を防ぎ、長期的な定着を促す効果も期待できます。
【担当者必見】入社祝い金制度を導入する5つのステップ
入社祝い金制度を採用戦略に効果的に組み込むためには、計画的に導入することが必要です。
以下では、入社祝金制度を導入するための5つのステップを順に解説します。
Step1:支給対象者と金額の決定
入社祝い金制度を導入するにあたり、まず支給対象者を明確に定めることから始めます。対象者を全社員とするのか、それとも採用が困難な特定の職種や雇用形態(正社員か否か)に限定するのかを、企業の採用戦略や人材獲得目標に合わせて決定します。この対象設定は、費用対効果を最大化し、最も採用したい人材にインセンティブが届くようにするために重要です。
次に、支給金額を設定します。採用予算や採用市場における競合他社の動向、求める人材の希少性などを総合的に考慮し、応募者にとって魅力的でありながら、企業にとって過度な負担とならない金額とすることが重要です。
Step2:支給条件の明確化(勤続期間など)
入社祝い金制度を効果的に運用し、支給後のトラブルや、祝い金目当ての短期離職を防ぐためには、支給条件を明確に定めることが極めて重要です。支給条件が曖昧なまま契約を進めると、支給されないといった問題につながる可能性があります。
最も一般的に設定されるのは、一定期間の勤続です。具体的には、試用期間満了後や入社後3ヶ月以上の勤務が必要といった形で設定されます。これにより、短期離職を防ぎ、企業への定着を促す効果が期待できます。
勤続期間のほかにも、対象期間中の出勤率が90%以上であることや、試用期間中の勤務評価が良好であることといった条件を設けることも可能です。これらの条件は、良好な勤務態度で真摯に業務に取り組む人材の定着を促す有効な手段となります。
設定した支給条件は、必ず就業規則や雇用契約書に具体的に明記することが不可欠です。書面での明記がない場合、後々のトラブルの原因となる可能性が高まります。
Step3:支給タイミングの検討(入社直後、試用期間後など)
入社祝い金の支給タイミングは、応募者へのインセンティブとしての役割だけでなく、祝い金目当ての短期離職を防ぎ、従業員の早期定着を促す上で極めて重要な要素です。適切なタイミングを設定することで、企業は採用リスクを抑えつつ、制度の効果を最大化できるでしょう。
主な支給タイミングは、「入社直後(初任給と同時など)」「試用期間終了後」「分割支給」の3つです。
入社直後の支給は、入社時の経済的負担を軽減し、求職者にとって大きな魅力となります。一方で、金銭目的での短期離職リスクが高まるデメリットも伴います。
次に、試用期間終了後の支給は、早期離職の防止に最も効果的な選択肢の一つです。「入社後〇日勤務した場合」や「試用期間を経過し、本採用された場合」といった条件設定は、従業員の定着を促し、企業側の採用リスクを低減するメリットがあります。
また、入社後数ヶ月ごとに複数回に分けて支給する分割支給も有効です。
| タイミング | メリット | デメリットや注意点 | 適した企業のニーズ |
|---|---|---|---|
| 入社直後 | ・入社時の経済的負担を軽減・求職者にとって大きな魅力・母集団形成に効果的 | ・金銭目的での短期離職リスク増大 | ・応募者数を増やしたい |
| 試用期間終了後 | ・早期離職の防止に最も効果的・従業員の定着を促進・企業側の採用リスクを低減・法的に安全な運用が可能 | ・入社時の経済的インセンティブとしては劣る | ・早期離職を防ぎたい |
| 分割支給 | ・従業員のモチベーションを継続的に維持・段階的な定着を促進 | ・管理の手間が増える可能性・一括払いと比較してインパクトは弱い | ・早期離職を防ぎたい |
Step4:就業規則や雇用契約書への反映
決定した入社祝い金制度の内容は、労使間のトラブルを未然に防ぎ、制度の公平性を保つためにも、就業規則や雇用契約書に明確に反映させる必要があります。
入社祝金が賃金としての性格を持つ場合、就業規則に明記すべき主な項目は以下の通りです。
- 支給対象者
- 具体的な支給金額
- 支給条件
- 支給タイミング
- 早期退職時の返金に関する規定
また、個別の労働条件として合意を明確にするため、雇用契約書にも入社祝い金の支給がある旨を記載し、詳細は就業規則を参照するよう記載することが重要です。
Step5:求人情報への記載方法
入社祝い金制度を効果的にアピールするには、求人情報への記載方法が非常に重要です。「入社祝い金あり」と記すだけでは、その魅力は十分に伝わらず、応募者の不安を解消することもできません。求職者が安心して応募を検討できるよう、入社祝金の金額や条件などを明確に記載しましょう。
入社祝い金に関する法的な注意点とトラブル対策
入社祝い金は、採用競争力を高める強力な戦略として活用できますが、税務や労働法規といった法的側面を正しく理解せずに導入すると、予期せぬトラブルに発展する可能性があります。
以下では、入社祝金制度を安全に運用するために、必ず押さえておくべき重要な法的注意点について解説します。
入社祝い金にかかる税金(所得税)の扱いはどうなる?
入社祝い金は、原則として給与所得と見なされ、所得税の課税対象となります。これは、雇用契約に基づき企業から支給される金銭であり、労働の対価としての性格を持つためです。
また、入社祝い金は所得税だけでなく、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料といった社会保険料の算定基礎にも含まれます。
早期退職者への返金要求は法的に有効か?
入社祝い金の返金要求は、原則として法的に有効とは認められません。
労働基準法第16条は、労働者が退職する際に金銭的ペナルティを課すことで、労働者の退職の自由を不当に拘束することを禁じています。そのため、入社祝い金の返還を条件付ける行為は、労働基準法第16条に抵触することになります。
たとえ「一定期間内に自己都合で退職した場合は返金する」といった内容の誓約書を従業員と交わしていたとしても、その合意自体が労基法や公序良俗に反するとされ、無効と判断される事例が複数存在します。
例外的に、入社祝金が従業員に対する貸金であり、返還条件などを明記した金銭消費貸借契約書が作成されている場合には、入社祝金の返金を求めることが認められる可能性があります。ただし、祝い金という名称を用いると、借金という認識を持ちにくいため、支給する金銭の名称には工夫が要するでしょう。
日本ポラロイド事件(東京地判平成15年3月31日)
一度支給された賃金をどのように使うかは労働者の自由であり,サイニングボーナスの額に比べ毎月の支給額が極めて高額であるといったような特段の事情がない限り,退職に際し,使用者から一度に100万円を超す相当額の賃金(サイニングボーナス)の返還を求められれば,通常の労働者は退職を躊躇するとみるのが相当である。また,原告会社は被告に返済計画では話合いの余地がある旨提案したことが認められるけれども,そうであるからといって,本件報酬約定の性質が変わるものではない。)。したがって,本件報酬約定に定める本件サイニングボーナスの給付及びその返還規定は,本件サイニングボーナスの性質,態様,本件報酬約定の内容に照らし,それが被告の意思に反して労働を強制することになるような不当な拘束手段であるといえるから,労働基準法5条,16条に反し,本件報酬約定のうち本件サイニングボーナス返還規定は,同法13条,民法90条により無効であるというのが相当である。
【要確認】職業安定法改正による「お祝い金」提供禁止との関係性
職業安定法の改正により、求人サイトなどの「募集情報等提供事業者」や「職業紹介事業者」が、求職者へ「就職お祝い金」を支給する行為は原則禁止となりました。この規制は、職業紹介事業者には2021年4月から、求人サイトを運営する募集情報等提供事業者には2025年4月1日から適用されています。
しかし、企業が自社で採用した従業員に対し、直接「入社祝い金」を支給する行為は、この職業安定法の規制対象外であり、合法的に実施可能です。
そのため、企業が採用戦略として入社祝い金制度を導入する際は、これが企業自身が支給するものであることを明確に示し、求人メディアなどが提供するキャンペーンと誤解されないよう注意を払う必要があります。
アルバイトやパートタイマーを対象にする場合の注意点は?
アルバイトやパートタイマーを入社祝い金の対象とする場合、正社員との間に不合理な待遇差が生じないよう、特に注意が必要です。
短期離職を防ぐためには、正社員と同様に支給条件を明確に設定することが重要です。特にパートタイムーは勤務日数が変動しやすい雇用形態であるため、「入社後3ヶ月間の継続勤務」や「総勤務時間〇時間以上」といった、より具体的な条件を定めることが求められます。また、祝い金の金額についても、採用コスト全体に見合っているか、費用対効果を慎重に検討する必要があります。アルバイトやパートタイマーの採用単価は正社員に比べて低い傾向にあるため、採用目標と予算のバランスを考慮した金額設定が重要です。
入社祝い金の問題は難波みなみ法律事務所へ
入社祝い金制度の概要から導入の5ステップ、そして見落としがちな法的注意点までを網羅的に解説いたしました。特に、入社祝金を支給した途端、社員から退職届が提出されたような場合に、入社祝金の返還を求めたいという相談が多く寄せられます。
しかし、入社祝金の返還を求めることは労基法や公序良俗に違反するものとして認められない可能性が高いです。退職者とのトラブルを防ぎつつ、入社祝い金を用いた効率的な人材確保を実現させるために、丁寧な制度設計が大切です。