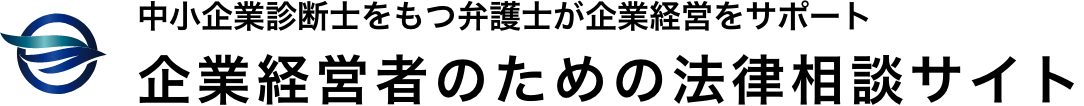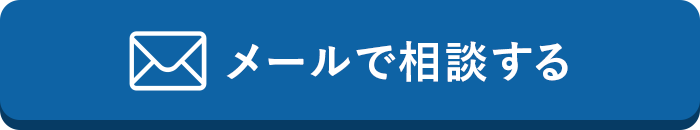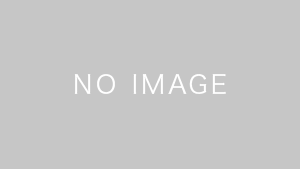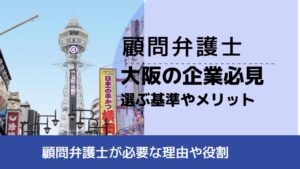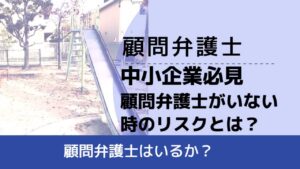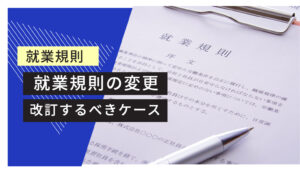家賃滞納が発生し、入居者が夜逃げしてしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。滞納家賃の回収はもとより、残された家財の処理、新たな入居者の募集など、対応すべきことは多岐に渡ります。
本記事では、家賃滞納者がいわゆる夜逃げした場合の対応について、強制執行の手続きを中心に解説します。万が一の事態に備え、冷静かつ適切に対処するための知識を身につけましょう。
入居者が夜逃げ?まず確認すべき兆候と絶対にしてはいけないこと
入居者と連絡が途絶え、夜逃げの可能性がよぎった場合、焦って行動することは禁物です。まずは冷静に状況を確認し、適切な手順を踏むことが重要です。以下では、夜逃げを疑うべき具体的な兆候と、法的なトラブルを避けるために大家さんが絶対にやってはいけない「自力救済」について詳しく解説します。
夜逃げを疑うべきサインとは
入居者による夜逃げを疑うべき状況には、いくつかの具体的なサインがあります。
まず、家賃の滞納が続いているにもかかわらず、電話やメール、訪問など、あらゆる手段での連絡に一切応じなくなる状況が挙げられます。これは、単なる連絡不通ではなく、入居者が意図的に接触を避けている可能性を示唆します。
また、部屋の郵便受けが郵便物やチラシで溢れている、あるいは電気やガスのメーターが長期間にわたってほとんど動いていないといった兆候もあるでしょう。
これらは、実際にその物件に居住している形跡がないと判断できる客観的な状況と言えます。夜になっても室内の明かりが全くつかない日が続いたり、洗濯物が何日も干されたままの状態であったりするのも、不自然な生活状況を示すサインです。
さらに、近隣住民やマンションの管理人から「最近、入居者の姿を全く見かけない」「夜中に大きな荷物を運び出すような音を聞いた」といった情報が寄せられる場合も、夜逃げを強く疑うべき重要な兆候となります。
これらの情報を総合的に判断し、適切な対応を検討していくことが大切です。
| 分類 | 具体的な兆候 |
| 連絡不通 | ・家賃滞納が続き、電話、メール、訪問など、一切の連絡に応じない。 |
| 物理的兆候 | ・郵便受けが郵便物やチラシで溢れている。 ・電気やガスのメーターが長期間動いていない。 ・夜になっても室内の明かりが全くつかない。 ・洗濯物が何日も干されたままになっている。 |
| 外部情報 | ・近隣住民や管理人から入居者の姿を見かけないとの情報。 ・夜中に大きな荷物を運び出すような音を聞いたという情報。 |
【厳禁】勝手な入室や家財の処分は「自力救済」にあたる
賃貸借契約において、家賃滞納や入居者の夜逃げが疑われる状況であっても、オーナーが法的な手続きを経ずに実力で権利を実現しようとする行為は「自力救済」と呼ばれ、法律で固く禁じられています。これは、たとえ入居者が契約に違反していても、その居住権や財産権は法的に保護されているためです。
オーナーが陥りがちな自力救済の具体例を以下に挙げます。
- 入居者の無断での室内への立ち入り
- 勝手に鍵を交換して締め出すこと
- 室内に残された家財を処分すること
これらの行為は法に抵触する可能性があるため、絶対に行ってはいけません。例えば、無断で室内に立ち入れば住居侵入罪に、家財を勝手に処分すれば器物損壊罪に問われる恐れがあります。さらに、入居者から民事上の損害賠償請求を受けるリスクも発生します。
このように、自力救済は刑事罰や多額の損害賠償といった大きなリスクを伴うため、必ず弁護士などの専門家に相談し、法的な手順を踏んで対応を進めることが不可欠です。
居住の事実を確認する適切な方法
入居者との連絡が途絶え、夜逃げの疑いがある場合でも、前述の「自力救済」は、決して行ってはならない行為です。借主の権利侵害を避けるためにも、あくまで慎重に居住実態を確認することが重要です。
まず、物件の外部から確認できる客観的な状況を確認しましょう。具体的には、以下の点に注目してください。
- 郵便受けに郵便物やチラシが長期間溜まっていないか。
- 電気やガスのメーターが長期間動いているか。
同時に、入居者への連絡を試みることも重要です。電話、メール、手紙などの手段で連絡を試み、その日時や内容を詳細に記録しておきましょう。これらの記録は、その後の法的手続きにおいて、貸主が連絡を尽くしたことを示す有力な証拠となります。
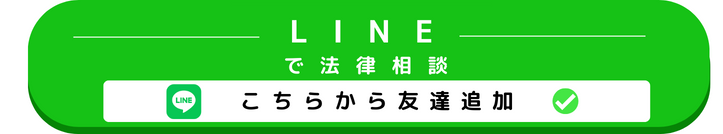
家賃滞納で夜逃げされた場合の正しい対応手順
入居者の夜逃げが発覚した際、貸主が感情的になり、勝手に部屋に立ち入ったり、家財を処分したりする行為は「自力救済」にあたり、法律で固く禁じられています。
冷静さを保ち、法に則った正しい手順を踏むことが、法的トラブルを避ける上で、極めて重要です。
ここからは、入居者が夜逃げした場合の正しい対応手順として、具体的なステップを順を追って解説します。
ステップ1:連帯保証人・家賃保証会社に連絡する
家賃の滞納が確認され、入居者との連絡が取れない場合、まずは「連帯保証人」または「家賃保証会社」への連絡です。
連帯保証人に連絡する際には、滞納状況を正確に伝えてください。連帯保証人には「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」が認められていないため、貸主は連帯保証人に対して、いきなり直接請求することが可能です。
家賃保証会社へ連絡する場合は、滞納家賃の代位弁済を請求します。保証会社への事故報告を所定の期限までにしなければ、保証会社は免責されるため注意しましょう。
ステップ2:内容証明郵便で契約解除通知を送付する
入居者との連絡が途絶え、家賃の滞納が続く場合、次のステップとして内容証明郵便を用いて賃貸借契約の解除通知を送付します。
内容証明郵便は、誰が、どのような内容の文書を、いつ差し出したかを郵便局が証明する郵送方法です。内容証明郵便を用いることで、後の明渡請求訴訟で相手方から「そのような通知は受け取っていない」と主張される事態を防ぎ、法的な証拠として強力な効力を持つことができます。
通知書には、法的に有効な契約解除とするために、以下の項目を明記します。
- 滞納している家賃の合計金額
- 相当の期間を定めて支払いを催告する
- 期間内に滞納家賃が支払われない場合には賃貸借契約を解除する旨の意思表示
- 建物の明け渡しを請求する旨
ただ、借主は所在不明となっているため、内容証明郵便を送付しても受領されない可能性が高いです。この場合には、内容証明郵便を公示送達という方法で送達する方法もありますが、次のステップである訴訟提起に移行させることが多いでしょう。
ステップ3:建物明渡請求訴訟を提起する
内容証明郵便を送付しても入居者からの返答がない場合や所在不明のため内容証明郵便を送付できない場合、次のステップとして「建物明渡請求訴訟」を提起する必要があります。
この訴訟の目的は、法的な強制力を持つ「債務名義」、すなわち建物明け渡しを命じる判決を得ることです。この判決がなければ、強制的に入居者を退去させたり、室内に残された物を処分したりすることは、法的に認められていません。
夜逃げのケースでは、借主の所在不明により訴状を送達することができないこともほとんどです。この場合には、公示送達という特殊な送達方法により訴状を送達します。公示送達とは、相手方の所在が分からないときに、裁判所の掲示場に掲示する方法で書類を送達したものとみなす制度です。公示送達により、掲示がなされてから2週間の経過により送達の効果が生じます。公示送達を含め送達ができてから、初めて訴訟手続が進行していきます。
公示送達により送達手続を行った場合、裁判期日に被告である借主が出席することはほとんどありません。そのため、被告の欠席により弁論は速やかに終結し、原告である貸主の請求を認める判決が言い渡されます。
ステップ4:強制執行を申し立てる
建物明渡請求訴訟で勝訴判決を得たにもかかわらず、あるいは裁判上の和解が成立したにもかかわらず、入居者が自主的に退去しない場合、最終的な手段として「強制執行」を申し立てる必要があります。裁判所の判決を得たからといって、自力執行が認められるわけではありません。
強制執行の申立てを行った上で、明渡の催告を行い、それでも明け渡しに応じない場合に明け渡しの断行をします。
建物明渡しの強制執行とは?手続きの詳細と注意点
建物明渡請求訴訟で勝訴判決を得たにもかかわらず、入居者が物件を自主的に明け渡さない場合、最終的な法的手段として「建物明渡しの強制執行」を行います。
以下では、この建物明渡しの強制執行について詳しく解説していきます。
強制執行の申し立てから完了までのプロセス
建物明渡請求訴訟で得た勝訴判決などの債務名義に基づき、強制執行を申し立てるところから、実際の強制執行の手続きが始まります。強制執行のおおまかな流れは、申立て→明渡しの催告→断行となります。
まず、強制執行の申し立ては、物件の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に対して行われます。
申立てには、以下の書類が必要です。
- 債務名義(判決の正本など)
- 送達証明書(債務名義が相手方に送達されたことを証明するもの)
- 執行文(強制執行を行う資格があることを示すもの)
- 当事者が法人の場合には資格証明書
申し立てが受理されると、執行官は対象物件を訪れ、入居者に対して明け渡しの期限を定める催告を実施します。明渡の催告は申立てから2週間以内に実施することになっています。
催告時には、執行官が断行日を伝えて前日までに明け渡しに応じるように伝えた上で、催告書の交付と公示書の掲示をします。借主が不在である場合でも、合鍵や解錠により物件内に立ち入り、占有状況を確認した上で、公示書と催告書を掲示します。
催告期限を過ぎても入居者が退去しない場合、断行と呼ばれる強制的な明け渡しが行われます。執行官の指揮のもと、専門の業者が鍵を解錠し、室内の家財を強制的に搬出します。
室内に残された家財(残置物)の処分方法
室内に残された家財(残置物)などの目的外動産の所有権は、依然として借主が有しています。そのため、貸主が勝手にこれらを売却したり廃棄したりすることはできず、強制執行のプロセスの中で適切に処理する必要があります。
すなわち、断行日に借主に目的外動産を引き渡すことができない時は、他の保管場所に目的外動産を移した上で、動産執行の例により売却をすることになります。この保管場所は執行業者の倉庫や貸主所有の倉庫などが挙げられますが、その保管料は債権者である貸主が一旦負担することになります。
ただ、建物明渡の強制執行をする場合には、目的外動産の差押えもセットで行うのが通常です。目的外動産の差押えをしておくことで、断行日に目的外動産を売却することができ、貸主自身が買い受けた場合には目的外動産を保管場所に搬出する必要もなくなるなど、搬出費用や保管費用を節約できる可能性があります。なお、差押禁止財産などがあることで動産執行できない場合には、保管替えの手続を行うことになります。
強制執行にかかる費用の内訳と相場
建物明渡しの強制執行にかかる費用は、原則として貸主が一旦立て替える必要があります。これらの費用は、執行の準備から完了までに多岐にわたります。
- 予納金(大阪地裁 6万円)
- 解錠業者の費用(1〜2万円)
- 執行業者の運搬費用(30万円〜60万円)
- 保管替えの保管料
執行業者の費用は、部屋の間取りや残された荷物の量によって大きく変動し、30万円から60万円あたりが多い印象です。
これらの費用は債務者である借主の負担すべき費用ですが、回収できないことがほとんどですので、実質的には貸主の負担にならざるを得ません。
手続き開始から完了までにかかる期間の目安
建物明渡しにおける強制執行は、申し立てたからといってすぐに完了するものではなく、法的な手続きを経るため、一定の期間を要します。滞納家賃の発生から訴訟提起、そして強制執行の完了まで1年以上かかる場合も珍しくありません。
具体的な各ステップにかかる期間の目安は以下の通りです。
- 建物明渡請求訴訟の提起から判決確定までは、借主が所在不明であれば、2ヶ月から半年程度が目安とされます。
- 判決確定後、強制執行を申し立ててから入居者への「催告」が実施されるまでは、およそ2週間から1ヶ月程度です。この催告では、明け渡し期限が約1ヶ月後に指定されます。
- 催告期限を過ぎても入居者が退去しない場合、実際の「断行」が行われるまでには約1ヶ月かかります。
- 保管替えをする場合には、1ヶ月ほど目的外動産を保管した上で売却することになります。
これらの期間は、あくまで手続きがスムーズに進んだ場合の目安です。入居者が裁判で積極的に争ったり、控訴したりする場合には、さらに期間が長引く可能性があります。また、執行官のスケジュールによっても、手続きの進行が前後することがあるため、余裕を持った計画を立てることが重要です。
今後のために!家賃滞納・夜逃げリスクを軽減する予防策
家賃滞納や夜逃げは、一度発生すると解決までに多大な時間と費用を要する深刻な問題です。
そのため、問題が実際に発生してから対処するのではなく、未然にリスクを防ぐための「予防策」を講じることが重要であると言えます。
入居審査で確認すべき重要ポイント
家賃滞納や夜逃げのリスクを未然に防ぐ上で、入居審査を厳格に行うことが重要です。
まず、申込者の支払い能力を客観的な書類で確認することが大切です。また、リスク軽減のためにも、家賃保証会社の利用を必須条件とすることも有効な手段となります。
敷金を入れてもらう
家賃滞納のリスクを回避するために、賃貸借契約の締結時に、借主から敷金を納入してもらうことが有用です。
敷金とは、借主が貸主に対して負う債務を担保するため、あらかじめ賃借人が賃貸人に差し入れておく金銭です。敷金を入れてもらうことで、借主が家賃を滞納しても、預託された敷金から滞納家賃を回収することができ、家賃不払いのリスクを軽減させることができます。
滞納発生後の初期対応を迅速に行う
家賃の滞納が確認された場合、迅速な初期対応をすることで、滞納の常習化や金額の増大を防ぎ、最終的に夜逃げといった最悪の事態へ発展するリスクを低減させることができます。
滞納発生後の初期対応の主なポイントは以下の通りです。
- 滞納発生から1週間以内を目安に連絡する。
- 電話やショートメッセージで、「家賃の支払いが確認できていない」事実を伝える。
- 「言った・言わない」といったトラブルを避けるため、書面による督促も検討する。
もし入居者と連絡が取れた場合は、滞納に至った具体的な理由を確認しましょう。一時的な経済状況の悪化が原因であれば、分割払いの相談に応じるなど、柔軟な姿勢で対応することが、解決への近道となる場合もあります。
滞納された家賃は回収できる?請求方法と時効の知識
入居者に夜逃げされてしまった場合でも、滞納された家賃の回収は決して不可能ではありません。正しい法的手続きを踏むことで、未払い分の家賃を回収できる可能性があります。感情的な対応は避け、冷静かつ計画的に対処することが重要です。
連帯保証人・保証会社への請求手続き
家賃の滞納が確認され、入居者との連絡が取れない状況であれば、まず連帯保証人または家賃保証会社へ連絡します。
家賃保証会社へ請求する場合、保証契約の内容に基づき、家賃保証会社に対して代位弁済を求めます。多くの保証契約では滞納発生後の報告期限が定められているケースが多いため、期限内に事故報告をするように留意してください。
ここで特に注意すべき点として、保証会社が代位弁済を行うと、貸主が有していた滞納家賃の債権は保証会社に移転します。そのため、保証会社による代位弁済後は、貸主が借主本人や連帯保証人に同じ家賃を請求することはできません。これは二重請求となるため、十分注意が必要です。
入居者本人から回収する方法
入居者本人が任意に滞納家賃を支払わない場合には、敷金の預託があれば敷金と滞納家賃を相殺することで回収を図ることができます。
一方で、敷金の預託がない場合には、入居者の財産を差し押さえるなどして強制的に回収するしかありません。入居者の財産を差押えをするためには、滞納家賃の支払いを命じる確定判決などの債務名義が必要となります。
まず、所在不明となった借主に対して建物明渡請求の訴訟提起をする場合、建物の明渡しだけでなく、未払い賃料の請求もセットで行います。そのため、建物明渡請求訴訟を通じて、未払い賃料に関する判決(債務名義)を得ることができます。ただ、夜逃げをする借主に十分な資産がないことがほとんどであるため、差押手続をしたとしても空振りとなる可能性は非常に高いといえます。
なお、家賃回収の方法として、支払督促や少額訴訟という手続も考えられます。これらの手続は迅速かつ簡易的なプロセスですので、債務名義を取るための有用な方法にはなります。ただ、いずれの方法も公示送達による送達手続を利用できないため、借主が夜逃げしているケースでは利用しにくいといえます。
家賃請求権の時効と更新手続きについて
家賃を請求する権利(賃料債権)には、法律で定められた消滅時効が存在します。この期間を経過すると、借主から時効の援用を受けることで賃料債権は消滅します。2020年4月1日に施行された改正民法により、債権の消滅時効は「権利を行使できることを知った時から5年」、または「権利を行使できる時から10年」と原則的に統一されました。
時効の完成を阻止するためには、適切な法的手続きを行うことが重要です。「時効の完成猶予」と「時効の更新」という二つの概念があります。
内容証明郵便による催告は、催告時から6ヶ月間時効の完成が猶予される「時効の完成猶予」にあたります。
一方、訴訟の提起や支払督促の申し立て、和解などが成立した場合は、時効期間がリセットされ、新たに時効期間が進行し始める「更新」の効果が生じます。また、借主本人が家賃の支払い義務を認める「債務の承認」があった場合も、時効は更新(リセット)されます。
滞納家賃が時効により消滅することのないように時効期間を管理し、万一、時効期間が間近であれば、催告の上で訴訟提起をすることで時効期間の更新手続を進めていくことが肝要です。
借主が夜逃げした場合には弁護士に相談を
家賃滞納者が夜逃げした場合の対応は、貸主にとって大きな負担となる問題です。
重要な点は、いかなる状況でも、貸主が勝手に鍵を交換したり、室内の家財を処分したりする「自力救済」は法律で固く禁じられていることです。強制執行は、申し立てから完了までに1年以上かかるケースも珍しくなく、多額の費用負担が生じることもあります。
もし明け渡しに必要となる法的手続きの対応に不安を感じたり、手続きが複雑で手に負えないと感じたりした場合は、速やかに弁護士へ相談することを強く推奨します。