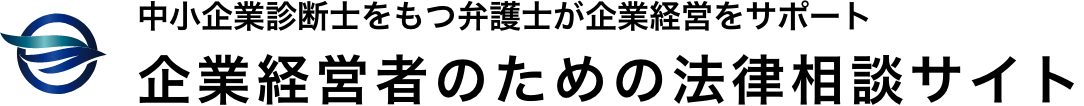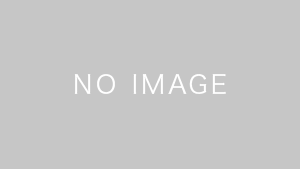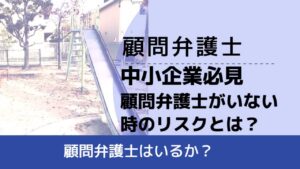懲戒処分を検討する際、企業は従業員に弁明の機会を付与する必要があるのでしょうか?人事担当者としては、その要否や、もし必要な場合にどのような手続きを踏むべきか、気になる点が多いのではないでしょうか。
懲戒処分は、従業員のキャリアに大きな影響を与える可能性があります。そのため、会社側は慎重な対応を求められます。今回は、弁明の機会付与について、その法的根拠から具体的な機会の与え方、注意点までをわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてみてください。
「弁明の機会の付与」とは?
適正な弁明の機会を付与せずに行われた懲戒処分は、後に訴訟などで無効と判断されるリスクがあります。企業としては、労使間のトラブルを避けるためにも、このプロセスを法的に極めて重要なものと位置づける必要があります。
以下では、弁明の機会の意義について解説します。
弁明の機会の付与の基本的な意味
「弁明の機会の付与」とは、企業が従業員に対し懲戒処分を下す前に、処分の対象となる従業員本人から、その原因とされる事実についての言い分を直接聞く手続きのことです。これは、従業員が問題行動に至った理由や動機、現状における反省の意などを説明し、自身の立場を主張するための重要な機会となります。
企業側としては、この弁明を聞くことで、一方的な判断による事実誤認を防ぎ、処分の客観性と公正性を確保する目的があります。従業員からの具体的な説明は、懲戒処分を行うか否か、またその内容を決定する上で、非常に重要な判断材料となります。
このように、弁明の機会は、懲戒処分が社会通念上相当であることを基礎付ける役割となり、後の労使間トラブルを未然に防ぐためにも不可欠なプロセスと言えます。
手続きを怠ると懲戒処分が無効になるリスク
「弁明の機会の付与」は、法律で明確に規定された義務ではありません。しかし、過去の裁判例では、懲戒処分における「適正な手続き」の極めて重要な一部として位置づけられています。この手続きを怠ると、懲戒処分の社会的相当性を欠くと判断される可能性があります。
実際に、弁明の機会を付与せずに懲戒処分を実施したケースで、処分が無効とされた裁判例も存在します。特に、就業規則で弁明の機会に関する規定が定められているにも関わらず、これを怠ると、懲戒処分が無効となる可能性が高まります。他方で、就業規則に弁明の機会に関する規定がない場合には、判断が分かれています。

弁明の機会の付与が必要になる具体的なケース
弁明の機会の付与は、法律上の義務ではありません。しかし、懲戒処分の有効性を左右する極めて重要な要素であり、実務上は必須となるケースが多数存在します。
以下では、弁明の機会が求められるケースを紹介します。
懲戒解雇など従業員にとって重い処分を行う場合
懲戒解雇は、従業員のキャリアや生活に重大な影響を及ぼす、会社が行う処分の中で最も重い処分になります。従業員にとって極めて大きな不利益となるため、その決定プロセスには客観的で、かつ、公正性が求められます。もし弁明の機会を付与しないまま懲戒解雇を実行した場合、裁判で手続きの妥当性を欠くと判断され、会社の懲戒権濫用として処分が無効となるリスクが非常に高まります。
また、懲戒解雇だけでなく、出勤停止、降格、諭旨解雇のような従業員の職位や処遇に重大な影響を及ぼす処分についても、同様に弁明の機会を設けることが不可欠です。
ハラスメントなど当事者の言い分が食い違う場合
ハラスメントの事案においても弁明の機会は必須となります。
セクハラをはじめハラスメントの申告を受けた場合、被害者から聞き取りを行い、客観的な証拠を取り付けるなど、ハラスメントに関する事実関係を調査します。
ハラスメントの調査において、行為者に対しても最終的に聞き取りを行います。行為者に対する事情聴取で、申告のあった事実が存在するのか、申告内容に対して弁解があるのかを聞き取ります。行為者に対する事情聴取は、ハラスメントの事実認定において必要となるプロセスとなるだけでなく行為者に対する「弁明の機会」の役割も果たします。
ただし、行為者に対する事実調査を行う際に、ハラスメントの具体的な内容や時期などを特定することなく、抽象的な聞き取りをした場合には、行為者に対して弁明の機会を十分に与えていないと判断されるおそれがあります。そのため、被害者側が行為者に対する聞き取りを控えて欲しいと要望する場合でも、行為者に対して適切な処分をするためには、行為者に対して事情聴取を行う必要性を説明するなどして説得することが必要となります。
就業規則に弁明の機会について定めがある場合
就業規則に「懲戒処分を行う際は、対象となる従業員に弁明の機会を与える」といった規定が明記されている場合、企業はその手続きを遵守する法的義務が生じます。
そのため、就業規則に弁明の機会を付与する定めがあるにもかかわらず、企業が弁明の機会を与えずに懲戒処分を下した場合には、その処分は無効になる可能性が高いといえます。
したがって、懲戒処分を検討する際は、まず自社の就業規則に弁明の機会に関する規定があるかどうかを必ず確認し、その定めに従って慎重に進めることが重要です。
ただ、就業規則通りに弁明の機会が与えられなかったとしても、弁明の機会に代替する意見聴取の機会が与えられている場合には、手続的相当性を欠くものではないとして、処分が有効となるケースもあります。
| 【大阪高等裁判所平20年11月14日】 懲戒委員会の全体において弁明の機会が与えられなかったとしても,調査部会において事情聴取がされ,また,懲戒処分の決定機関である理事会において,本人に弁明の機会が与えられた場合には,弁明の機会の付与に関して,本件停職処分に至る手続が違法であるとはいえないというべきである。 控訴人は,懲戒委員会の調査部会(懲戒委員会委員7名のうち教頭1名及び教諭2名で構成)の事情聴取において,本件飲酒がされた当時の経過について詳細に聴取されている。そして,控訴人は,理事会小委員会において,弁明の書面を提出するとともに,詳細な質問を受けて,懲戒事由に関する意見を述べており,理事会において弁明の機会が充分に与えられたと認められる。 |
【3ステップで解説】弁明の機会を付与する具体的な進め方
弁明の機会の付与は、企業が公正な懲戒処分を行い、将来的な労使トラブルや訴訟リスクを回避する上で不可欠なプロセスです。
この手続きを適切に踏まなければ、たとえ事実調査に十分な時間を費やしたとしても、懲戒処分自体が無効と判断される可能性があります。
そこで以下では、人事担当者が実務で弁明の機会を付与する際に迷うことのないよう、具体的な進め方を3つのステップに分けて詳しく解説します。
ステップ1:弁明通知書を交付する
弁明の機会を付与する最初のステップは、対象となる従業員に対して、弁明の機会を付与することを通知することです。この通知の内容が曖昧だと、従業員は何について弁明すべきか明確に理解できません。そのため、弁明通知書には、以下の点を具体的に明記する必要があります。
- 懲戒処分の根拠となる就業規則の条項
- 予定している懲戒処分の内容
- 懲戒処分の原因となる具体的な事実
- 弁明の機会の方法や日時
これにより、従業員は自身の立場や言い分を整理し、的確な弁明準備を進めることができます。
この通知は、後のトラブルを避けるためにも必ず書面で行うべきです。口頭での通知では「言った、言わない」といった争いになる可能性があり、客観的な証拠として残せません。そこで、弁明通知書を本人に直接手渡し、受領サインをもらう方法や、内容証明郵便で送付する方法が考えられます。
ステップ2:弁明の機会を実際に設ける(書面または口頭)
弁明書の提出期限と方法を告知した後、従業員から実際に弁明を受ける段階です。
弁明の方法として書面が選択された場合は、従業員が作成した「弁明書」を期日までに受理します。弁明書は、企業側が指摘した事実に反論したり、自身の行為に関する事情を説明したりするための重要な書類です。
一方、口頭での弁明となる場合は、面談形式で実施します。面談を行う際には、以下の点に留意しましょう。
すなわち、人事担当者など、会社側からは複数名(多くても3人程)で臨むようにしてください。1対1の面談は「言った、言わない」といったトラブルに発展しやすいため、避けるのが賢明です。
また、面談の態様としては、企業側で決めつけをしたり、威圧的な態度を示さないことはもちろん、必要があれば社員に対して関係資料を開示しながら、対象社員の言い分に傾聴する必要があります。さらには、面談の時間は、長時間に及ばないように注意し、社員のプライバシーに配慮するため、会議室などの部屋で実施するようにします。加えて、事後的に社員から威迫されたと主張されないように、弁明の機会においては秘密録音をしておくことも大切です。
ステップ3:提出された弁明内容を十分に検討する
従業員から提出された弁明書や口頭による説明は、懲戒処分を決定する上で極めて重要な判断材料となります。
企業は、これらの弁明内容を予断や偏見なく、中立的かつ客観的な立場で精査する必要があります。弁明内容の検討を通じて、企業が認識していなかった新たな事実が判明したり、事実誤認が明らかになったりするケースがあります。そのため、状況に応じて追加のヒアリングや証拠の確認といった再調査を検討することもあります。特に懲戒解雇のような重い処分を検討する場合や、従業員から強い反論があった場合には、再度の弁明機会を設けるなど、より慎重な手続きを踏むことが求められます。
こうした調査結果や弁明内容を総合的に判断し、当初予定していた懲戒処分が妥当であるか否かを改めて検討します。従業員の反省の度合いや情状酌量の余地なども考慮した上で、最終的な処分内容を決定します。
適切な対応のために知っておきたい注意点とQ&A
以下では、弁明の機会を付与する際に企業側が特に留意すべき点や、頻繁に寄せられる質問について、Q&A形式も交えながら具体的に解説していきます。
弁明のための準備期間は十分に設ける
懲戒処分の対象となる従業員に弁明の機会を与える際には、その準備期間を適切に設けることが非常に重要です。
従業員が自身の主張を効果的に行うためには、会社が提示した事実関係を詳細に確認し、反論のための十分な時間が必要です。もし準備期間が不当に短ければ、従業員は実質的に弁明の機会が与えられなかったと判断され、手続きの公正性が欠けていたとして、懲戒処分自体が無効となるおそれがあるため注意が必要です。
法律で具体的な日数の定めはありませんが、一般的には1週間から2週間程度が目安かと考えます。しかし、この期間はあくまで目安であり、個別の事情に応じて柔軟に設定すべきでしょう。
従業員が弁明を拒否した場合はどうする?
従業員が弁明の機会を拒否した場合でも、企業は、これまでに把握している客観的な証拠に基づいて懲戒処分の手続きを進めることができます。これは、従業員が弁明の機会を放棄したと見なされるためです。
しかし、弁明がなかったことをもって、対象となる行為を従業員が認めたと安易に判断するのは適切ではありません。あくまで、会社がこれまでに収集した事実や証拠の範囲内で、公正な判断を下す必要があることを認識しておくべきです。
将来的な紛争において、「弁明の機会が与えられなかった」と従業員に主張されるリスクを避けるためにも、弁明を拒否した事実を客観的に記録しておくことが極めて重要です。
弁明の内容は客観的に記録・保管する
従業員から得られた弁明内容は、その後の労働審判や訴訟といった法的な紛争に発展した際、企業が適正な手続きを踏んだことを証明する重要な証拠となります。
そのため、弁明の内容を客観的な証拠として保全するために、議事録を作成したり、会話録音をするなどの工夫をしておくことが大切です。
まとめ|適切な手続きが労使間のトラブルを予防する
「弁明の機会の付与」は、企業が懲戒処分を行う際の重要な手続きです。弁明の機会を設けなかったために懲戒処分が無効と判断されるケースは少なくありません。また、従業員に自身の言い分を述べる機会を設けることは、企業が事実関係を正確に把握し、誤った判断を下すリスクを回避することにもつながります。
本記事で解説した弁明の機会を付与する手順や注意点を参考にしながら、適切なプロセスを踏んで懲戒処分の手続を進めていきましょう。弁明の機会の手続を含め懲戒処分の手続で不明点があれば、弁護士に相談することを検討してください。