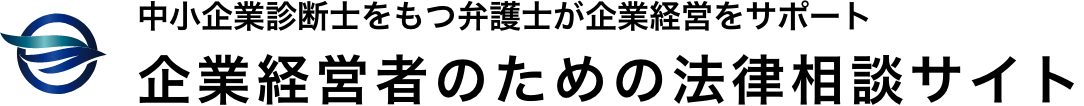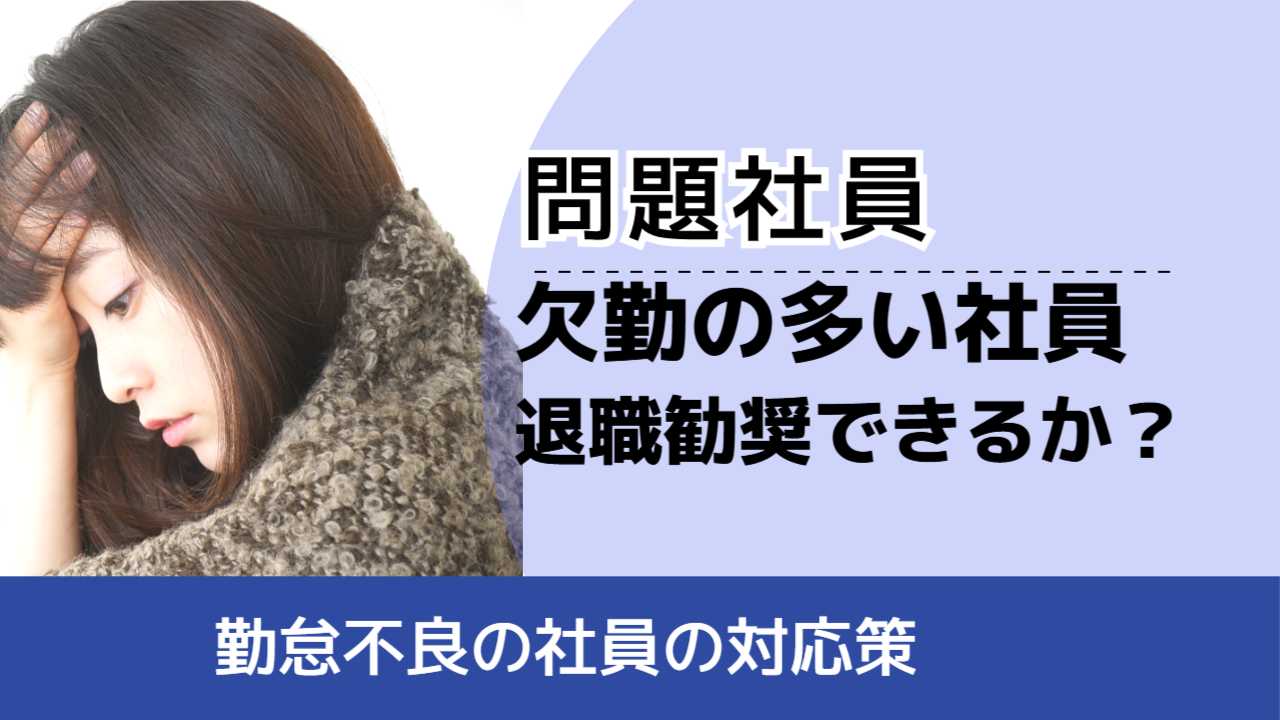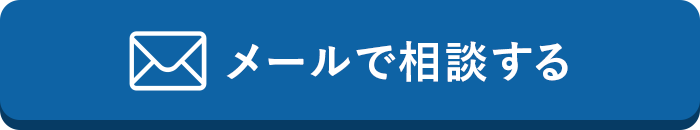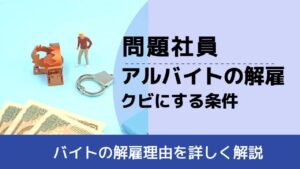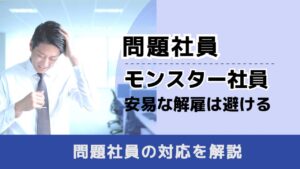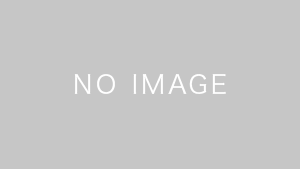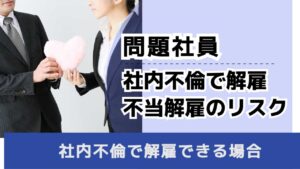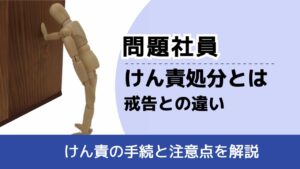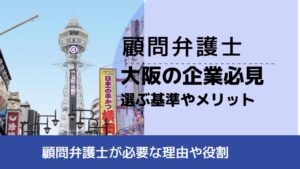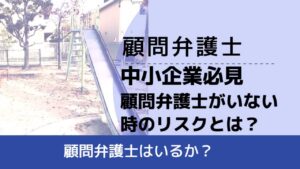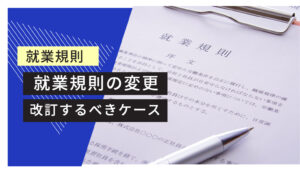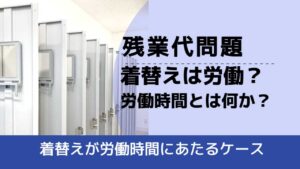欠勤の多い社員がいる場合、ついつい解雇をしてしまいがちです。何度も無断欠勤している場合や長期間にわたって欠勤している場合には、解雇処分することも許容されますが、欠勤が多いことを理由に当然に解雇が有効となるわけではありません。安易に解雇処分をすると、不当解雇となり、事後的に予期せぬ経済的な負担を強いられることも珍しくありません。
この記事では、欠勤の多い社員に対して退職勧奨を行う際の注意点や、適法に進めるための具体的なステップを解説します。また、万が一、解雇という判断に至る場合に、企業が留意すべき点についても詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
欠勤が続く社員への対応でまず確認すべきこと
欠勤が続く社員への対応は、退職勧奨や解雇といった性急な判断を避け、まずは客観的な事実確認から慎重に進めることが不可欠です。安易な対応は、後に労使トラブルへ発展し、会社が不利益を被るリスクを伴います。トラブルを未然に防ぐためには、具体的なアクションを起こす前に、複数の不可欠な確認事項を徹底する必要があります。
以下の項目では、欠勤が続く社員への対応において最初に確認すべき3つのポイントを解説します。具体的には以下の通りです。
- 欠勤の理由と状況を正確に把握する
- 就業規則上の根拠を確認する
- 面談記録や勤怠記録を客観的な証拠として確保する
欠勤の理由と状況を正確に把握する
社員が欠勤を繰り返す場合、まずはその理由と状況を正確に把握することが重要です。体調不良、家庭の事情、無断欠勤など、欠勤の背景によって企業が取るべき対応は大きく異なります。憶測で判断せず、本人から直接事情をヒアリングすることが必要となります。
特に体調不良が理由である場合は、状況を客観的に判断するため、医師の診断書等の資料の提出を求めることも必要です。診断書を求める場合には、就業規則において、診断書を求めることができる規定があるかを確認しておきましょう。
また、以下の客観的な事実を整理し、詳細に記録しておく必要があります。
| ・欠勤が始まった時期 ・欠勤の頻度 ・欠勤の期間 ・本人からの連絡の有無や内容 ・欠勤の理由 |
これらの事実は、今後の指導や退職勧奨、さらには解雇を検討する上で重要な根拠となります。
就業規則上の根拠を確認しておく
退職勧奨や解雇といった対応の正当性を確保するためには、就業規則の確認が不可欠である。退職勧奨自体は就業規則の定めまでは必要ありませんが、懲戒解雇をする場合には就業規則の根拠が必要となります。
就業規則は、従業員の労働条件や職場内の規律を定めたルールブックであり、労使間のトラブルを回避する上で重要な役割を果たすものになります。労働基準法により、常時10人以上の従業員を雇用する事業場には、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。
従業員の欠勤の関係で特に確認しておくべき事項は以下のとおりです。
- 欠勤時の連絡義務や遅刻・早退・欠勤の取り扱いを定めた服務規律
- 懲戒処分の種類とその事由(例えば「正当な理由なく欠勤をしたとき」など)
- 休職制度の有無と適用条件
- 普通解雇の要件
就業規則に明記された規定に基づいて指導や処分を行うことで、企業側の対応が恣意的ではないことを示し、後の法的な紛争に備えることができる。これにより、万が一の不当解雇訴訟などのリスクを低減し、企業を守ることにもつながる。
面談記録や勤怠記録を客観的な証拠として残す
社員とのトラブルを未然に防ぎ、後々の「言った、言わない」といった水掛け論や、企業による不当な対応だと訴えられるリスクを回避するためには、客観的な記録を正確に残すことが非常に重要です。これは、指導や退職勧奨のプロセスにおいて、企業側の対応が適法かつ適切であったことを証明する根拠となります。
まず、欠勤の事実を証明する勤怠記録は、正確に保管する必要があります。タイムカードの打刻データや勤怠管理システムの記録は、欠勤日や勤務時間を客観的に示す重要な証拠となります。
次に、社員と面談を実施した際は、その内容を詳細に記録します。面談記録に含めるべき主な項目は以下の通りです。
- 面談日時
- 出席者
- 指導内容
- 社員からヒアリングした欠勤理由
- その後の改善に向けた意向
可能であれば、記録内容を社員に確認してもらい、署名を得ることで、証拠の信用性を担保することができます。その際、感情的な表現は避け、事実のみを客観的に記載することが重要です。また、これらの記録は時系列に沿って整理し、一貫性を持って保管することが求められます。

退職勧奨の前に踏むべき段階的な指導プロセス
社員の欠勤が続く場合、いきなり退職勧奨を行うことは控えるべきです。そのため、段階的なプロセスを踏むことが必要です。
ステップ1:原因のヒアリングと改善に向けた口頭指導
まず、欠勤が続く社員と面談の場を設け、高圧的な態度を避け、欠勤の具体的な理由を丁寧にヒアリングすることが不可欠です。
体調不良、家庭の事情、職場の人間関係など、その背景は多岐にわたるため、原因によって企業が取るべき対応は大きく異なります。頭ごなしに叱責するのではなく、社員の意見を真摯に受け止め、傾聴する姿勢が重要となるでしょう。
ヒアリングで得られた情報に基づき、欠勤に正当な理由がないことが分かれば、勤怠不良が業務や他の従業員に与える影響を客観的に説明します。その上で、勤怠不良の改善を求めるとともに、業務量の調整、配置転換の検討などを提示することで会社として協力できる姿勢を示します。
この面談で話し合われた内容は、後々のトラブルを避けるためにも必ず客観的な記録として残してください。
ステップ2:改善が見られない場合の書面による注意・警告
口頭指導をしても、欠勤を繰り返すなど、改善が見られない場合、書面による注意指導を行います。
書面には、具体的な欠勤期間や日数、過去の指導内容、そして勤怠不良によって生じている具体的な悪影響を明確に記載します。また、会社が求める改善を具体的に示し、現状とのギャップを埋めるための明確な指示を盛り込むことも検討します。改善が見られない場合は、就業規則に基づく懲戒処分など、次の段階に進む可能性があることを明記し、本人が事態の重大性を認識できるよう促しましょう。
書面は、面談の場で本人に直接手渡し、内容を読み聞かせることで確実に伝達することが望ましいです。本人から署名を得ておくことで、書面を受け取ったことを証明できるようにしておきます。もし本人が受領を拒否した場合は、その事実を客観的に記録に残したり、内容証明郵便で送付するなどの対応を検討し、会社側の対応が適切であったことを証明する証拠を確保することが大切です。
ステップ3:懲戒処分(譴責・減給など)の検討
口頭指導や書面による警告後も無断欠勤等が改善されない場合、懲戒処分を検討します。
懲戒処分には、戒告や譴責(始末書の提出を求めて将来を戒める処分)、減給、出勤停止など、その重さによって段階があります。
いきなり、減給や出勤停止の懲戒処分を行うことは重過ぎると判断される可能性もあるため、まずは比較的軽めの処分である戒告や譴責を検討しましょう。ただ、無断欠勤の期間が長い、回数が多いといった悪質な場合には、重めの処分をすることもあり得るでしょう。
処分の重さを決定する際は、以下の点を総合的に考慮し、社会通念上相当と認められる範囲内で決定することが求められます。
- 欠勤の頻度
- 業務への影響
- 本人の反省度合い
- 過去の事例
- 過去の処分歴
懲戒権の濫用とならないよう、慎重な判断が求められます。
欠勤社員に退職勧奨を行う際の適切な進め方
段階的なプロセスを経ても社員の状況が改善されない場合、退職勧奨が検討されます。しかし、退職勧奨は、あくまでも、従業員自身の自由な意思に基づき退職を促すものであり、これに応じるか否かは従業員が自由に決定できます。
そのため、会社が退職勧奨に応じない従業員に対し、執拗に退職を迫ったり、不当な心理的圧力を加えたりすることは、違法な退職強要と見なされる可能性があり、損害賠償請求や退職の無効化といったリスクを伴います。
そこで、退職勧奨は、法的なリスクを回避し、円満な解決を目指すためにも、慎重かつ適切な手順で進める必要があります。
退職勧奨を切り出すタイミングの見極め
退職勧奨は、口頭指導や書面による厳重注意、懲戒処分といった段階的な指導を尽くしてもなお、従業員の欠勤状況に改善が見られないと客観的に判断できた時点で、初めて検討されるべきタイミングです。また、以下の状況も退職勧奨を切り出す適切なタイミングの一つといえます。
- 本人との面談において改善の意思が明確にないと判明した場合
- 欠勤が業務に著しい支障をきたし、回復の見込みがないと判断された場合
適切なプロセスを経ることもなく、いきなり退職勧奨を試みると、かえって社員の反発を招き、労使関係を複雑にしてしまうおそれもあります。
解雇という最終手段を講じる前に、労使双方にとって円満な解決を図る選択肢として、慎重にタイミングを見極めることが重要です。これにより、法的リスクを低減しつつ、職場環境の正常化を目指すことにつながります。
退職強要と見なされないための伝え方と注意点
退職勧奨は、従業員に自発的な退職を促すものであり、一方的な解雇とは性質が異なります。従業員には退職勧奨に応じる義務がなく、拒否する自由があります。
しかし、「退職強要」と評されるような言動は、不法行為として損害賠償請求や退職の無効といった法的リスクを招く可能性があります。具体的には、以下のような行為は避けるべきです。
- 大声で怒鳴る
- 短期間に複数回、または長時間にわたり執拗に面談を繰り返す
- 「辞めなければ解雇する」といった発言で脅す
- 大人数で面談を実施する
- その場で退職届への署名を強要する
面談では、感情的にならず、客観的な事実(勤怠記録など)に基づいて会社の考えを冷静に伝える姿勢が求められます。また、プライバシーが確保された個室で行い、従業員に熟考する時間を与えるためにも「一度持ち帰って検討してください」と促し、その場で決断することを強要しないようにしましょう。面談のやり取りは、日時、出席者、主な発言内容などを詳細に議事録として記録し、万が一のトラブルに備えることが大切です。
退職条件の提示と退職合意書の締結
退職勧奨を円滑に進めるには、社員が退職に応じやすいよう、具体的な退職条件を提示することが有効です。
例えば、退職金の割増、解決金の支払い、一定期間の労働義務の免除、未消化分の有給の買取り、再就職支援の提供などが挙げられます。これらの条件は、企業側に法的な義務があるわけではなく、あくまで円満な合意退職を目指す上での任意の提案であることを明確に伝えましょう。特に割増の退職金や解決金は、退職勧奨に応じてもらうためのインセンティブとして機能します。
口頭での合意だけでは、後々のトラブルに発展する可能性があるため、必ず「退職合意書」を書面で締結することが重要です。退職合意書は、会社と従業員が退職に関する条件などを双方の合意に基づき文書化したもので、法的拘束力を持ちます。これにより、会社と従業員の間で誤解が生じるのを防ぎ、円満な退職を実現します。
退職合意書には、以下の項目を明確に記載しましょう。
| 項目 | 内容 |
| 退職の合意 | 退職日を明記し、労使双方の合意を確認 |
| 離職理由 | 会社都合か自己都合かを明確にする |
| 業務引継ぎ | 最終出社日と業務引継ぎの具体的内容を定める |
| 金銭的条件 | 退職金や解決金の有無、金額、支払い期日を記載 |
| 返却物の確認 | 私物や会社からの貸与品の返却について取り決める |
| 守秘義務 | 退職後の守秘義務継続の有無や範囲を定める |
| 清算条項 | 労使間の権利義務関係を清算し、合意後に金銭請求等を防止する |
中でも「清算条項」は、合意時点で判明している一切の債権債務がないことを、労使双方が確認する重要な条項です。これを明記することで、退職後の不当な金銭請求や新たなトラブルの発生を未然に防止できるでしょう。また、会社側が合意書の内容を分かりやすく説明した上で、従業員がその内容を理解して納得したことを明記しておくことも大切です。
ただ、清算条項を設けたとしても、未払いの残業代までも清算できない可能性もありますので留意するべきです。

解雇処分は退職勧奨に応じない場合の最終手段
仮に社員が退職勧奨に応じない場合、企業が取りうる次の手段として「解雇」が考えられます。
しかし、労働法では解雇権の濫用が厳しく制限されており、解雇は決して容易なものではありません。以下では、欠勤を理由とする解雇が法的に認められる要件や、企業が注意すべき点について詳しく解説します。
欠勤を理由とする「普通解雇」が法的に認められる要件
欠勤を理由に社員を普通解雇する場合、労働契約法第16条に定められている「解雇権濫用法理」に基づき、解雇処分の効力が判断されます。
解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と明記されており、これは判例によって確立されてきた考え方が、労働契約法に明文化されたものです。
解雇の有効性が認められるためには、以下の判断要素を総合的に考慮し、慎重な検討が求められます。
| 判断要素 | 内容 |
| 欠勤の期間や頻度 | 長期間にわたり頻繁に欠勤しているか |
| 改善指導の有無や処分歴 | 会社が改善指導や懲戒処分を十分に行い、改善の機会を与えたか |
| 業務への支障の大きさ | 欠勤によって業務運営に重大な支障が生じているか |
| 社員の改善の見込み | 本人が改善の意思を示さず、改善が見込めない状況にあるか |
たとえ就業規則上、欠勤が解雇事由として規定されていたとしても、安易な解雇は不当解雇と判断されるリスクがあります。
不当解雇とされると、会社が高額の賃金相当額の支払いを命じられるなど、多額の金銭的負担を負うケースも存在します。解雇を検討する際は、必ず弁護士などの専門家に相談し、法的なリスクを十分に検証することが不可欠です。
無断欠勤と体調不良による欠勤での判断の違い
従業員の責任が重い「無断欠勤」の場合、正当な理由のある欠勤と比べると解雇処分が認められる傾向にあります。
就業規則に定められた期間(例:14日以上)を超え、会社への連絡もなく出社の意思が確認できない場合は、労働契約の重大な不履行といえます。
他方で、体調不良による欠勤の場合、まずは休職制度の適用を検討します。休職期間が満了した後も復職が困難と判断された場合には、初めて普通解雇や自然退職を検討することになります。安易な解雇は解雇権濫用と判断されるリスクが高く、休職期間を経ずに解雇したことで無効とされた裁判例も存在します。
不当解雇と判断された場合の企業側のリスク
裁判所で不当解雇と判断された場合、企業は複数の重大なリスクを負うことになります。
最も大きな金銭的リスクは、解雇が無効となることで、社員が解雇されていなければ得られたはずの賃金を、解雇時点に遡って支払う義務が生じる「バックペイ」です。このバックペイは、裁判が長期化するにつれて高額化する傾向にあります。解雇した社員の給与額や解決に至るまでの期間によっては、500万円や1000万円を超える金額になることも稀ではありません。
バックペイ以外にも、弁護士費用の負担が発生する可能性があり、さらに解雇の態様が悪質と判断された場合には、社員への慰謝料の支払いが命じられることがあります。
加えて、企業は不当解雇「ブラック企業」といったイメージが定着し、採用活動が困難になったり、既存社員の士気が低下したりする「レピュテーションリスク」も負うことになります。解雇が無効となった場合、一度関係が悪化した社員を復職させる必要が生じることもあるため、職場環境への悪影響や、関係修復の難しさといった実務上のリスクも避けられません。
これらの多岐にわたるリスクを考慮すると、解雇は極めて慎重に進める必要があります。
| リスク・負担の種類 | 内容と影響 |
| バックペイ | 解雇が無効とされた場合、解雇時点に遡って未払い賃金を支払う義務が生じます。裁判の長期化により、高額な支払いを命じられるケースも存在します。 |
| 弁護士費用 | 訴訟対応にかかる費用で、数百万円程度が必要です。 |
| 慰謝料 | 解雇の態様が悪質と判断された場合、慰謝料の支払いが命じられることがあります。 |
| レピュテーションリスク | 「ブラック企業」という企業イメージの定着により、採用活動が困難になったり、既存社員の士気が低下したりする可能性があります。 |
| 従業員のモチベーション | 一度関係が悪化した社員を復職させることで、職場環境が悪化したり、人間関係の修復が困難になったりするなど、実務上の課題が生じます。 |
欠勤社員への対応で特に注意すべき点
これまで解説した一般的な対応フローに加え、社員の個別事情によっては、より慎重な対応が求められるケースが存在します。以下の項目では、特別なケースにおける具体的な対応方法と、企業が留意すべき法的な注意点について詳しく解説していきます。
メンタルヘルス不調が疑われる社員への配慮義務
メンタルヘルス不調が疑われる社員が欠勤を続ける場合、企業は「安全配慮義務」を負い、心身の健康と安全を確保するための特別な配慮が求められます。
企業の自己判断で病状を決めつけることは避け、必ず本人の同意を得ながら、産業医や専門医との面談を設定し、客観的な診断に基づいた対応を検討することが重要です。医師の専門的な意見を踏まえることなく、早々に退職勧奨や解雇を進めるのではなく、まずは休職を促し、社員が治療に専念できる環境を優先的に提供することが望まれます。
さらに、社員の負担を軽減するための配慮を検討することも必要となります。具体的な「就業上の配慮」の例としては、以下が挙げられます。
- 業務内容の軽減
- 短時間勤務
- 配置転換
連絡が取れない無断欠勤社員への対応手順
社員が無断欠勤を続け、連絡が取れない場合、企業はまず社員の安否確認を行うべきです。
まず、社員の携帯電話やメールアドレスへ複数回連絡し、返信を求めます。それでも連絡が取れない場合は、就業規則で届け出ている緊急連絡先へ連絡を試み、社員の状況把握に努めましょう。これらの手段でも連絡が取れない場合、最終手段として自宅訪問を検討します。
一連の対応を試みてもなお状況が不明な場合、内容証明郵便で安否確認や出社を求める通知書を送付するという法的な手続きを行います。
これらの対応を経てもなお、無断欠勤が続くのであれば、解雇処分を下すことになります。ただ、社員が所在不明である以上、解雇通知を出すことができません。そのため、公示の方法により解雇処分の通知を出すことになります。
ただ、公示の方法による通知は、簡易裁判所に対して申し立てを行う必要があるなど手続きが煩雑です。このような不都合を回避するために、無断欠勤が一定期間続いた場合には、自動的に退職となる旨の規定を就業規則に定めておくことも大切です。
まとめ:欠勤社員への対応は専門家も交え慎重な手順を
欠勤が続く社員への対応は、企業の安定的な運営と、従業員との良好な関係維持のために非常に重要な課題です。本記事で解説したように、まず欠勤の理由と状況を正確に把握し、就業規則に基づいた指導や記録を徹底することが、その後の対応の基礎となります。このような段階的な対応を経ても改善が見られない場合に初めて退職勧奨を検討し、最終手段として解雇に至るという一連の流れを理解しておくことが重要です。
特に注意すべきは、退職勧奨や解雇といった措置が、従業員から「不当である」と訴えられるリスクです。労働法では解雇権の濫用が厳しく制限されており、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効となります。不当解雇と判断された企業が多額の金銭的負担を負うケースも少なくありません。このようなリスクを回避するためには、法的な観点から常に慎重な判断が求められます。
企業単独で欠勤社員への対応を進めることに不安を感じる場合や、具体的な法的判断が必要となる場面では、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。早期に弁護士の知見を取り入れることで、企業と従業員の双方にとって最善の道を見出すことができるでしょう。