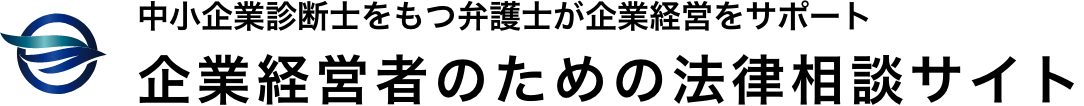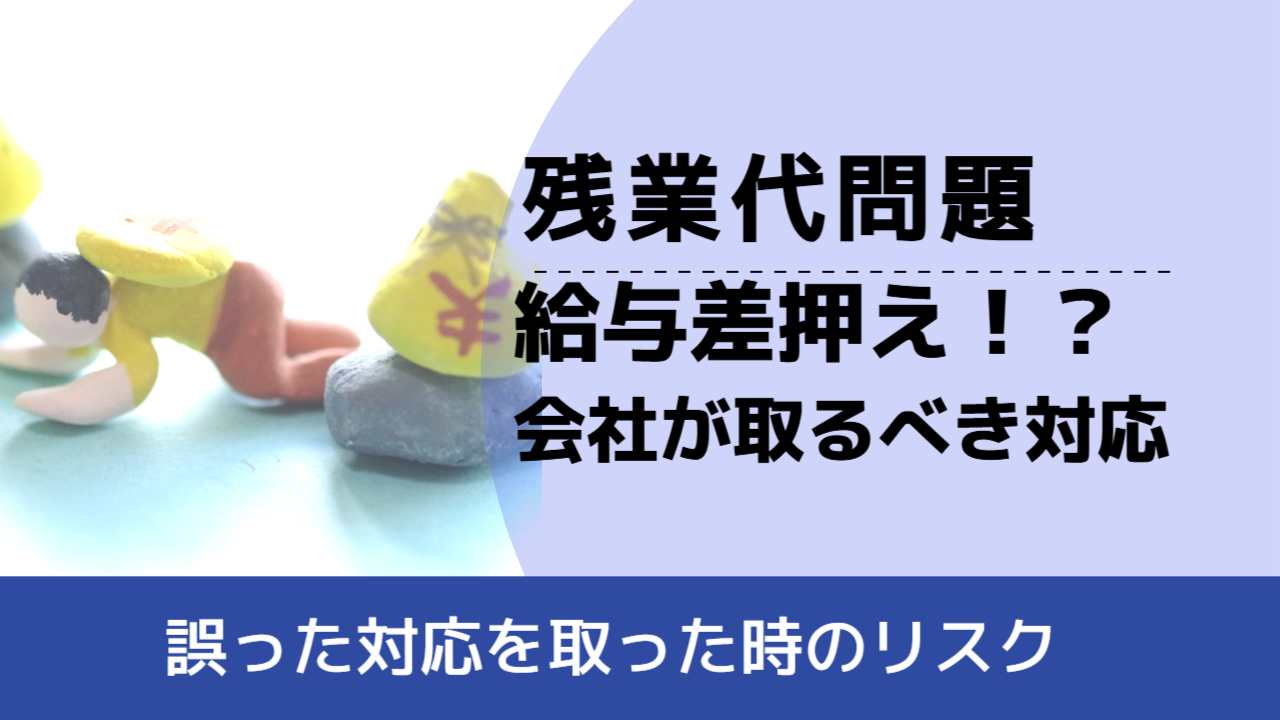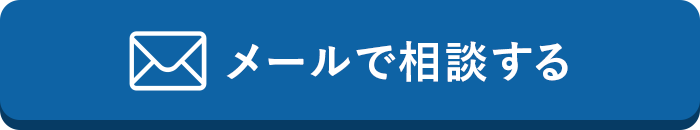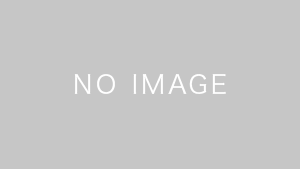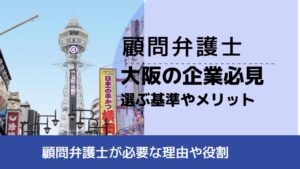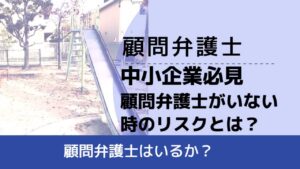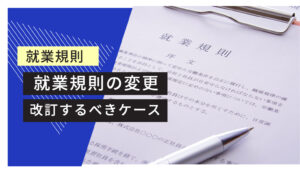従業員の給料差し押さえ通知が届いた際、人事・経理担当者は迅速かつ適切に対応する必要があります。会社として、まず何をすべきか、どのような法的義務があるのか、戸惑う方も少なくないでしょう。
本記事では、給料差し押さえ通知が届いた際の会社側の対応について、人事・経理担当者が知っておくべき知識と具体的な手順を徹底解説します。
まず確認!給料差し押さえにおける会社の法的立場とは
裁判所から届く債権差押命令は、従業員の給与から債務の一部を差し押さえるよう命じるものであり、会社には法律に基づいた適切な対応が求められます。以下の項目では、会社が取るべき対応を解説します。
給料差押えは「債権執行」という法的手続き
給料差し押さえは、法的な強制執行手続きの一つである「債権執行」に該当します。債権執行とは、債権者が裁判所の判決など(債務名義)に基づいて、債務者の債権から強制的に債権回収する手続きを指します。その対象となる財産は多岐にわたります。預貯金、給与債権、請負代金債権などが挙げられます。
この債権執行の中でも、従業員が会社に対して有する「給与債権」を差し押さえる手続きが「給与差押さえ」です。具体的には、債権者からの債権差押の申立てを受けた裁判所が、第三債務者である会社に対し、従業員に対して給与一部を支払うことを禁じた上で、その給与の一部を会社が債権者へ直接支払うよう命じます。この命令には法的拘束力があるため、会社はこれに従う義務があります。
会社は「第三債務者」として義務を負う
会社は、裁判所から「債権差押命令」が送達されると、法的な義務を負う第三債務者となります。
この命令に基づき、会社は民事執行法第145条により、従業員への給与の一部支払いを差し止め、債権者へ直接支払う義務が生じます。これは会社の意思で拒否したり、従業員に同情して命令を無視したりできるものではありません。
| 関係者 | 立場 | 役割 |
|---|---|---|
| 債権者 | お金を貸した側 | 債務者から債権を回収します |
| 債務者 | 借金をしている人(従業員) | 債権者にお金を返す義務があります |
| 第三債務者 | 債務者に給与を支払う義務がある人(会社) | 裁判所の命令に基づき、債務者の給与の一部を債権者に支払います |

【3ステップ】裁判所から「債権差押命令」が届いた際の初動対応
裁判所から「債権差押命令」が届くと、人事・経理担当者の方は突然の通知に戸惑われるかもしれません。しかし、会社は「第三債務者」として、法律に基づき、適切な対応が求められます。
以下では、債権差押命令を受け取った際、人事・経理担当者が冷静かつ正確に対応できるよう、具体的な初動対応を3つのステップに分けて詳しく解説します。
ステップ1:送られてきた書類の内容を正確に確認する
裁判所から届いた書類の内容を正確に確認することは、その後の適切な対応を進める上で非常に重要です。具体的には、以下の項目を確認してください。
- 書類の種類:「債権差押命令正本」であること。その控えを保管してください。
- 当事者目録:債権者、債務者(従業員)、第三債務者である自社の名称や住所に誤りがないかを正確に把握してください。
- 請求債権の金額:差し押さえの対象となる請求債権の元本、利息、遅延損害金といった内訳を理解し、会社が支払うべき総額を明確に把握してください。
- 陳述書の提出期限:同封されている陳述書の提出期限を確認してください。原則として、差押命令受領後2週間以内に陳述書の提出が求められます。
ステップ2:従業員本人へ事実確認と今後の流れを説明する
裁判所から債権差押命令が届いたら、従業員本人への説明を行うようにします。会社側には、従業員本人に差押命令が届いた旨を通知する義務まではありませんが、①トラブルを防止するために従業員本人に差押命令が届いた、②請求債権に心当たりがあるのか、③会社が「第三債務者」として法的な対応義務を負うため、給与の差し押さえ手続きに応じなければならないことを説明することが望ましいといえます。説明する際には、個室を用意するなどプライバシーに配慮した場所で、冷静かつ丁寧に事実を伝えることが求められます。
会社には、従業員に債権差押命令が届いたことを通知する法的な義務はありませんが、後のトラブルを避けるためにも、対面での丁寧な説明が推奨されます。
ステップ3:期限内に「陳述書」を裁判所へ返送する
裁判所から送付される「陳述書」は、会社(第三債務者)が裁判所に対し、従業員の給与債権に関する状況を報告するための重要な書類です。この陳述書によって、会社は差し押さえの対象となる給与債権が存在するか、その金額はいくらか、他に差押えをしている債権者がいないかを回答する義務を負います。
陳述書には主に以下の項目を記載します。
- 給与債権の有無と金額:従業員への給与支払いの有無、差し押さえ可能な給与額を具体的に示します。
- 支払いの意思:差し押さえ命令に従い、債権者への支払いまたは供託に応じる意思があるかを示します。
- 他の差し押さえの有無:他の差押債権者がいる場合には、その状況を記載します。
陳述書は、債権差押命令の送達を受けてから2週間以内に返送しなければなりません。期限を過ぎてしまうと、手続きの遅延だけでなく、会社が不利益を被る可能性があります。また、陳述書に虚偽の内容を記載したり、提出を怠ったりした場合には、会社が債権者から取立訴訟を提起されるなど、法的なリスクを負うことになりかねません。
差し押さえできる給与額の計算方法をわかりやすく解説
民事執行法に基づき、給与の差押え可能額に上限が設けられています。これは、差し押さえ後も従業員が最低限の生活を送れるよう保障するためです。
以下では、差し押さえできる給与額の計算方法をわかりやすく解説します。
計算の基本となる「手取り給与額」の算出方法
給与の差し押さえ額を計算する上で、まず基準となる「手取り給与額」を正しく理解することが重要です。給与差押えは、手取り給与額の4分の1または2分の1に制限されているからです。また、この手取り給与額は、実際に従業員の銀行口座に振り込まれる金額とは異なるため、注意が必要です。
給与の差し押さえにおける「手取り給与額」は、「総支給額(額面給与)から法定控除額を差し引いた金額」と定義されます。
法定控除額には、税金と社会保険料など、法律によって給与から天引きが義務付けられている項目が該当します。これらの税金や社会保険料を控除した後の金額が、差し押さえ額の計算対象となる「手取り給与額」となるのです。
一方で、財形貯蓄、従業員持株会の積立金、互助会費といった項目は、会社が任意で控除しているものです。これらは、差し押さえ額を計算する際の手取り給与額を算出するにあたり、総支給額から差し引いてはならない項目であり、特に注意が必要です。
原則的な差押可能額の計算式(4分の1ルール)
民事執行法第152条により、従業員の手取り給与額の4分の3に相当する部分は差し押さえが禁止されており、残りの4分の1のみが差し押さえ可能となります。
このルールが適用されるのは、手取り給与額が「44万円以下」の場合です。具体的に、手取り給与額が20万円の従業員の場合を例に計算してみましょう。
このように、手取り給与が20万円の場合、会社は債権者に対して5万円を支払い、残りの15万円を従業員本人に支払うことになります。この計算方法は、従業員の生活保障を考慮しつつ、債権者の権利も守るために設けられています。
手取り額が44万円を超える場合の計算方法
従業員の手取り給与額が44万円を超えていれば、差し押さえ可能な金額は、一般的な「4分の1ルール」とは異なる金額となります。この場合、手取り給与額から33万円を差し引いた残りの全額が差し押さえの対象となります。
具体的には、「手取り給与額 - 33万円 = 差し押え可能額」となります。
例えば、手取り給与額が100万円の場合、100万円から33万円を差し引いた67万円を差押えすることができます。会社は67万円を差押債権者に対して支払い、残りの33万円を従業員本人に支払います。
養育費や婚姻費用など、差押範囲が異なるケースも
給与の差し押さえには、原則的な計算方法とは異なる例外的なケースが存在します。特に、養育費や婚姻費用といった特定の債権においては、その性質を考慮し、それぞれ異なる差押範囲や計算方法が定められています。
養育費や婚姻費用などの「扶養義務等に係る定期金債権」の場合、子どもの生活に直結する重要な債権であるため、民事執行法に基づき、手取り給与額の2分の1まで差し押さえることができます。例えば、手取り給与額が20万円の従業員であれば、10万円が差し押さえの対象となります。
将来分の養育費や婚姻費用の差押えもできる
養育費や婚姻費用については、その一部に不払いがあれば、支払期限が到来していないものについても給与の差押えが認められています。
本来、強制執行は、支払期限が到来していなければ行うことはできませんが、養育費や婚姻費用などの定期金債権については、特例として支払期限が到来していなくても差押えすることが認められています。
そのため、債権者は、期限の到来していない将来の養育費や婚姻費用についても、一度差押えの申立てをしておくことで、その都度差押えの申立てをすることなく、給与から将来分の養育費や婚姻費用を回収することができます。
第百五十一条(継続的給付の差押え)
給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。
第百五十一条の二(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
引用 e-gov
差し押さえた給与の支払い・供託手続きの流れ
給与の差し押さえ額の計算が完了したら、次にその差し押さえた給与をどのように処理するかが重要なステップです。
以下の項目では、給与差押えが1件の場合と、複数の差し押さえが競合した場合の各手続きについて、それぞれの具体的な流れを詳しく解説します。
債権差押命令が1件の場合:債権者への支払い
債権差押命令が1件のみ届いた場合、会社は算定した差押可能額を直接債権者へ支払うのが原則です。
債務者である従業員に対して差押命令が送達されてから1週間が経過すると、債権者は会社(第三債務者)から給与を取り立てることが可能となり、そのため、会社は債権者から振込先口座の指定を受けることになります。
具体的な支払い方法としては、債権者から指定された振込先口座宛に給与支払日に合わせて振込手続きを行うのが一般的です。また、供託所に供託する方法もありますが、差押債権者が複数いない場合には、直接指定口座に振り込むことが多いです。
差押額を債権者に支払った後、その金額を控除した残りの給与は、通常通り従業員本人に支払います。なお、債権者への振込手数料は、一般的に債権者の負担です。そのため、会社は、差し押さえた金額から手数料分を差し引いて債権者に送金できます。
既に給与振込をしている場合
会社が従業員の給与振込口座に振込予約をした後に差押命令の送達を受けた場合です。
このような場合でも、振込予約を撤回することが著しく困難であるなどの特段の事情がなければ、従業員に対する給与振込を差押債権者に対抗することができないと解されています。
振込予約をしてから給与支払日までに差押命令の送達を受けた場合には、二重払いを防ぐためにも振込先銀行に対して、振込依頼の撤回を速やかに行う必要があります(最高裁平成18年7月20日判決)。
複数の差し押さえが競合した場合:「供託」の手続きが必要
同一従業員に対して複数の債権者から給与の差し押さえ命令が届き、差し押さえ可能な金額が債権総額に満たない状態を「差押えの競合」と呼びます。
このような状況で会社が特定の債権者に給与を支払ってしまうと、他の債権者から再度支払いを求められる「二重払い」のリスクが生じる可能性があります。
こうした事態を避けるため、会社(第三債務者)には、差し押さえた給与を直接債権者へ支払うのではなく、管轄の法務局(供託所)に預ける「供託」の手続きが義務付けられています。
供託の具体的な手続きは、以下の通りです。
- まず、会社所在地を管轄する供託所を確認します。
- 次に、「供託書」を作成し、必要事項を記入の上、法務局に提出します。
- 供託書が受理された後、差し押さえた金銭を法務局に納付することで、供託手続きが完了します。
供託後に必要な「事情届」の提出
会社が法務局へ供託した際、会社(第三債務者)は、供託手続きが完了したことを債権差押命令を発付した裁判所(執行裁判所)へ報告する義務があります。この報告に必要な書類が「事情届」です。
会社は供託金を納めた後、供託書正本と一緒に、事情届を裁判所に提出します。裁判所は事情届の提出を受けて、差押債権者に対する配当手続を行うことになります。
差し押さえられた従業員への対応と注意点
会社側は、法令を遵守した対応はもちろんのこと、従業員の状況に応じた適切な対応が求められます。
以下では、給料を差し押さえられた従業員に対する会社の対応と、特に注意すべき点を具体的に解説します。
給料差し押さえを理由に解雇することは原則できない
従業員が給料の差し押さえを受けた場合でも、会社がこれを理由に解雇することは原則としてできません。
解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」と判断されると無効となります。給料の差し押さえは、従業員の私生活上の債務整理に関わる問題であり、直ちに業務遂行能力や会社の秩序に影響を与えるとは言えないため、解雇の正当な理由とはなりにくいでしょう。
ただし、極めて例外的なケースとして、懲戒解雇が認められる可能性も生じます。しかし、これはごく限られた状況であり、安易な解雇判断は不当解雇として従業員から訴訟を起こされる大きなリスクを負うことになります。
従業員のプライバシー保護を徹底し、情報共有は最小限に
従業員の給料差し押さえに関する事実は、極めてデリケートな個人情報です。社内で不必要に情報が共有・拡散されると、従業員の心理的な負担が増大し、職場の人間関係や評価に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、会社としては従業員のプライバシー保護に十分配慮し、情報が拡散されないように情報管理を徹底することが求められます。
この情報は、給与計算や債権者への支払い手続きを担当する人事・経理部門の担当者といった、業務上不可欠な最小限の範囲に限定して共有するべきです。もし情報管理を怠り、従業員のプライバシーが侵害された場合、会社は従業員から損害賠償を請求される法的リスクを負います。
従業員との面談で状況をヒアリングする際のポイント
給料の差し押さえに関する従業員との面談は、デリケートな情報を取り扱うため、慎重な姿勢が求められます。
もし従業員と面談をする場合には、面談は、プライバシーが確保された個室で行うのが適切です。感情的にならず冷静な態度で、陳述書作成に必要な情報を丁寧にヒアリングします。会社としては、差押債権者への支払額や支払時期を具体的に説明することで、従業員の不安を取り除きましょう。
さらに、弁護士などの専門家への相談状況を確認し、必要に応じて公的な相談窓口の情報を提供するなどして、従業員の生活再建に向けたサポートすることも大切かもしれません。
会社の対応を誤った場合のリスク
裁判所からの差押命令に対し、適切な対応を怠ったり、誤った判断を下したりすると、会社は法的な責任を追及され、予期せぬ金銭的損失を被る可能性があります。このセクションでは、会社が給料差し押さえの手続きにおいて、具体的にどのようなリスクに直面する可能性があるのかを詳しく解説します。
二重払いのリスク:差押命令に違反して給与を支払った場合
裁判所から「債権差押命令」が届いたにもかかわらず、会社が差し押さえの対象となる給与を誤って従業員本人に支払ってしまった場合、いわゆる「二重払い」のリスクが生じます。差押命令は、第三債務者である会社に対し、従業員へ差し押さえた給与の支払いを法的に禁止する効力を持ちます。
もしこの命令に違反して従業員に給与を支払ったとしても、債権者に対するその支払いは法的に無効と見なされます。結果として、会社は既に従業員に支払ってしまった金額に加え、さらに債権者からも同額の支払いを請求されることになります。これは、本来一度の支払いで済むはずの金銭を、会社が二重に支払う義務を負うことを意味します。
損害賠償のリスク:陳述書に虚偽の記載をした場合
会社が裁判所に提出する陳述書には、従業員の給与債権の有無やその金額などの重要な情報を記載する必要があります。
この陳述書に故意または過失による虚偽の記載をした場合、会社(第三債務者)は債権者から損害賠償を請求されるリスクを負うことになります。
具体的な虚偽記載の例としては、従業員の給与額を実際よりも低く記載するケースや給与債権があるにも関わらず無いと回答するケースが挙げられます。
このような虚偽の記載により、債権者が本来回収できたはずの金額を回収できなかった場合、会社はその損害額について賠償責任を負うことになります。
対応を拒否・無視した場合に起こりうること
裁判所から送達された債権差押命令を会社(第三債務者)が拒否したり無視したりした場合、債権者から「取立訴訟」を提起される可能性があります。
これは、債権者が会社に対し、差し押さえるべき給与の支払いを直接求める訴訟手続です。
万が一、この取立訴訟で会社が敗訴した場合、たとえ既に従業員へ給与を支払っていたとしても、会社は自社の財産から債権者へ改めて支払う義務を負うことになります。これは会社にとって、本来不必要な純粋な金銭的損失を意味し、二重払いのリスクを招くことになります。
さらに、取立訴訟に発展した場合、本来支払うべき金額に加え、訴訟にかかる費用が会社に発生します。これらの費用は会社にとって大きな負担となり、場合によっては遅延損害金も加算されるため、会社の損失は不必要に拡大するおそれがあります。
給料差し押さえに関するよくある質問
以下では、給与差押えに関係する疑問に対し、Q&A形式で分かりやすく解説していきます。
Q.差し押さえはいつまで続くのですか?
給与の差し押さえは、原則として、対象となる債権の元金、遅延損害金、および強制執行にかかった費用を合わせた全額の支払いが完了するまで継続します。
差し押さえが途中で終了するケースとしては、まず債権者から裁判所に「取下書」が提出された場合が挙げられます。また、従業員が自己破産や個人再生といった債務整理手続きを行った場合にも、差し押さえは終了します。
Q.ボーナスや退職金も差し押さえの対象になりますか?
ボーナス(賞与)や退職金も、「給料債権」の一種とみなされるため、差し押さえの対象となります。
ボーナス(賞与)が差し押さえの対象となる場合、その計算方法は通常の給与と同様になります。ボーナスの手取り合計額を算出し、その金額に基づいて差し押さえ可能な額を計算します。
一方、退職金についても差し押さえの対象となりますが、その計算方法には注意が必要です。退職金の場合、通常の給与やボーナスとは異なり、「手取り額が44万円を超える場合に33万円を差し引いた全額」という計算ルールは適用されません。
Q.従業員が差し押さえ中に退職した場合、どうすればよいですか?
従業員が給料の差し押さえを受けている最中に退職した場合、会社は給与の支払い義務がなくなるため、原則として、それ以降の給与に対する差し押えも終了します。この際、会社は、従業員の退職に伴い、差し押さえの対象となる給与債権が存在しなくなったことを、速やかに債権者へ通知する必要があります。
ただし、退職時に退職金が支払われる場合は、その退職金も給与と同様に差し押さえの対象となるため注意が必要です。
給与差押えの問題は難波みなみ法律事務所へ
従業員の給料差し押さえ通知への対応を誤ってしまうと、会社は損害賠償請求や二重払いといった予期せぬ法的リスクを負う可能性があるため、正確な知識に基づいた対応が求められます。
手続きの正確性はもちろんのこと、対象となる従業員のプライバシー保護も徹底することが不可欠です。給料差し押さえに関する情報は極めてデリケートな個人情報であり、業務上必要な最小限の範囲に限定して共有し、情報漏洩を防ぐ厳重な管理体制を構築することが求められます。さらに、給料の差し押さえのみを理由とした解雇などの不利益な扱いは、原則として認められない点も理解しておくべきでしょう。