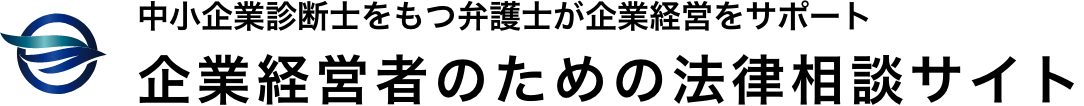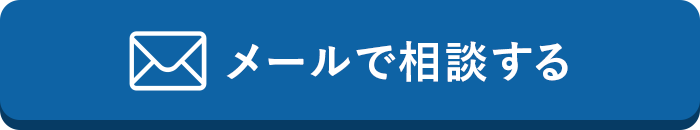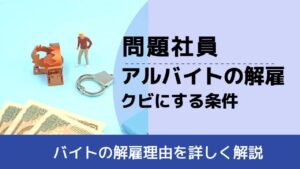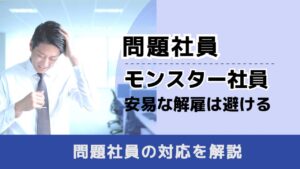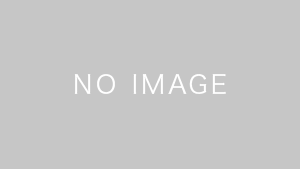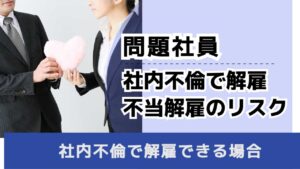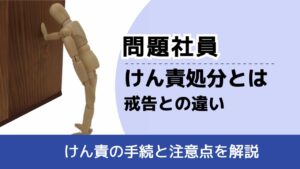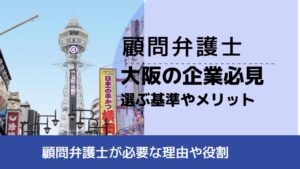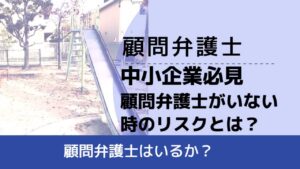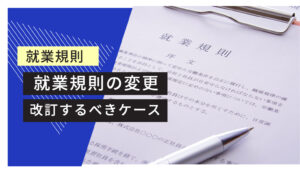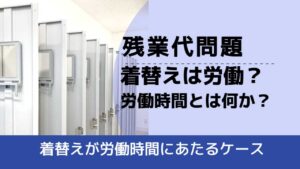会社の秩序を乱す「嘘つき社員」の存在は、業務にも支障をきたす深刻な問題です。特に、虚偽の報告は経営判断を誤らせる可能性もあり、企業にとって大きなリスクとなります。
では、職場でそのような問題社員に対し、処分は可能なのでしょうか? また、実際に嘘が発覚した場合、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。
本記事では、虚偽報告を行った社員への処分について、具体的な対応手順と法的リスクを詳しく解説します。
嘘つき社員を放置することで生じる3つのリスク
従業員による些細な嘘や虚偽報告は、つい「大したことない」と見過ごしてしまいがちです。しかし、そのような安易な判断は、重大なコンプライアンス違反へと発展する恐れがあります。
以下の項目では、社員の嘘を放置することで企業が直面しうる、3つの具体的なリスクについて解説します。
職場全体の規律が乱れる
一人の社員が虚偽の報告をしても許容される職場では、「この会社では嘘をついても問題ない」という悪しき前例を生みかねません。これにより、他の社員の規範意識が低下し、組織全体の倫理観が希薄になる恐れがあります。規範意識の欠如は、不正行為や違法行為への抵抗感を薄れさせ、最終的にコンプライアンス違反へと繋がる可能性があります。
また、嘘が黙認される社内文化は、勤怠管理や経費精算といった社内ルールの軽視へと波及させます。正直に業務に取り組んでいる社員は「嘘をついた方が得をする」と感じ、不公平感から組織への信頼を失いかねません。
他の従業員のモチベーションが低下する
社員の嘘や虚偽報告が黙認される職場では、真面目に努力する他の従業員との不公平を生みます。その結果、組織内のチームワークは機能しなくなり、職場の雰囲気は悪化し、働くこと自体へのモチベーション低下につながります。このような状況が続けば、組織全体の士気を低下させ、生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
会社に経済的な損害を与える可能性がある
従業員による虚偽報告は、企業に経済的損害をもたらす可能性があります。直接的な損害の典型例としては、以下のような経費の不正請求が挙げられます。
- 架空請求や水増し請求
- 通勤手当の不正申請
- 経費の私的利用
さらに、タイムカードの不正打刻といった勤怠記録の改ざんは人件費の過大な支払いを引き起こします。また、取引先への虚偽報告が発覚した際に、信頼を失って契約を打ち切られたり、損害賠償請求に発展したりするリスクが考えられます。

社員による嘘・虚偽報告の事例と処分の重さの目安
社員が職場で報告する嘘や虚偽には様々なケースがあり、その内容や会社に与える影響の度合いによって、適切な懲戒処分の重さは大きく異なります。
処分の判断を誤り、不当に重い処分を下してしまうと、従業員から不当解雇などを理由に訴訟を起こされるリスクが生じます。
会社としては、安易な判断は避け、個々の事例に応じた適切な処分レベルを把握しておくことが極めて重要です。
以下では、社員による嘘や虚偽の内容に応じて行うべき処分について解説します。
能力や経験の虚偽申告
会社が人材を採用するに際して、応募者が能力や経験について虚偽の申告をして採用された場合、それを理由に懲戒処分をすることができるかが問題となります。
社員の能力や経験について虚偽申告があっても、直ちに懲戒処分を下すことができるわけではありません。
能力や経験の虚偽申告が重要な経歴の詐称と言える場合には懲戒処分とすることができると解されています。会社が真実の経歴を知っていれば、採用していなかったと客観的に認められる場合に、重要な経歴に該当するものと考えられています。例えば、会社が熟練の溶接工を募集したところ、12年にわたって溶接作業に従事したとの虚偽の申告をしたようなケースでは、重要な経歴詐称として解雇処分が有効となりました。他方で、採用時に求められている能力や経験とは関係のない経歴の詐称であれば、それを理由に懲戒処分に付すことは難しいと言えます。
| 事件名 | 詐称内容の概要 | 判決結果(懲戒解雇の有効性) |
| スーパーバック事件(東京地判昭55.2.15) | 短期大卒を高卒と申告し、職歴の詐称(三度の転職、無職期間、経営歴) | 懲戒解雇有効 |
| ゲラバス事件(東京地判平16.12.17) | 職務に必要なプログラミング能力がないにもかかわらず、能力があるかのように職歴を偽り採用された | 懲戒解雇有効 |
前科がないと嘘の申告をした場合
採用時に前科を秘匿していたことがわかった場合に、それを理由に懲戒処分を付すことができる場合があります。
先ほどと同じように前科が重要な経歴と言える場合には、前科の秘匿は懲戒処分の対象になります。前科は、職場への適応性、企業の信用性の保持、適切な業務遂行の観点から重要な経歴と考えられています。
ただ、個人情報保護法の関係で、前科は要配慮個人情報となるため、本人の同意を得ることなく前科情報を取得することができません。そのため、応募者が回答を拒否する場合には、それ以上の回答を求めることができません。しかし、前科が要配慮個人情報であるからといって、嘘の申告まで許容するものではありませんので、応募者が虚偽の申告をすれば懲戒処分の対象になり得ます。
前職でのトラブルを隠していた場合
前職における非違行為や懲戒処分の事実を告知しなかったことを理由に懲戒処分をすることができるかが問題となります。
前科と同様、前職における非違行為や処分歴が重要な経歴に該当する場合には、懲戒処分の対象になります。
まず、前職の非違行為が横領や背任などの犯罪行為に該当する場合です。たとえ犯罪行為が事件化されずに前科にならなかったとしても、犯罪歴に準じるものとして「重要な経歴」に該当すると判断できる場合もあるでしょう。ただ、犯罪行為の悪質さや被害の程度を踏まえて判断する必要があります。
次に、前職の非違行為がセクハラやパワハラなどのハラスメントに該当する場合です。会社は、ハラスメント防止のために必要な措置を講じる義務を負うこと、ハラスメントを行った者が同様のハラスメントを繰り返す傾向にもあることを踏まえると、前職のハラスメント行為は重要な経歴に該当する可能性があります。ただ、ハラスメント行為が過去にあったとしても、直ちにそれだけで懲戒処分とすることは控えるべきです。ハラスメント行為の悪質さ、被害の程度、懲戒処分の内容、本人の反省の有無や程度、さらに、採用後の業務内容、採用後の勤務態度を踏まえて、過去のハラスメント行為が重要な経歴とまで言えるのかを判断するべきでしょう。
また、労働者は、過去の非違行為について申告を求められた場合には、信義則上、真実を告知する義務を負っているため、虚偽の説明をすれば経歴を偽ったとして懲戒処分の対象となり得ます。他方で、自発的に過去の非違行為を申告する義務までは負わないため、面接時に過去の非違行為の有無を確認されなかった場合に、これを申告しなかったことを理由に懲戒処分とすることは難しいと考えられます。
出張の虚偽報告をした場合
出張に際して、従業員に出張報告書等の提出をさせるケースはよくありますが、この出張報告書に虚偽の記載をした場合には、懲戒処分の対象となります。
ただ、出張時の虚偽報告があったとしても、安易に懲戒解雇をすることは避けるべきです。出張それ自体に問題はなく、虚偽報告は一回のみで、その他に非違行為がなければ、戒告処分や減給に留めておくことが穏当です。他方で、虚偽報告をこれまでに繰り返し行っており、処分歴が複数ある場合には懲戒解雇も想定されます。例えば、私立学校の教頭が修学旅行の引率中にホテルに待機中にゴルフに出かけていたにもかかわらず、学校側にも虚偽報告をしたことを理由に懲戒解雇された事案では懲戒解雇は無効とされました(大阪地判平5年9月29日)。これは修学旅行中に事故等もなく、一回のみの行動で、これ以外の非違行為がないことが考慮されました。
虚偽のハラスメントの申告をした場合
社員が嘘のハラスメントの申告をした場合には、懲戒処分の対象となります。
ただ、すべてのケースで懲戒処分となるわけではありません。虚偽のハラスメントをした動機や目的、虚偽申告によって生じた損害の程度を踏まえて検討することになります。
例えば、上司や同僚に懲戒処分を受けさせるなどの損害を与える目的で殊更に虚偽申告をしたのであれば、悪質性の高い虚偽申告であると、懲戒処分とするべきです。その上、虚偽申告により、申告を受けた社員が重大な処分を受けるなどの損害が生じている場合には、厳しい懲戒処分を検討するべきでしょう。
他方で、社員がハラスメントの被害を受けていると誤信し、誤診することにつき相当な理由がある場合には、懲戒処分とするべきかは慎重に考える必要があります。例えば、セクハラには法的には該当しないものの、これに類する言動が繰り返し行われていたため、セクハラ被害を受けたと誤信する理由があるようなケースです。
虚偽の理由で有給休暇を取得した場合
社員が嘘の理由で有給休暇を取得した場合、懲戒処分の対象となる可能性があります。
本来、有給休暇の利用目的は自由であり、使用者は利用目的について干渉することはできません。しかし、会社は有給申請を受けた時に、事業の正常な運営を妨げると判断すれば、時季の変更を求めることができますが、取得目的を考慮して時季変更権の行使を控える場合もあります。そのため、有給休暇の取得理由には真実を記載することが求められ、取得理由に虚偽がある場合には懲戒事由に該当し得るとされています。
ただ、取得理由の虚偽記載だけで懲戒解雇まで行うことはあまりにも重すぎる処分となるため、厳重注意又は戒告処分といった軽めの対応に留めるべきです。
タイムカードの不正打刻
社員は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録しなければなりません。それにもかかわらず、タイムカードの不正な打刻に及べば、懲戒事由に該当することになります。また、不正な打刻をして、給与を不正に受給していれば、詐欺罪にも該当し得るため、その観点からも懲戒事由に当たることになります。
ただ、不正打刻に対する懲戒処分の選定は、様々な事情を勘案しながら検討する必要があります。
例えば、会社がタイムカードによる労働時間の管理が杜撰であり、不正打刻を黙認している場合には、厳しい処分をいきなり行うことは控えるべきです。
他方で、不正打刻に対して厳正に対処することを周知しているにもかかわらず、不正打刻に及び、給与を不正受給している場合には、懲戒解雇などの厳しい処分をもって臨むべきでしょう。
通勤手当の不正受給
通勤手当の不正受給は、詐欺行為を働き金銭を詐取する行為であり、詐欺罪に該当するため、懲戒事由に該当します。
そうだとしても、通勤手当の不正受給の全てにおいて、懲戒解雇までできるわけではありません。
不正受給が労働者の故意ではなく、過誤により行われている場合には、受給金額やその返済額にもよりますが、懲戒解雇は控えるべきと考えます。他方で、不正受給が労働者の故意により行われており、その期間も長期間に及んでいるために会社の損害額も大きい場合には、労働者の反省や返済額を踏まえながら、懲戒解雇を検討するべきです。
社員の嘘が疑われるときに会社が取るべき4つのステップ
社員の嘘や虚偽報告が疑われる場合、企業には感情的な対応を避け、客観的な事実に基づいた慎重な対応が求められます。
安易な判断や性急な処分は、不当解雇や不当処分として後に社員から訴えられ、法的なトラブルに発展するリスクがあるためです。
以下では、社員の虚偽報告が疑われた際に会社が取るべき具体的な4つのステップを順を追って解説します。
ステップ1:客観的な事実確認と証拠の確保
社員の虚偽報告の疑いがある場合、最も重要となるのは、憶測や感情に流されるのではなく、客観的な証拠や事情に基づいて判断することです。
性急な対応や証拠不十分なままの処分は、手続きの不備と見なされ、法的トラブルに発展するリスクを伴います。不当な処分であると主張され、企業が訴訟リスクを負うケースも少なくありません。また、調査や聴取の方法によっては、かえってハラスメントと見なされて損害賠償請求に発展する可能性も否定できないため、細心の注意を払った対応が不可欠です。
まずは、事実関係を明らかにするための客観的な証拠を確保することが重要です。
以下に、確保すべき証拠の例を挙げます。
- メールやチャットの履歴
- 勤怠データ
- 経費精算システムの記録
- 防犯カメラの映像
事案によっては、他の社員等からのヒアリング内容も重要な証拠となり得ます。ヒアリングを実施する際は、日時、場所、発言内容などを詳細に記録し、書面として残しておくことが大切です。情報漏洩を防ぐためにも、調査は慎重かつ内密に進めるように心がけましょう。
ステップ2:本人への事情聴取
ステップ1で客観的な証拠を確保したら、必ず本人から直接事情を聴取するプロセスが必要です。一方的な事実認定は、その後のトラブルや法的紛争につながるおそれがあるためです。
事情聴取を行う際には、以下の点に注意してください。
- 聴取担当者は2名程度で対応する
- 長時間の聴取は避けて、30分から1時間に留める
- 高圧的な態度で自白を強要せず、話したくないことは話さなくても良い旨を伝えた上で、適切に質疑応答をする。
- 聴取の目的を明確にし、議事録を作成して本人に内容を確認させるように努める。
加えて、懲戒処分の有効性を確保するためには、「弁明の機会」を付与することが法的に重要です。就業規則にその規定がある場合、このプロセスを怠ると処分が無効と判断される可能性が高まります。事情聴取とは別に、「弁明の機会」を与えることが賢明です。
ステップ3:就業規則の懲戒事由に該当するかを確認
懲戒処分を行うためには、その根拠となる規定が就業規則に明確に定められていることが必要です。
ステップ1で確保した客観的な証拠とステップ2での事情聴取の内容に基づき、今回の虚偽報告が就業規則上のどの懲戒事由に該当するのかを慎重に照らし合わせる必要があります。
もし、該当する行為が就業規則のいずれの懲戒事由にも明記されていない場合、会社は原則としてその行為に対して懲戒処分を下すことはできません。この状況で無理に処分を進めると、その懲戒処分が無効と判断され、かえって法的トラブルに発展するリスクがあるため、細心の注意が必要です。
ステップ4:行為に見合った懲戒処分を検討・決定する
ステップ1から3で得られた客観的な証拠、本人の弁明内容、そして就業規則の懲戒事由を総合的に評価し、最も妥当な懲戒処分を慎重に検討するプロセスに進みます。この段階では、以下の点を多角的に考慮することが不可欠です。
- 行為の悪質性
- 会社に与えた損害の程度
- 本人の反省の度合い
- 過去の処分事例との公平性
各事情を踏まえて、処分の内容が重過ぎると、社会通念上の相当性を欠くとして、懲戒処分が無効になる可能性があります。
最終的に処分が決定した際には、本人に対して「懲戒処分通知書」などの書面で通知します。この通知書には、処分の内容、処分の根拠となる事実と、就業規則の該当条文を明確に記載しなければなりません。適切な手続きと客観的な根拠に基づく処分を徹底しましょう。
虚偽報告に対する懲戒処分の種類と選択の注意点
処分の決定には細心の注意が必要です。処分の重さが社会通念上不相当であると判断された場合、その処分が無効となる可能性があるためです。
以下の項目では、具体的な懲戒処分の種類と、処分選択における法的な注意点について詳しく解説します。
懲戒処分の種類一覧
従業員の非違行為に対する懲戒処分は、違反の軽重に応じて様々な種類に分けられます。一般的に軽いものから重いものへと段階的に定められており、具体的には以下の7種類が存在します。
以下に、懲戒処分の種類とその概要をまとめます。
| 処分種類 | 概要 |
| 戒告 | 厳重注意を行い、将来を戒める処分です。 |
| 減給 | 賃金の一部を減額する処分です(労働基準法に上限があります)。 |
| 出勤停止 | 一定期間の出勤を停止し、その間の賃金を支給しない処分です。 |
| 降格 | 役職や職位を引き下げる処分です。 |
| 諭旨解雇 | 従業員に自主的な退職を促し、応じない場合は解雇とする処分です。 |
| 懲戒解雇 | 企業が最も重いと判断した場合に、従業員を即時解雇する処分です。 |
まず「戒告」は、将来を戒める最も軽い処分です。続いて「譴責」は、始末書の提出を求め、将来を戒める処分を指します。これらに続く「減給」は、制裁として賃金の一部を減額する処分であり、労働基準法でその上限が定められています。
「出勤停止」は、従業員が一定期間働くことを禁止するもので、期間中の給与は支給されません。さらに重い処分には「降格」があり、役職や職位、職務資格を引き下げることを意味します。降格に伴って給与が引き下げられる場合があります。
「諭旨解雇」は、会社が従業員に自主的な退職を促す処分です。もし勧告に応じない場合は、懲戒解雇へと移行することが一般的です。そして最も重い「懲戒解雇」は、企業秩序を著しく乱した従業員を一方的に解雇する処分であり、退職金の一部または全部が支払われないのが一般的です。
懲戒解雇を選択する場合の判断基準
懲戒解雇は、従業員の地位を奪う最も重い処分であり、裁判所はその有効性を極めて厳格に判断します。安易な懲戒解雇は「解雇権の濫用」と見なされ、無効と判断される危険性があるため、会社側には慎重な検討が求められます。
裁判所が懲戒解雇の妥当性を判断する際には、以下の要素を総合的に考慮して判断します。
解雇の判断基準
- 虚偽報告の悪質性(計画性、常習性、動機など)
- 会社が被った損害の大きさや影響
- 従業員の役職や責任の重さ
- 本人の反省の有無や態度
- 過去の勤務態度や懲戒処分歴
解雇処分が不当解雇となり無効となると、会社は解雇時から解決までの社員の賃金(バックペイ)などの経済的な負担に加えて、他の社員の士気の低下や社員の社会的な評価を毀損するリスクがあります。
まとめ:社員の虚偽報告には毅然とした態度で適正な手続きを
社員による虚偽報告は、個人の問題に留まらず、組織全体の信頼関係を深く損ねるだけでなく、職場規律の乱れ、他の従業員のモチベーション低下、さらには経済的損害や企業の社会的信用の失墜といった深刻なリスクを引き起こします。
このような虚偽報告が疑われる場合、会社は感情的・場当たり的な対応を避け、冷静かつ客観的に適正な手続きを踏むことが不可欠です。これらの手続きのいずれかに不備があった場合、処分が無効と判断され、かえって法的トラブルに発展するリスクがあるため、細心の注意が求められます。
また、社員がミスや課題を一人で抱え込まず、安心して報告できる健全な職場環境を構築することが、結果として組織全体の信頼性と生産性の向上に繋がるでしょう。